風信 沼のほとりから 第51号 令和六年皐月
- クレマチス

- 2024年5月24日
- 読了時間: 1分
「・・・五月も終わり僅かになりましたがお元気ですか。茂みから蚊が襲来し狭庭に蚊取り線香の煙が棚引く近頃、初鰹到来のスーパーのチラシに心躍らせています。山遠い沼地なのでホトトギスの声は聞こえませんが青葉だけは溢れています。蚊に刺されて昨年使い残したキンカンを慌てて探す初夏の午後。垣根の紫テッセンの艶然たる花に大兄の健勝を確信しています。別便メールにて「沼のほとりから」五月号を送ります。・・・」
春硯さんからさりげなく大患を越えた近況を伝える風信が届きました。懐かしい三四郎と阿房列車の話題がリニア新幹線につながり、今回は枯れた印象の句が並んだあとで最終句のウツギの花の白さが鮮やかに残りました。


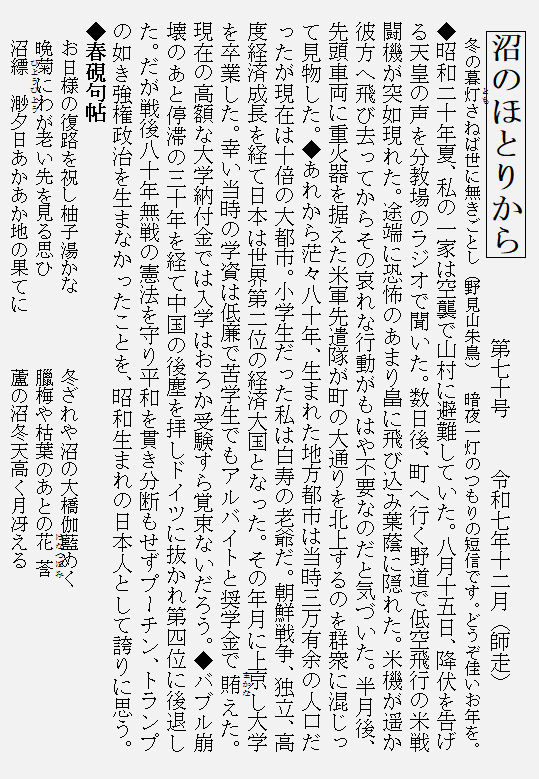


漱石の「三四郎」、懐かしいと言いたいところですが、実は私ちゃんと読んでいないのです。ただ、この主人公が上京する途上の浜松で中年男性と出会って交わす会話は、ちょっと癪に触って覚えていました。この男性は当時の日本をケチョンケチョンに貶し、富士山なんて自然のもので人間が創ったわけじゃないのに、それしか自慢するもののない日本が情けない、なんて言う。いや、それをいうなら大昔の人の建てたピラミッド、アクロポリス、ストーンヘンジなどで稼いでいる現代人の方が情けないような気もするけれど。
同じ宿の部屋で過ごした男女に何事もなかったのは、男に勇気がなかったからか。これは古い映画(1934年)It Happened One Night(邦題:或る夜の出来事)を思い出させます。主演の一人はクラーク・ゲーブル。バスで知り合った男女が懐具合から一部屋を共有することになり、互いの純潔(?)を守るため、真ん中にロープを張って毛布を掛け二つに分ける。からりとして面白い映画でした。
聖五月といえば、五月は欧州ではやたら宗教上の休日が多い月で、これらはキリスト教のカレンダーで復活祭から計算されるので毎年多少ずれますが、今年のペンテコステ(五旬節)はこの20日でした。たいていは、タンポポの綿毛やポプラの絮が盛んに飛ぶ時期です。それで
・五旬節祠の格子の絮払ふ
となりました。私が「ほこら」と呼んでいるもののイメージを掴んでいただけるよう、一例を添付します。
この中にマリア像が置かれていることもあって、春には
・聖母にも春愁ありや野の祠
という句を作ったことも。
葦の句。私は芦刈説話が好きで、季節を問わず何となしに葦の傍を素通りすることができません。コロナ禍の直前の真冬に私はちょっとした手術を受けたのですが、そのあと定期的に通院する必要があって、駅から病院への道にかかっている古い橋の下に枯れ葦が揺れているのをいつも目にしていました。
・枯れ葦や橋のたもとに陽を拾ふ
通院はしばらく続いて
・青葦となりても続く医者通い
という状況でした。葦と言えば、葦牙という言葉も私は好きです。氷解け去り葦はつのぐむ・・・かつてこの名の雑誌があったそうですね。
さまざまのこと思い出す、桜が終わって初夏の句を楽しませていただきました。
杖の身は申し訳ほどの花見かな 開花したと聞けばじっとしていては花に申し訳ない、、申し訳ほどの花見…このような花見も確かにございますね、、それでも見届けているよと言う気持ちは花にも伝わっている 鳥の日やかぼそき命籠の中 両手で抱え込んでしまえばうっかりすると折れてしまいそうなる骨で囲まれた生命もまた命、、か 谷津出れば遠く沼見ゆ五月晴 ゆるゆると晴れ渡った5月の空の下ご一緒に散歩した気分を味わえます 蘆青む沼のほとりや道の駅 毎年の風景なれど新たに青む蘆を見て、洗われたような目で見れば見慣れた道の駅もまた新たに出現したような錯覚にとらわれる 聖五月隻眼無胃の卒寿かな 聖五月、キリストのお母さんの生まれ月でしたっけ、、信者でなくても聖五月と呼びたい、今も愚痴ひとつ言わず機能している身の無事寿ぐ卒寿、万歳、、と言わせて下さいませ 卯の花よ吹き降りなれどゆめ散るな 卯の花の風趣がいかにも日本的…と言ったら他の国の人は何と言うだろうか? 花びらのまろみ、ぼんぼりのようなのほほんとした白はいつまでも見ていたい、、一緒に生きようぜ、の下五に揺さぶられます 寝床から起き上がって拝見していてよかったです、寝床でぐずっている場合ではない、、爽やかな朝になりました、ありがとうございました❣️