花の名前―ドイツの黒い森から 72(びすこ)
- クレマチス

- 2025年7月2日
- 読了時間: 11分
今年の五月早々、半世紀来の友人が東京の有名な S 病院で股関節の手術を受けた。股関節の問題は生まれたときからだそうで、若い頃にはほんの少しびっこを引いているかな、と思う程度だったのが、還暦を過ぎて母上の介護を一手に引き受けた時期から目に見えて悪化したという。その母上を見送ってのち 10 年余りそのまま仕事を続けていたのだが、それが年々厳しくなり、スペイン語の通訳として海外出張するのも無理になった上に、国内でも同時通訳のブースに出入りするのに同僚の手を借りる必要が出てきたというので、医師に相談したら「では 80 歳過ぎたら手術しましょうか」(現在 75 歳)と言われたそうである。
それを聞いた私ともう一人の、これまた長年の、友人は異口同音に「どうして 80 歳まで待つ必要があるの。」「仕事のことより、痛みを一日も早く鎮めることが大事でしょう。」「 80 歳で手術したら今より年を取っていて回復にもリハビリにも時間がかかるわよ」と早期の手術を促した。それで再度医師に頼んで手術の時期を早めて―と言っても遅すぎるくらいだが―もらったわけである。
簡単なリハビリも含めて 3 週間の入院という話だったので、手術後数日たって大きな痛みが消えてからは病院生活に退屈しているだろうと、私たち 3 人の間でのメールの交換が始まった。さすがに患者となるとあまり長いメールを書く力はないはずなので、あとの二人が見舞いの言葉の他に近況報告などして彼女の無聊を慰めており、殊に私の書くものは貧弱な内容ながら、楽に読めるならいいじゃないかと勝手にあれこれ書き連ねていた。
お決まりの時候の挨拶などして日欧の初夏の違いを綴り、この季節にはドイツのみならずその周辺国でも金雀枝(エニシダ)が野山を黄色く染めています、と書いてから、エニシダというのは日本ではあまり見かけない植物だということに思い当ってあれこれとその花の説明をした。
私はまだ日本にいた時期に花屋で小さな鉢植えを見つけて買ってきたことがあるが、おそらく土壌の関係で日本では蔓延らないこの植物の名前が「金雀枝」というのに興味を惹かれ、しかもそれをエニシダと読ませるのが不思議だったのでちょっと調べてみた。エニシダは英語では broom と呼び「箒」というのはその枝が箒のようだからというのは知っていた。トーマス・ハーディやブロンテなどヴィクトリア朝の小説を読んでいると、田園風景の描写の中でヒースと並んでこの植物がよく出てくる。
それで百科事典の写真などでエンドウ豆の花に似たこの花の姿を知ったのだったが(エニシダはマメ科である)、もう 40 年近く前の春にイスラエルに旅した時、到着の翌朝テレアビブを出てハイファに向かうバスの窓から海沿いにエニシダの咲き誇る風景が見られ、父があれはいったい何の花かと訊くので説明したことがあった。多分北欧を除きヨーロッパから小アジアにかけてどの地にも見られる花だが、地中海東岸では季節は西・中欧より2 か月ほど早いらしかった。
ドイツでは金雀枝は初夏の風物詩で、ヒース同様にやせたアルカリ性の土壌を好むため現在私が住む辺りの丘陵地や路傍は五月の声を聞くころには黄一色になる。同じく黄色で三月に盛りを迎える連翹は、植木だからエニシダほどは繁茂しておらず花期も短い。エニシダは花の力が旺盛で花期も長いのでその花粉で停めた車や住まいの窓が黄色く汚れ、窓拭きは 5, 6 週経って花が終わるまで待つのが常である。
ドイツに来てこのエニシダを何と呼ぶのか尋ねたら「ギンスタ」というので、なんだか似ているなと不思議だった。それも道理でラテン語名は Genista といい、そこからギンスタとなって、日本語のエニシダの語源も同じだという。
さらに、英国に昔フランス系のプランタジネット王朝( 1154-1399 )というのがあったが、そもそも同王朝の名はフランス側の祖であるアンジュー家の紋がエニシダであったところから、エニシダを意味する Plant Genista がプランタジネットになったというのが面白い。そんなことを面白がるのは暇人の私くらいのものだろうし、プランタジネット朝なんて世界史で習ったことも忘れている御仁が多いと思うが、私はこの王族の、特に王と王妃の丁々発止の対立をテーマにした映画「冬のライオン」( 1968 年、私が観たのは 70 年代)がいたく気に入っていたので、王朝の名も忘れられないのである。
しかし私がメールの中で強調したのは、エニシダに金雀枝という字を当てた日本人のセンスについてだった。入院中の患者を中心にしたディジタル鼎談の中で、私以外は東京の山の手に生まれ育ったせいか花や植物にさほどの関心は示さないが、三人とも外国語を使う仕事に携わってきて言語に拘りがあるという共通点がある。
かつてはフランス語の通訳・講師でその後日本語学に宗旨替えした金沢在住の友人は、私のメールを読んでミモザとエニシダを混同していたことに気が付き、調べたら「エニシダってスイートピーみたいなのね」とあって、さらに英語の「 broom(箒)」について魔女の箒もエニシダでできているとどこかに書いてあったと教えてくれた。そして、え、英語ではそんな風に言うの、と驚いた例はいくつかあるが、最近びっくりしたのはハナミズキを英語で dog wood と呼ぶことだという。
子供の頃に彼女が読んだ小説(英語からの翻訳)の中に「今夜の君はハナミズキのように美しい」という台詞があって素敵な表現だと感心したのだけれど、あれは原語では dog wood みたいと言っていたのか、とがっかりしたそうである。(一青ナントカの名曲「ハナミズキ」も英語のタイトルがドッグウッドではねえ、とあったが、この歌を私は知らなかった。)
*編集者注 一青窈(ひととよう)のハナミズキは
彼女の話から私が連想したのは、例の「赤毛のアン」の中のアンの台詞である。
ここでちょっと男性の皆さんに説明しておくと、私たち戦後生まれの「かつての」女の子、特に団塊世代の女子にとって L. モンゴメリーの「赤毛のアン」とオールコット女史の「若草物語」はいわばバイブルのようなものだった。その共通点があるので、成人してさらにバアサンになって後も、出身地や家庭の背景や生活環境がどれほど異なっていようと、「アン」とか「ジョー」というと、途端に「開けゴマ」のごとくに会話の流れに弾みがつくのである。
一つには、当時のまだまだ貧しかった日本において欧米は憧れの地であったことと、そして私などのように後に語学の道に進むようになる文科系の女子にとっては、アメリカやカナダの若い女性の生き方が光り輝いて見えたことに由るのだろう。
それで鼎談の中で「赤毛のアン」を持ち出すのに何の前置きも要らなかったわけである。
以下に私が二人宛てのメールに書いた内容を記す。
「(ハナミズキ云々のコメントで)頭に浮かんだのが、『赤毛のアン』の中のアンの台詞でした。彼女は人の名前でも土地の名称でも、その響きやイメージにひどく拘るのですが、それについて揶揄されると『薔薇は薔薇という名前でなくても同じように美しいなんて言う人もいるけど、私はそうは思わない。薔薇がキャベツという名前だったらあんなに美しく咲くことはないはずよ』なんて言う。
頂いたメールでそれを思い出したので、赤毛のアンの原語版を取り出してその箇所を読んでみました・・・原文は次の通りです。
I read in a book once that a rose by any other name would smell as sweet, but I've never been able to believe it. I don't believe a rose would be as nice if it was called thistle or a skunk-cabbage.
ここで気が付いたのですが、私が読んだ 60 年代初めの翻訳版には thisle に当たる言葉はなかったように思います。あったとしても、スコットランドの国花であるこの花のシスルという名称は、詰まらないとか無粋ということはありませんよね。(日本語の「薊」というのは結構良い名前じゃありませんか。)
薊はドイツ語で Distel(ディステル)と言い、音がちょっと似ています。オールド・イングリッシュでは thistel ですって。(中略)それよりも原文を読んだときに驚いたのは、薔薇という名称と比べられたのが私の記憶にあるキャベツでなく、スカンク・キャベッジとなっていることで、これ、水芭蕉のことなんですね。
訳者の村岡花子さんは、skunk-cabbage が水芭蕉のこととは知らなくて、あるいは知っていても面倒だしキャベツの方が分かりやすいから、それで済ませたのでしょうか。」
という具合で、そこから、日本人の間で人気を博した外国の少年少女小説が翻訳された大正から昭和初期にかけては今と違って西洋の事物・風物も習慣も知られていなかったので、翻訳家は対応する日本語を探すのにさぞ苦労しただろうという話になった。だから、当時の翻訳の間違いやズレを必ずしも指弾するわけにはいかない、という私たち 3 人の寛容さは、自身が翻訳を手掛けた経験があればこそ、だろう。
勉強家で好奇心の強い金沢の友人は、それだけでは足りず、水芭蕉について植物に詳しい人にいろいろ話を聞いたそうで、「水芭蕉はサトイモ科の植物であり、世界一醜い花として有名なショクダイオオコンニャクの親戚なので悪臭を放つことは十分考えられるそうです」と書いてきた。
実はサトイモ科というのはなかなか面白い植物で、例えばザゼンソウなどもその中に含まれ、私はこちらの林の中で、春には可愛らしい達磨のような姿をしていたこの植物が秋になって真っ赤な実をつけているのに出くわし、「座禅草座って実る赤い秋」なんてふざけた句を作ったことがある。
サトイモ科については多少の知識はあった一方で、初耳だったのはエニシダをスペイン語で「イエニスタ」ということで「そう、あの有名なサッカー選手イエニスタと全く同じ綴り・発音だそうです。イエニスタ選手はエニシダ選手だったんですね」と言うのだが、私はそのイエニスタ選手をまるで知らないのであった。
*編集者注 日本語 Wiki ではイニエスタ Andrés Iniesta ですが、私の問い合わせに対するびすこさんの返信メールでは、
「イニエスタに関しては、私もよく分からないのです。ウィキで調べるとスペイン語でもgenistaでしたから、文字は同じでもスペイン語の読み方は違うのかな、とも思いました。でもその友人にイニエスタのことを教えてくれた人はスペイン語の専門家なんですって。さらにこのやりとりについて、入院していた友人が、スペイン語のかなりの権威であるにもかかわらず何もコメントして来ないので、大きな疑問は抱きませんでした。・・・」
それにしても、一青よう(この人の漢字が出ない、読み方も分らなかった)のハナミズキの歌といい、「あの有名なイエニスタ選手」といい、ほとんどの日本人が知っているらしい事柄に無知なのは、必ずしも外国に住んでいるせいではなくて、私は昔からクイズ番組でも「スポーツ」と「芸能」の分野はお手上げなのである。(懐メロは好きで、それに関する知識ならわりと自信があるが。)
そしてクイズの中に「植物」「花」のジャンルが滅多にないことを残念に思いつつ、そんな知識が何の役に立つのか、というのが大方の意見だろうと察してはいるけれど、しかし花の名前を知っていることは、こちらでの生活に文字通り花を添えてくれている。上記のザゼンソウ然りで国が違っても植物は季語になるから便利である。
ミズキについては「亡き父を語る姉妹や水木咲く」という句を詠んだことがあり、これは今から 30 数年前の 4 月上旬に父が逝って翌月、妹と里帰りして父親の思い出を語っていた時、庭にミズキの花が咲いていたからである。その妹も今は亡く、庭のミズキも老いて花の数も少なくなった。
ということで、今回のブログを終えるにあたり、夏の句をいくつか披露させていただきたい。半分は日本での、あるいは日本を思い出しての句で、残り半分は欧州で出会った植物にインスピレーション(というほどのものでもないけれど)を得た句である。
(日本版)
・合歓木の花弁透かして夕の星
・碑(いしぶみ)の苔にも花は咲きにけり
・その中に横たふ夢や朴の花
・落ちてなお姿まったき凌宵花
・蹲踞(つくばい)に花びら投げて空木散る
・ままごとの旬のおやつは蛇苺
・蔵の扉(と)の重さや柿の花落つる
・どくだみの薄闇避けて隠れ鬼
・花落ちの胡瓜を齧る帰郷かな
・鉄橋の走行音に真菰(まこも)揺れ
(欧州版)
・汗ばめる額(ぬか)にそそぐ香見上ぐれば 春を送りてアカシアの咲く
(アカシアの花で夏が始まる。)
・誰が植えし見張りの塔のゼラニウム
・降るごときラヴェンダーの香や星月夜
・牡丹散る咲き初めし日の約束で
・万緑やウインナワルツの漏るる窓
・闇に眼が慣れて退く薔薇(そうび)の香
・ピレネーを越えて金雀枝夜も耀(あか)る

(スペインの聖地サンチアゴ・デ・コンポステラに旅した時の風景から。写真 1. はピレネーの金雀枝)
・白き花枝離(さか)る頃夏至の宵
・梅花藻や水鳥の雛育ちけり

(梅花藻・バイカモについては滋賀県米原市醒井宿の清流が有名で、テレビでこれは日本にしかない花と言っていたが、写真 2. のように私たちのアルザスの常宿の後ろを流れる小川にもこの花は咲く。それまでに白鳥も鴨も春からの子育てを終えている。)
・やまぼうし列なして咲く公園の花のうしろに着信メロデイー
(ヤマボウシもミズキ科)

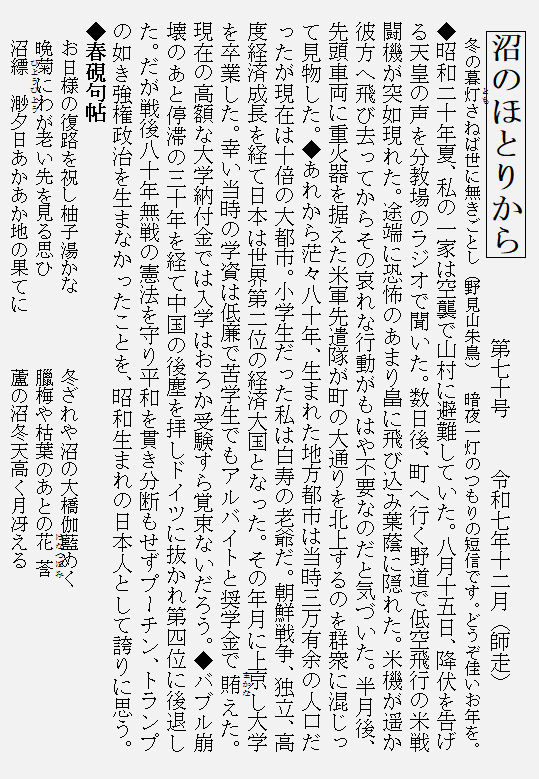


打てば響くように、共通の話題で盛り上がるなんともおうらやましいご交際ですね。皆さんが広く深いご経験があればこそお話は尽きませんね。
ずいぶん気前よく俳句、歌、披露してくださいました、率直でおおらかに広がる絵画を見るようです。その場の空気感まで伝わって参ります。繊細なゆらぎ…びすこさんの世界ですね…ありがとうございました。楽しめました。
合歓木の花弁透かして夕の星
蔵の扉の重さや柿の花落つる
どくだみの薄闇避けて隠れ鬼
花落ちの胡瓜を齧る帰郷かな
降るごときラヴェンダーの香や星月夜