白いペスト――ドイツの黒い森から 45(びすこ)
- クレマチス

- 2022年10月18日
- 読了時間: 10分
この「白いペスト」という言葉が結核を指すものであることは、かなり昔から、それもかなり多くの人の間で常識だったようだが、非常識で無知な私がそれを知ったのは、恥ずかしながら(今さら恥じても仕方ないが)ほんの数年前、忘れもしない 2019 年の暮れのことだった。
その時期私は日本にいて、師走の声を聞く頃に以前から読みたいと思っていた山崎正和の「世界文明史の試み」上・下巻をやっと手に入れ、ところが間もなく手術が必要になったので、その前後もっぱら通院の列車の中でそれを読むことになった。山崎正和の名前はもうだいぶ前から聞いたことがあったが、この人が書いたものを最初に目にしたのは、90 年代半ばに日本経済新聞の第一面に掲載されたコラムにおいてである。
文壇その他の分野で著名な確か 5 人ほどの人物が交代で担当するコラムはさほど長くはなく、第一面にあるのでいやでも目につき毎回読んでいた中で、山崎氏の文章は格段に中身が豊かで鋭く示唆に富んでいた。調べて大阪大学で教鞭をとっていることが分かったので、当時阪大の大学院にいた友人に訊くと、かなり有名で講義も人気があるが自分は聴講したことがないとのことで、密かに「まあ、もったいない」と思ったものだった。
以来この作家・批評家のものは何冊か読んでいたが、あるとき「世界文明史の試み」の書評らしきものをネットで見て(発行から既に何年も経っていた)興味を喚起され、3 年前の帰国時に郷里の町の本屋に頼んで取り寄せてもらった。そもそも題からして分かるように作者が取り組むのは厖大な文明史、別の言い方をすれば人類史・人間史であるから決して読みやすくはなく、そのアプローチもしばしばシロウトの意表を突くようなところがあった。
その上巻の序において、山崎氏は〈健康な身体の普遍化〉と題した節で次のように述べている。
〈しかし何といっても、近代から現代にかけてもっとも顕著な現象は、この地上に健康な身体が溢れ、それとともに健康についての意識が世界的に高まり、裏腹に死と病気に対する忌避感が世界を覆ったことだろう。
その第一の原因が医療の進歩にあったことは先にも述べたが、とくに化学薬品による細菌性の伝染病の制圧があずかった成果にはめざましいものがあった。近代以前、当時の先進世界だった西洋にもたびたび疫病の大流行があって、それぞれの疫病が歴史上の一時代を画するという現象が見られた。人々が特定の病気を時代の宿命と見る共通感覚が生まれ、それが宗教や文学や人生観に影響を与えたのである。〉
続いて中世の黒死病すなわちペストという災厄がもたらした無常観や悲観主義、東洋では「天刑病」などという恐ろしい名で呼ばれたハンセン氏病、さらには梅毒にその命を蝕まれた多くの思想家・芸術家(シューベルト、ニーチェ、それからハイネも)に触れたあと、
〈だが「時代の病」といえばその最大のものは、やはり 19 世紀以降の結核であることに疑いはあるまい。その脅威から「白いペスト」の異名をとった結核の猖獗は、いうまでもなく工業社会の到来と、それが惹き起こした都市への人口集中の副産物であった。劣悪な栄養と衛生状態、密集した住居と労働環境は、古くからあったこの病気を爆発的に増幅させた。それはたちまち中流以上の若い男女をも侵して、その精神状態にも深い影を落とすことになった。症状の苦痛があまり激甚でなく、死への過程が緩慢だという病気の特色は、若者の思考や感情を奇妙な形で刺激した。小デュマの「椿姫」からトーマス・マンの「魔の山」に至るまで、多くの文学や芸術の素材となったという意味で、結核ほどたんに肉体のみならず、時代の精神をも支配した病気はほかにないだろう。〉
と記している。
この本を読んで数年が過ぎた今頃になってそこに見た「白いペスト」という言葉とその病がある時代に及ぼした影響を取り上げているのは、例のコロナからの連想ではなく(これも「なんで今頃」という話になる)、今月初めに夫と休暇を過ごしたスイスで読んだ雑誌記事がきっかけである。
ドイツ語の新聞も持っていった日本語の本も文字が小さくて疲れたので、気楽な雑誌でも読もうとホテルにおいてあった Landliebe(ラントリーベ)という季刊誌をめくったら、繁茂する樹木に囲まれて丘陵に立つ大きな古い建物の写真(写真1)が目に留まり、旧ホテルかと思えば「ゴッタルド-サナトリウム」とある。
(このラントリーベというのは近年ドイツ語圏で発行されて好評を博している「田舎暮らしの楽しさ」紹介のいくつかの雑誌の一つで、おそらくは 19 世紀末から今日まで英国で根強い人気のある Country Life という雑誌にヒントを得たものと思われる。)

写真のキャプションには「ゴッタルドに旅する人はこの威風堂々たる建物を列車またはアウトバーンから見ることができます。場所はピオッタの南向き斜面です」とある。ゴッタルドはスイス北方のドイツ語圏から南のイタリア語圏に旅する際に必ず通る場所で、かつては峠を越えていたが今は自動車トンネルがあり、また 2016 年には世界最長の鉄道トンネルが新たに開通した。ピオッタはイタリア語圏のティチーノ州の村で、私たちもロカルノやマジョーレ湖に行くのには面白くもないトンネルを避けて峠を越えることが多かったので(この 10 年あまりご無沙汰だが)、チラリ程度には目にしているはずなのに全く記憶にない。
しかしそれにしても凄い建物だなあ、と記事を読んでいくと、その案内役を務めている 79 歳の男性は、かつてこのサナトリウムで患者の治療にあたっていた医師の一人の息子であった。フラヴィオ・トネッラ氏が子供時代を過ごした自宅はサナトリウムのすぐそばにあり、父親は彼がサナトリウムで働く人たち、園丁や厨房係や清掃人と普段接することを別に制限しなかったという。病室だけは禁じられていたが、それもこっそり入って患者と談笑することもあったそうだ。医師が来ると患者のベッドの下に隠れたりして。

当然ながら、有名医師のいる立派なサナトリウムにおいて澄んだ空気と陽光と良質の食事で結核の治療を受けられる人々は富裕層で、20 世紀初めの頃の高級ホテルと見まがうような設備は往時の写真から伺える。(写真 2 は 1905 年当時のもの。上の写真は戸外での静臥療法のためのベランダ、下の写真は患者のための食堂で、食事は一日 6 回、昼と夜とは 5 品のメニューだった。)
ティチーノ州はイタリア語圏だけあって明るい南欧の雰囲気と清涼な山々の景色とで欧州各国から多くの観光客を惹きつけてきたが、観光業が本格化したのは 19 世紀末の鉄道敷設以降のことだった。それに目をつけて、結核という当時の業病さえも商売の種にしようとここに静養のための豪華な施設が建設されるが、経営もイタリア風であったのか設立後数年で傾き、そのあと第一次世界大戦中は兵士を治療する軍の病院となるなど、常時順調な経営とはいかなかった。
このように紆余曲折はあったものの第二次大戦後まで何とか維持され、結核は裕福な人々の贅沢な病気という、当時欧州に流布したイメージに寄与した。この疾病にかかるのは貧しい労働者層ももちろん多かったが、免疫の無さもあって中・上流層も次々と病魔の犠牲となり、さらに罹患するのは 20 代の女性と 30 代の男性が多数を占め、病人は青ざめて肌の色は透き通るように白く頬は微熱で赤らむので、美男美女の病とまで言われたという。
そこから結核患者を登場させる小説や詩が生まれたわけだが、その点は日本も似ており、1898 年から新聞に掲載されて読者の紅涙を絞った徳富蘆花の「不如帰」などは、さすがに私の世代が読むには古すぎたものの、「人はなぜ死ぬのでしょう」「千年も万年も生きたいわ」という浪子の台詞は昭和中期まで周囲で話題になっていたものだ。
幸田文の「おとうと」も 10 代で結核に罹って世を去った実弟との物語である。長女と妻に続きたった一人の男の子を失った露伴の胸中はいかばかりであったろう。
個人的には結核に関する文学作品で最も胸を打たれたのは、宮沢賢治の「永訣の朝」という詩であった。賢治より二つ年下の妹トシが 24 歳で逝ったとき彼が詠んだ「けふのうちに/とほくへいってしまふわたくしのいもうとよ」で始まる絶唱に、少女の私はしばらくさめざめと泣いた。
結核と詩人との組み合わせとなれば、ビジュアルに私の頭に浮かぶのは英国詩人ジョン・キーツである。ロンドンの貸馬業者の息子に生まれ 25 歳という若さでローマの地に没したこの詩人の肖像を見ると、夢見るような瞳といい、その華奢な体格といい、まさに才能に重ねて結核という病をミューズに着せられた芸術家の化身とも見える。(この人の傑作の一つにTo Autumn〈秋に寄せて〉という美しい詩があって、この季節になるとよくその出だしを思い出す。)
他にも、「風立ちぬ」や「菜穂子」で知られる堀辰雄、正岡子規その他の歌人・俳人、詩人の八木重吉(彼もまたキーツの詩を愛した、そして秋が好きだった)、さらに、腎不全が死因とされているが結核を病んでいたという森鴎外など、近代日本の文学者の中にもこの病に侵され「末期の眼」で人生を眺めていた人々は少なくない。明治 29 年(1896 年)の夏、彼女の死の 4 カ月ほど前に露伴が鴎外の実弟三木竹二とともに訪ねて、後年自分の娘に「薄皮だちで血のさしきが早かった」とその印象を語った樋口一葉も、皮膚が薄く色白という結核患者の風貌の典型だったらしい。
また、かつて結核に罹ったことのある知人(もうとうに世にないが)の話によると、胸の病をかかえている間はなぜか神経がひどく鋭敏になり、いやがうえにも感性が研ぎ澄まされてくるそうで、この人も病床で歌を詠むことを覚えたと言っていた。
話をゴッタルドのサナトリウムに戻して、それが最終的に閉鎖されたのは 1962 年、今からちょうど 60 年前のことだった。その背景には、結核菌に対する抗生物質ストレプトマイシンの登場で治療効果抜群の化学療法に切り替えられ、ドイツ語で Liegekur と呼ばれる静臥療法が過去のものとなったという経緯がある。
上記ラントリーベ誌の記事によれば(たかが田舎暮らし推奨の雑誌と侮れない)、1882 年にロベルト・コッホが結核菌を発見してこれが伝染病であることを明らかにし、そして 1928 年には英国人アレキサンダー・フレミングによってペニシリンが開発されていたものの、結核菌を退治するストレプトマイシンが世に出るまでにはさらに 15 年余りを要した。
考えさせられるのは、数あるスイスのサナトリウムのうち、ダボスのそれ(トーマス・マンの妻がここで療養し、その時に見舞った経験から「魔の山」が生まれたことは有名)を初め国内の大規模な療養施設はその後建て替えられて現在も様々な用途に活かされているのに対し、このゴッタルドのサナトリウムは打ち捨てられたままで今は廃屋と化しているという事実である。
しかもそういう廃墟や幽霊屋敷を好むフリークが頻繁にここを訪れてインターネットで写真を配信しているというが、これらの素人写真家や自称冒険家がゴッタルド詣でを始める前から、閉鎖されたサナトリウムでは「立入り禁止」の標識など完全無視で破壊・略奪行為が横行し、利用出来る物はすべて持ち去られ不要なものは打ち壊され、壁や天井は醜悪な落書きで今は見る影もない(写真 3 )。この廃屋の管理に責任を負うのはティチーノ州であるから、案内人のトネッラ氏は同州の行政に大いに問題があるのだと憤慨している。
これは多言語・多文化の共存に成功しているはずの「模範国」スイスの影の部分を示しているのだが、その点には今回は触れない。

さて、冒頭で言及した山崎正和氏であるが、私が手術後の手当てを終える頃に始まったコロナ騒動で日本を出られずにいた 2020 年の 8 月にその訃報を新聞で知った。そこであらためて既に読み終えた「世界文明史の試み」を一部再読し、
〈現代人の意識にとっては、病気はすぐれて医学の問題であり、栄養と環境の改善という意味でせいぜい政治と経済の問題ではあっても芸術や文学の主題などになる機会は乏しく、時代の共通感覚を育てる可能性も少ないといえるだろう〉
という記述をそこに見て、その死の直前に同氏も聞き知ったはずのコロナ禍をこの人はどう捉えていたのだろうと思ったのだが、その問いかけは、あれからさらに 2 年余り過ぎても世界が疫病から解放されずにいることで切実になっている。
いずれそのうち、コロナ禍時代に人々が共有した感覚をベースに新たな文学作品が世界のあちこちで誕生するであろうか。あるいはコロナの災厄は「時代精神」を生むには短過ぎ、また犠牲者の多くが高齢者であるこの病気は文学者や芸術家の目には散文的で、ほどなく忘却の彼方に消え去るのだろうか。

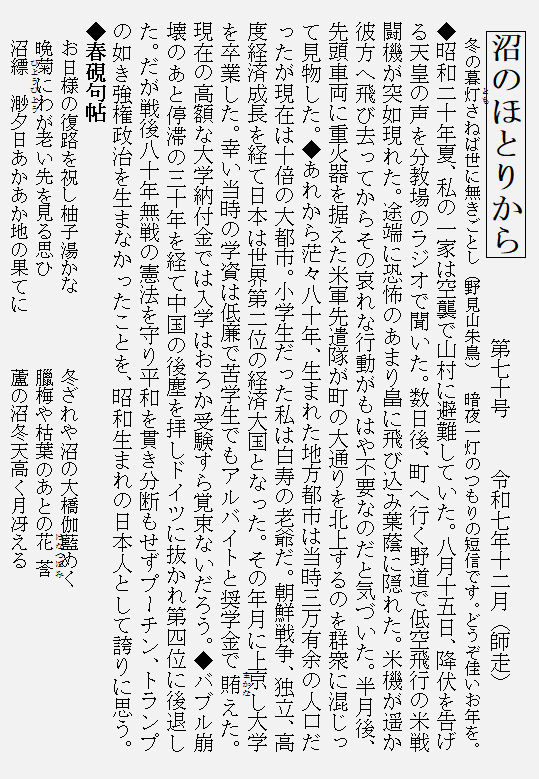


おやすみになっちゃったのでは強制できませんけど、目覚めの暁には良いお返事がありますように。こっちは朝までまだ12時間以上ありますので。
いつも丁寧なコメントをありがとうございます。
まず、ブログに一つ間違いがありますので、それを訂正してから。露伴の言葉で「血のさしき」とあるのは「血のさしひき」の誤りです。さっと青ざめる、さっと赤くなる。これ面の皮の厚い色黒人間だとほとんど目立ちませんね。
私の高校時代、自身は腎臓を悪くして1年休学しましたが、ほかに一人1年遅れてきた女子がいて、聞けば結核の療養でということでしたから、そんな遠い昔の話ではありませんね。やはり色白でほっそりした人でした。1964年のことです。当時は「ストマイつんぼ」などという言葉も聞かれました。ストレプトマイシンで難聴になるケースが結構あったようです。
そうなんです、建物の汚され方、絶句しますよね。そしてここに汚しにくるのはドイツ人が一番多いようです。地理的に近いということもあり、ドイツ人がヨーロッパの中で一番ひどいというわけではありません。
この破壊の欲求「バンダリズム」は欧州のあらゆる国で猛威を振るっていて、みんな蛮族バンダル人の血を引いているのだろうかと考えますが、中東・北アフリカからの移民も壊し好きで、絵は大体下手ですけれど壊し方はゲルマン民族顔負けです。アメリカでこの種の行動が頻繁なのは、欧州から新大陸にやって来たゲルマン系の子孫たちが率先して始めたことなのかもしれません。つまり本場は欧州?
これに関連して、日本に来た欧米人が最初に何より驚くのは、壊された公器や落書きが非常に少ないことです。公衆電話(90年頃までの話)が全部機能する、自動販売機がきれいに保たれている、わー、信じられないよう!というコメントを私も何度か聞きました。
そうだ、ちょうどいい機会ということで一つお願いしてよろしいですか。私は今ちょっとしたきっかけで「在宅介護」について興味を持っているのですが、いちまるさん、お母様を何年か自宅で介護なさいましたよね。私は断片的にしか伺っていなくて、その断片を繋ぎ合わせようとしても、かちねっとの頃のブログはもう見られないし、フォーラムもずっと以前のまで辿るのが手間過ぎる(面倒くさがっている場合じゃないけど)ので、一度まとめてフォーラムに書いて下さいませんか。原稿用紙で5枚程度。え?原稿用紙なんて今は使わない?そうか、では2000字くらいでいかがでしょうか。いや、思い出をあれこれと書き連ねて下さるだけでいいのです。
またいつものように一気に読ませていただきました…お陰様で、今読んでいる魔の山、の時代背景もよく分かりました、小説の風景と建物に至るまで楽しくつながりましたがコロナ禍と文学がつながるとは到底思えませんね、、文学的でない世の中、ちょっと辛いかなと、、それともたっぷり文学的なのにうかつにも見落としているのかどうか今どっと疲れているのでまた持ち直した時にゆっくり考えたいと思います…でも今回のご投稿を拝見していて少し息抜きができましたと言っては失礼ですが…息抜きは生存上欠かせないものです、ありがとうございました😊 (魔の山、主人公のいとこで軍人のヨーアヒムがまたサナトリウムに帰ってきたシーンでストップです。 もしかしたらびすこさんが述べてらっしゃるサナトリウム療養生活みたいな死の影が色濃くある環境の死の影を薄くした生活ぐらいは努力すればできるんじゃないかとは思いますが結構難しいです。ぼくの日常生活もややこしい事からは逃げまくっていますが追いかけてくるものは対応しなければなりません。自分でまいた種ももちろんあります。 とりあえず気持ちを落ち着けるために…部屋のそこここに重なっている本の山が目障りなので見えないところに隠しました、ないことにする、便法を多用してきた僕にとってはわけないことです、来週には…また読書生活に入ります、なんてかっこつけたりして…近況報告まで済ませてすいません、あ、もう一言…おかげさまで魔の山、読み通す気になりました、それと人のいない建物の汚され方がアメリカ的なのにびっくりしました、ヨーロッパも深いところでアメリカに毒されている…あはは、毎度失礼しています😅)