男が素敵に見えるとき――ドイツの黒い森から 18(びすこ)
- クレマチス

- 2021年8月3日
- 読了時間: 7分
なんだかえらくミーハーなタイトルですが、はい、私、ミーちゃんハーちゃんなんです。
今から 24, 5 年前のこと、事務所で一緒に仕事をしていた女性たちが、その数日前のテレビ放送で「どんなときに男性が魅力的に見えるか」を語るトーク番組があったとかで、あなたはどう?と質問し合っていた。
彼女たちの話によると、自動車の運転席の男性が車をバックさせるのに肩越しに振り返って後ろの障害物の有無を確認する、その動作が素敵、という意見が多かったそうな。
このバアサンも意見を訊かれたので(おや、気を使ってくれて)、特に考えもせず「男の人がネクタイを外すときっていいわね」と答えると、ああ、そういう意見も結構ありました、とのことであった。
深く考えずに答えたのは、実際にネクタイを外す姿を見て「いいな」と思った経験があるからだが、考えてみるとこれはちょっときわどい発言ですよね。小説やドラマなんかで見られるように、ホテルで不倫するときのシチュエーションになる。
いやいや、私はそういう状況下で私のためにネクタイを取ってくれる男を嬉しそうに眺めたわけではありません。でもこれもあまり否定すると逆効果になるから、話を先に進めて。
昔あるところに、ではなく、あれは 1984 年だから 37 年前、場所は遠い南アフリカでの出来事である。仕事の依頼主は南アの貴金属販売促進団体で、日本の新聞記者や作家、要するに物書き商売の人達 8 人が南アを旅していろんな記事やストーリーを書くことになっており、私はその取材の通訳を仰せつかったわけだった。
ヨハネスブルクの鉱山企業本社の訪問もあったし、プレトリアの国会も見学したし、土日は豪華な観光プログラムが組まれてセスナ機で象やライオンを見に行ったりした。しかし旅の第一の目的は鉱山見学で、金山もあるにはあったがほとんどがプラチナ鉱山であった。
当時は無論アパルトヘイトの時代で、名誉白人として扱われる日本人の立場に居心地の悪さがあったことは言うまでもない。(今この件を話題にすると長くなりすぎるので、現在の南アの無法・無秩序状態と合わせていずれ。) だが当時ほどなくバブル期に入ろうとしていた日本は貴金属消費者としては大切なお客さまだったから、極めて丁寧な扱いを受けた。そんな中で私が心を動かされたのは、鉱山技師の大部分を占めていた旧東欧圏の人々がみんな穏やかでとても親切だったことだ。
鉱山運営の技術面はオランダ系のアフリカーナーに任され、算盤をはじくのは英国系というのがどこでもお決まりのパターンだったが、採掘現場の技師に東欧からの人が多いのはなぜかと思ったら、彼らはみんな戦争孤児で、ポーランドやチェコを占領したソヴィエト軍が「厄介者」として幼い彼らを家畜運般列車で南アに送ったのだという。南アは戦争難民の受け皿だったわけである。
私はチェコ生まれだという男性とチャスラフスカのことを話したりした。「チェコの女性って美人が多いですよね」と私。答えて「うん、うちにも一人いるけどね」、これには日本人から「俺も一度言ってみたかった」の声あり。ポーランド出身者たちとは「森へ行きましょう」を合唱した。
(話が飛ぶが、最近東京の友人からのメールに「ロウ菅の歌―ある樺太流刑者の足跡」という本の著者(先川信一郎)が私より少し若い高知県出身者だが、知りませんか、とあり、調べていくうちにアイヌ人とポーランド人の繋がりを知り、それが昨年の直木賞受賞作「熱源」(川越宗一)のテーマということも分かり、さらに 20 世紀初めに日本がシベリアにいた 750 余人のポーランド孤児を救ったこと、そのためポーランド人が日本に特別な思いを抱いていることなどを知った。問い合わせてきた友人は日本語教科書出版社の社長で、「ポーランドの小学校で 1. 2. 4. 5 年生が日本語必修、来年は 6 年生も」とあった。そんな話を当時知っていたら。)
鉱山は広大で当然都会にはないから宿泊施設が限られ、記者や作家は何とかゲストハウスに泊まれたが私の部屋が確保できないとのことで、鉱山長の家で一晩を過ごすことになった。アフリカ―ナーの方が差別意識は激しいと聞いていたけれど、鉱山長さんは本当に優しく穏やかで、多分私など子供のように見えたのだろう、慈父のように接してくれた。
翌日坑内の見学を終えて(黒人労働者の医療施設なども廻った)昼食の場に移るとき、案内してくれた人が私に「今日あなたは名誉男性ですからね」と言う。は?と首をかしげると、昼食をとるクラブハウスは英語でいうスタッグ・クラブ〈スタッグとは雄鹿のこと〉、つまり男性のみ出入り可能な施設なのだが、通訳がいないと困るので例外的な措置になったとのこと。
さてそこでの和やかな食事が終わり、プレゼントの交換になって日本からのおみやげが手渡され、それに対して鉱山側から見学者グループの団長さんに差し出されたのはネクタイであった。
団長さんはさる工業新聞の年配の編集長で、白髪頭のずんぐりしたオッサンだった。その編集長、もらったネクタイを見て、おお、これは素晴らしい、ありがとう、と儀礼にかなう態度を取ったと思った次の瞬間、それを差し出した鉱山技師長の胸元を指し、「だけど俺、そっちがいいな」と言ったのである。
さあ、どうしよう、と困っていると、訳す前に技師長はオッサンの意図を察し自分のネクタイを指して「これが欲しいのですね」と訊くやいなやさっとネクタイを外して相手に渡した。そして引き換えにオッサンのじみ~な冴えないネクタイをもらって、それを締めた。
このときの技師長のスマートな反応と所作とに私は惚れ惚れしてしまった。この人はスコットランド人で実に男らしく、私は今でも名前を覚えている。この旅から帰って私はしばらく「鉱山(やま)の男っていいな~」と言い続けていた。
ということで、不倫相手のネクタイ外しに心奪われたわけではないのです。
しかし私はその後、ネクタイを外す動作よりも、ハンドルを握って肩越しに振り返るしぐさよりも、もっと男が素敵に見えるケースと遭遇することになる。
その前にちょっとだけドイツ語のレッスン。仏語もそうだが、英語のYouにあたる二人称には二通りあって、ドイツ語の場合には丁寧な Sie(ジー)とカジュアルな Du(ドゥ)が用いられる。丁寧と言ったが、敬語の常で Sie は相手との間に距離を置く人称で、ドイツでは狎れ合ってはいけない間柄、部下と上司、顧客と業者などの間で使われ、家族や親戚同士、友人間では Du と呼び合う。
夫の会社で彼が Du と呼んでいる社員は一人もいない。身分でなく立場の違いをはっきりさせるのがドイツの流儀で、これは差別ではない。立場は変われる。逆転もありうる。
またドイツは基本的に名字の文化で、呼びかけるときはミスターに当たるヘア (Herr) を付ける。アメリカ辺りでは知り合ってすぐに「ロンと呼んでくれ」などと言うが、ドイツ語圏ではまずそれはありえない。ヘア・シュミット、女性ならフラウ・ミュラー等。馴れ馴れしくファーストネームで呼ぶのはご法度である。
だから夫も同業者、顧客、供給業者との会話ではほとんど Sie であり、その種の礼儀が守られてこそ長い付き合いが可能と考えている。
ただ、何かの節に、あ、この男とは Du で呼びあってもいいな、と思ったときにそれが変わり、以後はファーストネームの関係になる。これを duzen (ドゥーツェン)といい、「 Du で呼ぶ間柄になる」という動詞である。
この変化を起こすのは年長者もしくは目上の人の側からの提案で、年下の人が「お互い Duにしようよ」ということはできない。ドイツ人というのは、今でもかなり形式や古来のルールに拘る国民なのである。もっともうちの亭主は 80 を越えた老人で、付き合う人達も相応の年齢、だから平均よりも保守的・古風な環境にいるともいえるけれど。
あるとき、同業者の友人の誕生パーティがあってでかけたが、そこの営業マンがなかなか気持ちのいい男で夫は気にいっており、このイベントで会えるのを楽しみにしていた。相手は10 歳ほど若く、もちろんまだ Sie の仲である。
パーティが始まる前にバーで一緒に飲んでいたとき、ふいに年上の夫が「僕の名はハンス」と言って手を差し出した。すると相手は「僕はトーマス」と応じて、二人はしっかり握手した。
これで、今後はドゥーツェンですよ、他人行儀は無しだよ、ということになる。ちょっと儀式っぽくしかも男の可愛さが感じられて、ほのぼのとした場面である。
前述の通り、ドイツ人は本質的に堅苦しく(そのイメージを変えたがっている人は多いが、そうすると妙に不自然でぎこちなくなるので、メリケンさんの真似など止めた方がいい)、Sie から Du に切り替わる瞬間を目にすることはあまりないけれど、目睹すると野暮なドイツ男もなかなかのもんだと思う。
普段から「ハーイ、ロルフ」「ハーイ、ジョー」などとダラダラしていないだけに人間関係にメリハリがあって、堅苦しさが解ける一瞬がとてもいい。
そんなわけで、ネクタイを外すしぐさよりもさらに男が魅力的なのは、Sie から Du に切り替える握手をする姿です。


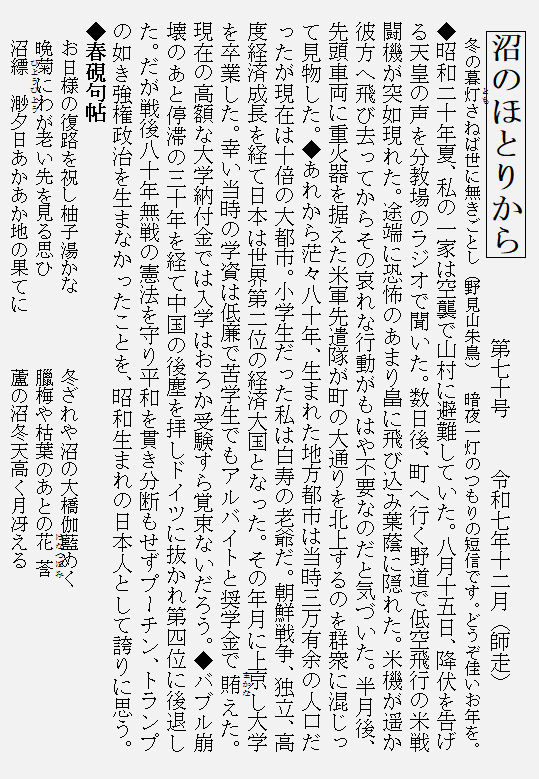


封土授与、貸与、、、あたりのシステムが似ていた事はなんとなく納得できますね。ご褒美で喜ぶのは犬と同じ、時代が下ってあげるものがなくなって茶器だの絵、美術工芸品を代替品、さらには分捕り品が給与がわり、あたりも似ているとすると…人間の考える事はそんなに違いはないと言うことでしょうか…あはは🤣
(この大村さんのコメント、フォーラムの方から持って来ました。びすこ)
びすこさんがブログにあげてくださった#18にコメントを何度アップしてもエラーになってしまいますので…こちらの方でお答えさせていただきます…これをご覧いただきますように、、なるほどなるほど、込み入っているように見えて説明を伺うとなるほどですね。 Sieから Duの間柄になる瞬間、うーん🧐、
自分が所属する社会ルールに則った所作とタイミング…その内容が傍目にも心を許せる関係になったと確認できるシーン、、、たまたまそんな場面に遭遇できたら、きっとそれは傍目にも気持ちの良いものだと思います。ただし、それは状況を全て理解できる人だけに可能なわけですね、このシーンは使わせていただきます、それとお話に付随してくる当時の状況が大変貴重です、いつもありがとうございます、 (これはドイツの黒い森🇩🇪ブログへのコメントでした)