洪水小史――ドイツの黒い森から 17(びすこ)
- クレマチス

- 2021年7月23日
- 読了時間: 8分
ドイツには“Nach uns Sintflut(ナハ・ウンス・ジントフルート)という格言がある。直訳すると、我々の後の洪水、という意味で、そう、かのポンパドール夫人が言ったとされるAprès nous le délugeのドイツ語版。この場合の洪水はドイツ語でもフランス語でも「ノアの洪水」を指し、「我々が死んだあとでノアの洪水があったって、そんなの知ったことか」という意味で、一般に「あとは野となれ山となれ」と訳される。
ナハ・ウンス・ジントフルートというのは日常でも結構耳にすることがあり、特に政治家があれこれと偉そうに詭弁を振るったり偽善的な演説をしたりすると、大衆は「ふん、あいつらは自分の身の安全のためにゴチャゴチャ言ってるだけで、この俺が死んだあとはどうにでもなれ、というのが本心さ」と嘲り、そこで「我々のあとのノアの洪水」となるわけである。
目下のドイツの洪水、正確にはもたつく洪水の後始末と犯人騒ぎの狂騒を見ていると、いやでもこの表現が頭に浮かぶ。しかしいくら目下の自分の保身のためとはいえ、政治家たちはもう少し冷静な議論ができないものか。
二酸化炭素で地球が熱くなり、それで水蒸気がどんどん発生して降雨量が増し、こんな大洪水が起きた。従ってこの悲劇に責任があるのは、今まで車社会にブレーキをかけようともせず、CO2 を排出する企業を野放しにしておいたこれまでの政権(主にキリスト教民主連合と社会民主党)である。しかも苦しんでいるのはドイツのみではない、これら二大政党は世界の億単位の人々の死に責任がある。
等々、これまで与党になったことがない政党(「緑の党」はちょっとだけ連立で関与したことがあるが)が憎悪剥きだしの形相で口を極めて現政権を罵るのを聞くと、理性も判断力もないこんな連中が政権を握ったらどんな政策を打ち出すかと恐怖に襲われる。
そもそも、今回被害の大きかったラインランド・プファルツの州政府は、数年前まで社会民主党と緑の党との連立だった。環境保護を大きく掲げ「世界を変える」という意気込みで州の環境省を担当したが、解決策なるものは風力発電オンリー。野も山も道路脇も風車だらけとなり、喧しいし(かなりの騒音が発生する)、景観は損なわれるし、喜ぶのは風力発電装置を製造する半国営企業のみで、さすがに住民は「もう結構です」と最近の選挙でこの政党にお引き取り願った。
しかし失うものが何もなくなると、この緑の党と左翼党とは以前にもまして獰猛さを露わにしている。
そこへ、メルケルの後継者とされるキリスト教民主党の党首が被災地を訪れ、何だか知らんがジョークを言って愉快そうに笑っているようすがカメラに捉えられ全国に流された。打ちひしがれている被災者を見舞いに行って、ヘラヘラ笑うか? この男、相当おつむが弱いと私は見ていたが、悲しいことにそれが当たってしまった。
しかしさらに恐ろしいのは、まだ少数派とはいえ、この推定有罪人の弾劾に加担する国民がいることで、しかも彼らはかなり真面目にガソリン車を廃止し工場を潰したらドイツと世界を救えると思っているらしい。
政治のバランスのために産業支援の自由民主党もいるのだが、今の世論ではあまり勝ち目がない。企業は悪者なのである。そもそも政治の議論やトークショーにこの政党は呼ばれず発言の場がない。メディアは右を嫌うので顔を出すのは圧倒的に左派。ただしメルケルはキリスト教民主連合をかなり左に押し寄せたというのでジャーナリストには人気があって、左派も彼女の悪口は言わない。まあ、いいや、公正な判断は後人が下してくれよう。といってもその時分は私も泉下の人だろうけど。
(ただ、メルケルは「あとは野となれ」とは思っていないはずである。良くも悪くもこの人にとって名誉と人望は命以上に大事で、死後の評価への妄執もある。一応この 9 月で政界を引退するそうだが、いやいや、静かな老後など送るものですか。ちょっと休養したらまたまた何らかの形で「国際舞台」に踊り出てくるに違いない。ノーベル平和賞もまだもらってないし。低能の男を後継者にしたのも、おそらく自分との差を見せつけるだめだろう。)
それにしても、いまメディアや各政党が好んで口にする「前代未聞の災害」という表現に私は大いに疑問があって、少しばかりドイツの洪水の歴史を調べてみた。
この関心は今回の災害のためだけでなく、これまで私はライン河畔の町をいくつか訪れたことがあるのだが、そこで古い住居や公共の建築物の壁にこれまでの洪水の際の水位を示す目盛りを目にしていた。それが近年のものに限らず、数世紀前のものもあり、信じがたい水位を示す印も残っている。柱のきずはおととしの・・・いや、数百年前の洪水の規模を示しているわけである。
それらがどの町だったか記憶が定かでないものの、そういえばエルベ川河畔でも、またドナウが他の二つの川と合流するオーストリアに近いパッサウでも、ドイツ語でいう「ヴァッサーシュタント(水位)」のマークはあったっけとインターネットで調べてみた。
わりとすぐにあちこちのが見つかった。その一部をここに披露しているのだが、一目瞭然なのは、大洪水は二酸化炭素なるものが増えた 20 世紀・21 世紀に集中しているわけではない、ということである。

1. ローゼンハイムの水位マーク(イン川)

2. ラウエンブルクの水位マーク(エルベ川)
ただし、写真 1 と 2 に見るように、新しく書き直したものはほとんどが 20世 紀以降で、これは古いのも全部記入しているときりがないということで、19 世紀以前のはよほど大規模でない限り(エルベ河畔のラウエンベルク 1855 年、イン川沿いのローゼンハイム 1897 年など)省略してしまったのだろう。
それを示唆しているのは写真 3 のパッサウの水位で、これは印をつけた建物(貯水塔らしい)自体がかなり古いので、16 世紀、18 世紀、19 世紀の記録がばっちり残っている。

3. パッサウの水位マーク(ドナウ川)
しかし調べていて私が最も驚いたのは、ハノーファー・ミュンデンに残る洪水記録だった。(ミュンデンは「川が注ぐ」とか「流れ込む」という意味で、この地名はドイツ中にいくつもあるので、混乱しないよう近くの大きな自治体の名前が付される。)氾濫を起こした川はヴェーザー、ここで合流する河川が三つあり、周囲一帯が水浸しになった。
氾濫の時期は 1342 年 7 月の 19 日から 22 日にかけてで、災害の範囲は東のウィーンから西のフランクフルトまで、南北でいうとドイツを横に三分割した中央の部分がほぼ全部水浸しになった。
原因は、その年の降雪が異常に多く春は寒くて雨模様だったのでどこでも川の水かさが増したためだという。3月・4月までのアルプスの雪が夏になって平地を襲ったわけである。近年の温暖化でアルプスの氷河が減り積雪も少なくなって、それが欧州にダメージを与えているというが、雪が多ければ多いで大災害につながることをこの水位マークは示している。
このミュンデンでは、14世紀のそれよりはマシとはいえ16世紀・17世紀にもやはり大洪水があった。近年そこの名前が聞かれないのは、おそらく川の流れの制御や堤防の整備がなされてきたためであろう。ほーら、本気になれば防災は可能じゃないの。

4. ハノーファー・ミュンデンの水位マーク(ヴェーザー川)
新聞には、バングラデシュやインドのひどい水害も温暖化のせいで、ということはカーボンを出している先進国に責任があると書かれているが、黒い煙朦々のダッカやインドの町の炭酸ガスの量をこれらの記者は知っているのだろうか。
それより何より、私はバングラデシュに行ったとき、町の汚さ、人々の貧しさよりも、離着陸の前後に飛行機から見下ろしたこの国の地理的条件にまさに絶句した。ラグーン(潟)というか洲というか、海沿いの町村のかなりの部分が水の中なのである。工業が余りないので水は澄んでおり、その砂地のようなところに頼りなげな柱を立てて家を作っているので、水位が数センチも上がれば家の中(といっても四方の壁もろくにないが)は水浸しになる。
聞けば、毎年モンスーンで壊れてまた建て直すので、しっかりした作りにすることには意味がないのだという。そういう暮らし方もあるだろうが、しかしそれで洪水・冠水を先進国のせいにするのはちょっと言いがかりに近い。いや、バングラデシュの人が文句を言っているのではなく、欧米の進歩派がそう主張しているのですけどね。
日本など随分開発援助をして、これで国民にマシな家を建てさせて下さい、とか、インフラを整備して下さい、などと勧めているけれど、毎回、あら、あの資金、どこへ消えたの?になる。もっとも日本の政治家が現地で真っ先にやることは、自分の名前を冠したナンチャラ館とか、ドウタラ公園などを作ることだと、これは政府の海外開発推進組織のプロジェクトを請け負った建設会社の人が言っていた。
新聞といえば、昨日の NZZ 紙の国際欄を開いたら、オーストラリアはニュー・サウス・ウェールズ州での鼠の大量発生のニュースがあった。もう、ものすごい規模でもちろん既に何万匹と殺したがそれでは追いつかず、殺鼠剤を使うと他の動物に影響があるので禁じられており、町中・村中が死んだ鼠の腐臭で住めなくなったという。鼠の集団自殺を待つしかないというところらしい。
この鼠の繁栄で大いに潤っているのは、川の魚と蛇だという。大きな魚がいて喜んで捕まえたら、その腹から三匹の鼠が出てきたとか。餌の鼠がいくらでもいるので蛇も大繁盛しているそうだ。
この辺りは過去数年降雨量が極端に少なく旱魃に苦しんでいた。それが今年は雨が普通に降って草も伸び、家畜用の干し草も作れた、と喜んでいたところ、旱魃で大量発生した鼠にほとんど全部食べられてしまったという。
住民は「温度が下がって、そして雨がたくさん降ってくれると、鼠は減るんですがねえ」といっており、問題は雨の多寡でなく降雨量の適切な「配分」にあるようだ。しかしこればかりは人間の力ではどうにもならない。それとも緑の党に任せれば、欧州の雨を減らし、豪州の雨を増やすことができるのかしらん。

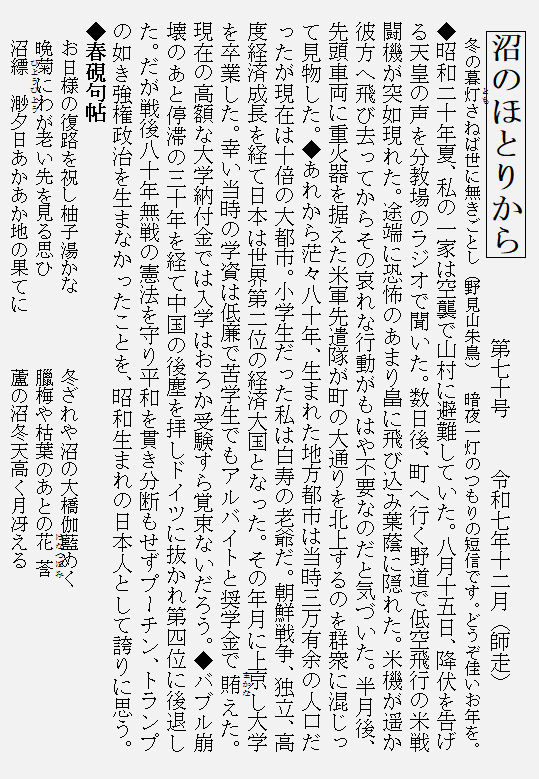


それにしても、ラシェットさんの被災地でのこの表情はいただけませんね。
被災地で略奪行為が多いなんて、地続きの国では大昔から他国から襲われることに慣れてる国民性がそうさせるのかしら?日本は海に囲まれているので他国に襲われる可能性はなかったから国民皆仲間うちという認識が被災地泥棒が少ない理由なのかな~?
メルケルが後継者にしたキリスト教民主連合の党首(ラシェットという)のことをボロクソに書いて罵ったので、なんてお品が無い、と思われた方もいるでしょうけど、彼の失態をお見せしたら、どなたも納得して下さるでしょう。
普段のラシェットは、どこにどもいる気の良さそうなオジサンという印象。のんきな父さんのイメージといっていいかもしれません。でもシャープなところや特筆すべきところは何もない。メルケルの太鼓持ちで出世したような男です。
このラシェットが被災地に行ったら、すでにドイツ大統領のシュタインマイヤーがいて、被害者たちを前に演説をしていました。「おお、なんとお気の毒なみなさん、でも大丈夫ですよ、私はあなた方の悲しみに寄り添って・・・」この人、お涙頂戴のスピーチはお手の物の偽善者政治家だから。
日本では知られていませんが、ドイツ連邦共和国でプロトコル(儀礼)上、最高位にいるのは、政治力はほとんどなくて飾り物・象徴的な意味を持つだけの大統領です。立憲君主国なら国王・女王・天皇ということになりますが、共和国では大統領が名目上はトップです。(フランスと米国だけは大統領の立場がちょっと違いますが。)
ちなみにドイツで第二位は首相ではなく、連邦議会の議長(現在はショイブレ)、第三位が首相です。これは実際の権力とは関係なく、あくまでも国の儀礼の話です。しかし政治家や官僚はこの決まりを無視することはできません。(一般市民、まして私のような者が、ふん、大統領なんかただの金食い虫じゃないか、というのは「自由」です。)
ラシェットはいやしくも国会議員ですし、政治家として活動するなら国家の儀礼は守らなければなりません。ところが、大統領が(あまり意味がないとはいえ)スピーチをしている後ろで、プロトコル上は臣下にあたる彼は取り巻きと雑談をしていた。そしてジョークを言ってアハハとなったのです。
さあ、並み居る取材記者の喜ぶこと!!見ろよ、こんなバカがメルケルの後釜なんだってよ、とさっそくネットでも新聞でもその馬鹿っぷりが報道されてしまいました。
写真をご覧ください。この顔でどうやって被災者を慰め励ますのでしょうか。
それにしても、こんな能足りんを後継者としたメルケルという人間が私には全く分かりません。
洪水の到達水位、歴史とともにしっかり刻みつける文化…絵になりますね、うちらの国は電信柱か何かに新築マンション売り出しの張り紙と見紛うような推定水位表示がなんとも安っぽい。でも負けたとは思わない。洪水との親和力?はうちらのほうが大先輩だと思うからです。最近新聞は読まない僕ですが、びすこさんのお便りが楽しみです、このコーナーの隠れファンが多いわけだ…風の便りと言うけれど…どこの新聞社も伝えてくれないヨーロッパの今の風が僕らに届く…ありがとうございます😊