旧交蘇る-1 ――ドイツの黒い森から 64(びすこ)
- クレマチス

- 2024年5月20日
- 読了時間: 13分
漸くドイツも 1 年で最良の季節に入った。見渡す限りの若葉の新緑、それが澄んだ青空のもと日々色濃くなっていく。ドイツには Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün (五月さん、来ておくれ、そして木々をまた緑にしておくれ)で始まる唱歌があって、モーツアルトの作曲とされ日本でも知る人ぞ知る歌らしいのだが、私はこちらに来るまで聞いたことがなかった。ドイツに移って間もない時期に私が「早春譜」をハミングしていると夫が、「お、五月の歌だね、もう覚えたの」というので何のことかと思ったことがある。なるほど、メロディが一部似ている。
しかしその前の四月の気候は今年もひどかった。それについては April, April, er macht was er will(四月ってやつは自分のしたいようにする)と嘆く格言があり、要するに四月の天気は予想不可能ということで、その通り今年も雪あり雹あり霰あり、その合間にお愛想のように晴れてみたり。
その四月の下旬のある日、またしても雪まじりの雨が降る中を夫の業界のイベントでザルツブルクに向かった。出発は午後だったから車での旅が少々悪天候に祟られても、翌日晴れてくれるなら別に構わない。
ザルツブルクまでは 6 時間近くかかり、80 代も半ば近い夫にそれほど長く運転させたくないので、途中ミュンヘンの手前で一泊して一挙に走るのは一日 3 時間以下に抑えようと当初は考えていた。それで行き帰りに宿泊するホテルを予約しようとしてふと思いついたのは、管理人の M さんに運転を手伝ってもらうことだった。彼は MS(多発性硬化症)という厄介な病気を抱えていても普段は元気だし運転が大好きだし、何より 1960 年代の東独生まれとあってドイツ国内やその周辺にあまり旅したことがない。聞けばオーストリアにも行ったことがないそうな。
ザルツブルク滞在は 2 泊 3 日なので、彼に同行してもらって大部分運転を任せれば往復の中途でホテルに泊まる必要がなくなって、ザルツブルクでの彼のホテル代くらいすぐ賄える。私は二日目には夫を会議に送り出したら暇なので町を散策しようと思っていたが、Mさんが来てくれれば、ザルツカンマーグート(地図参照)と呼ばれる周辺の地をドライブすることができる。湖水地域や有名な観光地を案内する好い機会だ。Mさんは私の依頼を二つ返事で引き受けてくれた。

霧雨の中を到着した夕方には既に着いていた 4, 5 人の同業者たちとホテル内のレストランで食事し、その中の二人はオーストリア人だったので彼らの勧める郷土料理とデザートを注文した。面白かったのは、その一人が M さんのアクセントを耳に留めて「東ドイツの人なの」と尋ねたことで、彼自身はウィーン近郊の生まれだがお母さんが旧東独のベルリン近くの出身で子供のころからその方言を聞いているためすぐ分かったのだった。
翌朝はピッカピカの日本晴れ、いやドイツ語でいう皇帝晴れとまではいかなかったものの、雨は免れて M さんと私は元気よく出発した。田舎の景色ならシュヴァルツヴァルトも長閑で美しいが、大きな違いはオーストリアのアルプスである。頂を雪で覆われた山並みに Mさんが歓声をあげる。行き先はバート・イシュルという町。ザルツブルク市内の見物は、翌日に夫の会議が昼まであるので午前中に回れば十分だ。
バート・イシュルについて M さんは聞いたこともなかったそうだが、同行が決まったとき私がそこを訪ねようと提案してあったので、家で奥さんに話すとインターネットで調べ「まあ、フランツ・ヨーゼフ皇帝とシシ(エリザベート皇后)がお見合いして婚約した所じゃないの!」とえらく興奮していたそうだ。さすがに共産主義の東独に生まれた女性ですら、オーストリア帝国のこの美貌の后妃については興味も知識もあるらしい。オーストリアのみかドイツの特に南部でも(シシはバイエルン王国の王女だったので)このカップルは今に至るまで大変な人気で、バート・イシュルの町は若き皇帝がエリザベート姫を見初めてたちまち婚約の儀となったエピソードを誇り、カフェやレストランや店など至るところに二人の肖像画が掛かっている。そしてその華やかな物語にふさわしい優雅で洒落た街並みが今に至るまで維持されている。
私は早速いくつかの目ぼしい場所に案内したが、歴史を知るにはカイザーヴィラ、つまり皇帝の別荘を見るのが一番と M さんを連れていった。これで三度目か四度目である。入口で切符を買おうとしたらえらく高いので、見るだけでこの料金?と怪訝そうな顔をすると、これには別荘内のツアーの分も含まれています、と言う。このツアーも私は二度ほど経験があるから、つい「あなた見たい?」と M さんにぶっきらぼうに尋ねてしまった。そう訊かれれば「いや、結構です」と答えざるを得ないではないか。気の利かないことだった。
最初は別荘の広い敷地を回るだけで十分だと思ったのだが、館の前に来て M さんはちょっとだけ覗いてもいいかという。もちろん、と応じて入口のホールに入ると何人かが次の回の館内ツアーに加わるために待っていた。それがあと 10 分後である。カウンターの女性に訊くとツアーの切符はここでも買えるというので、M さんに「せっかくだから見ていらっしゃい、私はあそこの喫茶で待っているから」と言って押しやった。
全館を回るのに 45 分ということだったのに、1 時間経っても帰って来ないので先の女性に「どうしたんでしょう」と尋ねると「たまに質問が多くて長引くこともあります」と言う。1 時間 10 分して漸く戻って来た。察するに、一番あれこれ質問しまくったのは M さんだったらしい。奥さんへの土産話として出来る限りの情報を仕入れたかったのだろう。館内の土産物店でもインテリアの飾りや小冊子を買っていた。
そして私に、こういう逸話を知っているか、とか、フランツ・ヨーゼフの癖や習慣について聞いたことがあるか、などと質問するので、「知ってるわ、中国人もアメリカ人も案内したことがあるから、皇帝夫妻について 20 分程度の講義ならできるわよ」と笑った。
大袈裟でなく、フランツとシシに関しては別にこれという興味もなかったのに、何の因果かそれまでにいろんな話を仕入れる羽目になった。正直なところ、ゴシップやスキャンダルめいた話(皇帝夫妻の唯一の男子ルドルフ皇太子の情死は「うたかたの恋」という映画にもなった)が最も記憶に残っているのだが。
しかし関心というなら、フランツ・ヨーゼフが実質的にハプスブルク家の最後の皇帝となった経緯や、それまでのハプスブルク=ハンガリー二重帝国の時代、さらにその前にマリア・テレジアがロートリンゲン家から婿を迎えて 16 人もの子供を産んだ件―その一人がフランスに嫁いだマリー・アントワネットである―や、もっとずっと昔に遡って 15 世紀以降の神聖ローマ帝国の歴代皇帝などについても、ごく表面的ではあるが読んだり聞いたり(テレビの歴史番組で)していた。
ところでこのヴィラを訪ねる前に、到着してから陽が照り始めた中をあちこち歩いたこともあって小腹が空いたので、私は M さんを Zauna(ツァオナ)という有名な菓子店・カフェ・レストランに誘った。町には二つのツァオナがあり、ショッピング街のそれは品数が多くて土産物を買うにはいいが、オーストリアらしい雰囲気を味わうにはもう一つの、川べりの散歩道の奥にある優雅なカフェの方がいい。
川向うにレハール(「陽気な未亡人」等のオペレッタで知られるハンガリー生まれの作曲家)の記念館を見ながらカフェに着いて、テラスはまだ寒いからと中に入ると、昼には少し時間があってかなり空いている(写真 1 はその内部)。選り取り見取りで席を選んで座ろうとしたら、ウェイターが素早くやってきて「お食事ですか、それともお茶を?」と訊く。

ヨーロッパではだいたい客にすぐサービスをすることは珍しく、待たせてからおもむろにやって来て「ご注文は?」というのがウェイター、ウェイトレスの沽券とでもいう風なので、あらま、と思いながらウェイターの顔を見て、アッと思った。
とっさに「私あなたを知っているわ!」と言うと、彼は驚いている私に「ええ、さきほど奥さまが入って来られた時、すぐに、あ、あの方だと分かりました」と顔を輝かせた。こちらも少し息を弾ませながら「ホテル・フューベルクにいらした方ですよね。今はここで?」と尋ねた。
ホテル・フューべルクというのは、上記の地図のヴォルフガング湖のほとりにある絵のように美しい宿で、住所はモーツアルトの母親の出身地サンクト・ギルゲン町だが実際は同じく湖の北の端の、その町の中心のちょうど対岸にある(写真 2 )。立地と景色は抜群だが、ホテルそのものは取り立てて豪華な造りではない点もいい。すぐ前が水なので水泳もできるし観光船の乗り場もある。特徴はオーナーが毎朝舟で魚を漁りに出て、収穫物をシェフである奥さんが料理してくれることだ。

日本からやって来た妹夫婦を案内してザルツブルクの近辺をドライブしていたとき、偶然この隠れ宿を見つけたのが 2005 年。以降、しばらくは毎年のようにここで休暇を過ごしていたのだが、そのうちこのホテルが大人気となってなかなか予約できず、ときにはそこから少し離れたビルロートというホテルに泊まることもあった。ここも悪くはなく、ビルロートというのは有名な同名の外科医(ドイツ人だがウィーン大学医学部でも教え、ウィキにも出ている)が住んでいた屋敷を改築した宿で、ロビーや階段の重厚な造りに古きよき 19 世紀の建築の名残がある。しかし何といってもフューベルクのアットホームな雰囲気が好きなので、選べるならそちらに泊まっていたのだが、コロナ前の何年かはザルツカンマーグートに旅することも稀になっていた。
ツァオナで再会したウェイター、マイク(ミヒャエルの略称)との最初の出会いはフューベルクを利用し始めて間もなくで、あるときマロニエの木の下のテーブルで食事した私がそこにカメラを置き忘れたことがあった。暗くなってから気づいてもしやと見に行ったがテーブルの上には何もなくて、半ばあきらめていると、翌日シェフの奥さんが「マイクがこれを見つけました」とカメラを私たちの朝食の席に持ってきた。その時、お礼にと夫がかなりの額のチップを渡したこともあり、私たちのことはマイクの記憶に残っていたらしい。
それから少ししてマイクはいなくなり、と思ったらザルツブルクの喫茶店でお茶を飲んでいた時にウェイターの中に彼の姿を見て私が声を掛けた。人の顔を覚えるのが大の苦手の夫は私が見知らぬ人に話しかけたとびっくりしていたが、マイクが「ああ、あのカメラの方」と言ったので思い出したらしい。その後またフューベルクに行くと彼はそこに戻っていて、「ええ、またここで働いています」と照れたように言った。そして私たちにはちょっとだけ特別なサービスをしてくれた。
その後はオーストリアへの旅というとウィーンとリンツの顧客を訪ねるのが主で、観光目的の旅行はほとんどなくなり、フューベルクともしばらくご無沙汰であった。しかし懐かしい場所であることに変わりはなく、今回もバート・イシュルへの途中でヴォルフガング湖沿いに車を走らせている M さんに「向こうに白っぽい建物が見えるでしょう、以前はよくあそこに泊まっていたのよ」と指さして説明したりした。
だからマイクとの再会は 7, 8 年ぶりだったのだが、私がアジア人であるためもあって一目で「あ、あの」となったらしい。そして M さんにちらりと目をやりながら、今日はご主人様は、と訊くので、「彼は今日ザルツブルクで業界の会議に出ています。こちらは主人の会社で働いている M さん、運転してもらっているの」と簡単に説明した。「それで、お変わりないですか。」「ええ、84 歳でまだ働いています、呆れるでしょう」と私が言うのに、「それは結構なことじゃありませんか」と驚いた風もなかった。こちらでは長いのですかと質問したら「 6 年になります」とのことで、コロナの時期も何とか乗り越えられたという。
バート・イシュルは M さんには初めてだと言うと、それでは是非当地の特別メニューを召しあがっていただかねば、とまずテーブルに真っ白いクロスを敷き「カイザーシュマール(パンケーキの豪華版)」のものすごくでっかい一皿を持ってきて、ミネラルウオーターやコーヒーや至れり尽くせりの丁寧なサービスをしてくれた。
食べながら M さんにマイクとの馴れ初めを説明し、昼食目当ての客で少し立て込んで来た店内の彼の様子をそれとなく見ていると他のウェイターやウェイトレスに指示を出していて、どうやらここのチーフらしかった。大皿を片づけに来た彼に「フューベルクとは今もコンタクトがありますか」と尋ねたら、「ええ、妻があそこの受付で働いていますので」とはハピー・サプライズだった。では是非また主人と参らねば、というと、はい、どうかいらしてください、それからここにも、と丁寧な物腰で「ご主人にくれぐれもよろしくお伝え下さい」と繰り返す。
打ち明けて言うと、私が彼に少し特別な興味を抱いたのは、一つにはその容貌のせいだった。背はさほど高くなく髪はアッシュブロンド(くすんだ金髪)、やや鉤鼻で若干いかつい印象もあるが、特筆すべきは目の色だ。緑がかった薄いグレーで、それだけなら時にドイツ人の間でも見かけるけれど、澄んだ水のようでもあり夜の猫の眼にも似ており、これはバルカン半島のセルビアやブルガリアの人々に見かける瞳である。輪郭がくっきりして、誤解を招く表現かもしれないが「野生」を宿した風貌と言える。
以前に出身地を聞いたら「この近くです」と言っていたが、もしかして先祖はバルカン半島から移住してきた人だったのかもしれない。というのは、オーストリア=ハンガリー二重帝国はその名前が示す以上に多民族国家で、ポーランドの南部、チェコスロバキア、ルーマニアなどを含み、第一次大戦勃発の契機がサラエボでのフェルディナンド皇太子夫妻の暗殺であったことから分かるように、現在のセルビア、クロアチア、ボスニア、ヘルツェゴビナなども帝国に属していた。
そしてそれをドイツ系民族の専横と捉える向きも多いが、実際には皇帝を「帝国の父」として多くの一般人は独自の言語や文化を保ちつつ穏やかな共生を実現していた。フランツ・ヨーゼフ皇帝は子供のころから帝国領土の民の言葉を学ぶよう義務付けられ、ハンガリー語はもちろんチェコ語やルーマニア語なども話せて訪問先では常にその地の言語で会話したという。
夫と私は昨年の初秋に上記のオーストリア人の同業者にさそわれてスロベニアでのイベントに参加する機会があったが、ウィーンからは車で 3 時間ほどのこの国の、イタリアの雰囲気を漂わせるアドリア海沿岸の町もかつては帝国の一部で、オーストリア人が「ここには昔ながらのオーストリアがある」と強いノスタルギーを口にしていたのが印象的だった。
四月末のオーストリア旅行は M さんには新鮮な驚きと雑多な知識をもたらしたようだが、私はこの旅でマイクと再会したことから、オ―ストリアというかつての大国・現在の小国の歴史と運命を改めて考えるようになった。
それで帰宅して参考文献や論文記事をインターネットに探したら、ティモシー・スナイダー(Timothy Snyder)という米国の歴史学者(主に東中欧が対象でロシア・ウクライナも含む)の「ハプスブルク家の終焉」という小論文があり、これは 2014 年に新チューリッヒ新聞に掲載されたもので短いながら「噛み応えがあって滋養に富む」読み物であった。このイエール大学教授の著書は日本でも翻訳がかなり出ているらしい。
フランツ・ヨーゼフ皇帝ではないが、スナイダーも第一次資料に直接当れるようにとその研究範囲に含まれる国々の言語 11 か国語をマスターしたという。そのことも、そして現在のEU とオーストリア=ハンガリー二重帝国との比較も、ドイツ人その他の欧州人には見られない斬新かつ冷静なアプローチで、さすがアメリカ、腐っても鯛の国と思わされると同時に、マイクとの再会が未知の分野への扉をほんの少し開けてくれたような気がしている。



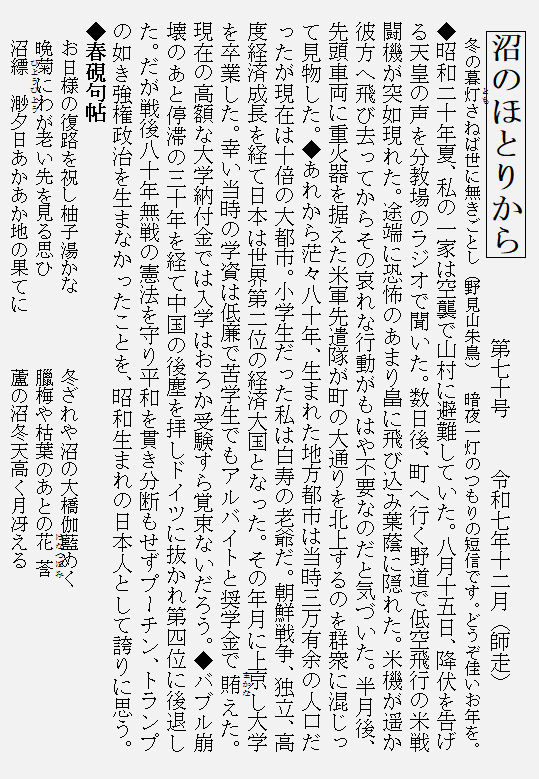
今の欧州は移民問題に悩むと同時に、「多様性」が強調され、いろんな国の人間を入れて共生を図ろうとしていますが、実際は手厚い福祉制度で働かずにすむので労働力とはならず、最近はアジア(インドより東)の人の働き手が増えました。彼らは主義主張をあれこれ主張せず黙って働く。でも欧州人は、「近東・中東」ならまあ仲間だけど、アジアは他人という見方です。歴史的経緯もあるのでしょうが、これで「世界に開かれた欧州」が聞いてあきれる。
現在欧州人の多くが唱える「多様性」というのは、既にオーストリア=ハンガリー二重帝国では自然な形で存在していたようです。一応の統一があって、これという差別や搾取も無くて、一般人のレベルでは特に不満も無かった。それなのに「民族」という概念が出て来て、特にバルカンの南スラブ人などはゲルマン系ドイツ・オーストリア人に支配されるのは我慢ならないと言う。ポーランドやチェコなど西スラブ人の一部もそれに同調する。この民族主義をゲルマン嫌いのフランスや英国が利用してさらに煽って、そこにアメリカが加わって第一次世界大戦になるのですが、オーストリアやハプスブルク家が何か悪いことをしたわけでもない。ヒットラーが台頭した第二次大戦前のドイツとは違います。
その民族主義の勝利で戦後はあちこちで独立運動が起き、実際独立を達成した国も多かったけれど、第二次大戦後はソ連の台頭でその脅威に立ち向かう必要が出てイデオロギーが幅を利かせ、それからやっとソ連が崩壊したら、自由を謳歌できるはずの国々の発展がどうもはかばかしくない。独立した小国も以前からの大国や昔の宗主国の支援なしではやっていけない。それで「助け合おう」と欧州連合(EU)なるものが生まれて拡大され、民族主義者の声が次第に小さくなって、少なくともEU内では国境は姿を消し「欧州人」として振舞おうということになったわけですが、これはオーストリア=ハンガリー二重帝国がとうの昔に実践していたことです。
フランツ・ヨーゼフを始めハプスブルク帝家やその領土内の王家の連中が帝位・王位と家系・血統と王朝継続にああも拘ることがなければ、順調にミニEUあるいは立憲君主連邦国に推移できていたはずなのに。(スイスは多言語・多民族・多文化の共存に成功しているではありませんか。)以上は無知無教養なアジア女の感懐であり勝手な説なのですが、まあ、こういう見方もあっていいんじゃないでしょうか。
Mさんにとって忘れられない旅になりましたね♪ びすこさんも懐かしい出会いがあって人のつながりの妙に驚きます。 前にも言いましたが僕の最初の相棒が仕事でヨーロッパに少し滞在した時…ヨーロッパなんて歴史を知らなければ何も面白くないとよく言っていたことを思い出しました。 風光明媚な土地柄に名家の別荘が残っていて、歴史が今に伝わり土地の人にも旅行者にも口の端にのぼり、亡くなった人の肖像画が当然のように展示されている…当然ではないですよね、、僕の友人の気持ちが少しわかりました、、事情を知れば知るほど理解が深まる…知らなければ、、あるいは知ろうと思わなければ歴史書の写真を見るが如し、雰囲気を味わってお終い。 美しい写真と一緒にちょっと覗いてみた感じがなんとも楽しかったです…ありがとうございました😊