夏休み感想文――ドイツの黒い森から 42(びすこ)
- クレマチス

- 2022年8月13日
- 読了時間: 11分
欧州全体にわたって今年の夏休みはコロナの影響は少なく、しかし間接的には人手不足で航空機を飛ばせないとか、空港で積み残された何千人分もの荷物がそのまま乗客の帰国を待っているなどの問題が頻発したが、それでも特に若い人や家族連れは果敢に地中海やスペイン、さらには東南アジアなどに飛んでいった。
欧州人の夏季休暇は最低でも 3 週間、有給休暇を貯めて一か月休む人も少なくない。そんな中でわれわれ老夫婦は例年のごとく「安・近・短」で済ませている。といっても、日本人の感覚から言えばさして安くはないし、近場とはいえスイス・オーストリアとなれば車で 3時間はかかるし、2,3 泊で帰宅などヨーロッパでは出張でもない限り考えられないから、私たちも土曜日から木曜日まで 5 泊 6 日の旅行となった。当初は 10 日ほど滞在するつもりだったが、夫がさっさと予約をしなかったためスイスの常宿が金曜日以降は満員ということで渋々帰ってきたのだった。
渋々と言ったが、それは夫だけの話で、私は早く帰れるのがむしろ嬉しかった。信じてもらえないかもしれないけれど、私にとってはバカンスというのは一種の義務で、自身はひどい出不精なのに、普段仕事に追われている連れ合いに休暇・休養が必要なことは認めているので、本心を言うと「さっさと行って(休暇という)用を済ませて、さっさと帰って来たい」のである。
そんなわけで昨日夕方に帰って、メールをチェックしたら日本も祝祭日とかで今週は誰からの音信もなかった。明日からは盆休みだそうで、なるほど今日金曜日に有給休暇を取れば日本人も6連休を楽しめるわけである。国際ニュースはスイスやオーストリアでも見聞きできるから、同世代のオリヴィア・ニュートン・ジョンが 73 歳で亡くなったとか(この人の母方の祖先に有名なドイツ=ユダヤ系の物理学者がいるそうな)、三宅一生が肝臓がんで逝ったということはテレビ・新聞で知っていた。
オリヴィア・ニュートン・ジョンのことで話が逸れるが、英国生まれの彼女がオーストラリアに移住したのは父親がそこの大学でドイツ語を教えることになったから、と書かれていた。それで思い出したが、私が 20 年余りも昔にフライブルクのドイツ語学校(ゲーテ学院)に通い始めたとき、無論私は初級者のAクラスだったが上のCクラスにオ―ストラリアから来たという中年女性が何人かいた。事務所の人の話を聞くと、毎年一定数のオーストラリア人が上級クラスに参加するという。彼女らはいずれも、高校のドイツ語教師なのだった。
日常彼・彼女らがドイツ人と接することはあまりないため、何年かに一度はブラッシュアップを兼ねてドイツの語学学校で学び直すのだと言っていた。ゲーテ学院はドイツ全土にあるので、毎年かなりの数のオーストラリア人のドイツ語教師がやって来るわけである。
そんなわけで、オーストラリアにおけるドイツ語熱については以前から知っていたが、まさかあの美少女オリヴィアの父親がドイツ語の教師だったとは。
さて、ここで本題に戻って。今日のテーマはかなり重く私の感想文も長くなりそうで、雑談をしている暇などないのに、ついつい逸れてしまった。
帰宅してメールの次にチェックしたのはこのKBCのフォーラムである。いちまるさんの投稿、特にイモズルシキホンノキには大いに刺激を受けており、スイスの宿でも一日の大半をグーグー寝ている亭主を尻目に、私は最近そこのフォーラムで辻邦生の作品が話題になったことからこの作家の「西行花伝」を持参して毎日読んだ。これがまたえらく長くて美文調で、そこへ平安・鎌倉時代の貴人・武人がまさに浜の真砂の如く出てくるので、数ページ読むと私もまた休憩が必要という体たらくだった。
あ、いけない、また話が逸れる。さて、今回いちまるさんによって取り上げられた作品は西行とも辻邦生とも関係なく、「えた非人:柳瀬勁介:塩見鮮一郎訳」である。
自慢じゃないけれど、この「穢多(えた)」というのは、実は幼い子供の頃から私の心を捉えていたテーマである。なぜなら、実際にこう呼ばれる人達が私の周りにいたからで、そして彼らの当時( 1950 年代)の悲惨な「生」はずっと心の片隅に張り付いており、今でも拭い去ることができない。
私の住む村には彼らの集落はなかったが 3,4キロ離れた海辺の地区に彼らは住んでいて、同じ被差別民の中にも多少の貧富の差はあったらしく、私が通りがかりに目にしたのはその中でもましなスラムであった。その奥には目を覆うような暮らしぶりの人々がいたらしい。
市内のいろんな地区で初夏と秋には神祭と呼ばれるお祭りがあって、来客をもてなす行事の翌日には、この「穢多」の女たちが大きなズダ袋を持ってやって来る。宴会の残り物を乞い、残飯を袋に無造作に入れると次の家に回っていく。私はその様が恐ろしくて彼女たちが近づいて来ると逃げていたが、そのやせ細った身体、特に骨と皮だけの四肢を見ると胸が潰れそうになった。
これほどの悲惨な光景はやがて次第に姿を消したが、その背景にはもちろん戦後に自治体が着手した福祉制度があって、これらの人々もいくらかは生活保護費をもらえるようになっていた。だから物乞いをする様子は次第に珍しくなっていたけれど、私は夏休みになるといつも彼女たちと再会するのであった。場所は眼科の病院である。
村の学校にはプールなどなく泳ぐのは近くの川で、そこの水はどうも清潔とは言い難かったらしく、また当時は炎症が起きやすい体質だった私はよく物もらいができたり時には結膜炎になったりで、必ずと言っていいほど眼科医の世話になった。(現在でも帰国の都度に白内障・緑内障の検査を受けるが、今の可憐な女医さんは当時の男の先生のお孫さんである。)
病院の待合の一隅に必ずと言っていいほど、被差別部落の女性が固まって座っており、彼女らの中には目を開けられない人たちもいた。病名はトラコーマだった。今では先進国においては稀になった眼病であるが、日本でも 60 年代まではかなり見られたように記憶している。失明率も高かった。そのトラコーマについて調べていて「垂直感染」という言葉に出くわし、私はひどいショックを受けた。ウィキによれば「病原体が親から直接その子孫に伝播される感染様式。狭義には経胎盤感染や経卵感染(in egg、on egg)などの出生以前の伝播のみを指すが、産道感染や母乳などによる分娩後短期間内の伝播を含む場合もある」とある。運命により数代にわたって惨劇が繰り返される病で、まさにこのことが「穢多」と呼ばれた人たちの悲劇を象徴していたといえる。
私の郷里ではこれらの人々は「新(しん)」と呼ばれていた。いちまるさんが紹介された本の引用によれば、
<明治維新の善政によってひとたびは「穢多」という醜名は廃止され、平民と同列になり、法律においても、他の人たちと同等の権利を持つことになった。しかしながら、長年にわたる因習は俄かに改まることがない。今度は「新平民」という新しい名称で呼ばれ、しばしば汚濁の深淵に投げ込まれて落魄の身になる。>
どうして彼らをシンと呼ぶのかと尋ねたのは私が 7,8 歳の頃で、従ってその時から「新平民」という言葉は知っていた。母が「喜々として」教えてくれたからである。
母の実家は「士族」の家柄であった。士族といっても下級武士のその末端で、暮らしの貧しさの方はまだしも、気概や志などというものはとうの昔に失われ、ただその身分だけが誇りという、はっきり言って実に情けない家系だった。そして母には「その家柄から、金持ちだけが取り柄の農民の家に嫁いできてやった」という奢りが終生見られた。
「シン」という言葉の由来を訊く私に母は、それは「新平民」のことだが、自分の家は「旧士族」なのだと胸を張った。小学校から女学校まで自分より成績のいい級友はたくさんいた中で、「旧士族」と通知簿に記されているのは自分だけだったというのである。彼女とその兄弟姉妹の通知簿に「旧・云々」とあったというなら、かつて穢多と呼ばれてきた子供たちの場合には「新平民」と書かれていたわけだ。そして、そのことへの抗議は、戦前社会には見られなかった。
この母親の返事だけで、彼女とその実家への嫌悪を私の心に引き起こすには十分であったが、それからしばらくして、わが家にやって来た魚売りから母が何か買い、彼が去ったあとで「あの人はシンだからね。ほんのこの間までああいう人間は、私が住んでいたお侍の地域に来ると、その入り口で草履を脱いで裸足にならないと入れてもらえなかったのよ」とまたしても得々と語ったことがあった。
その時に自分の親とその係累に対し湧きあがった激しい怒りと侮蔑を私は今も忘れることができない。残念ながら幼過ぎて、その感情の因ってきたる所を論理的に説明する能力はなく、そのことがまた自分を一層惨めな気持ちにした。
これまで私はこのブログその他で母親や一部の親族のことを滅茶苦茶に貶していて、自分の親をそこまで悪くいうなんてと呆れた方々も多いだろうが、私は 7,8 歳の子供の頃から既に母親には一片の敬意も抱くことができず、ただ本能的な軽蔑しか感じなかった。そしてそういう女を妻として容認している父が不思議だった。一緒にいて自分が気楽でさえあれば、それでいいのか。子供に与える影響になぜあれほど無関心でいられたのだろう。
一方で母親に溺愛された弟の方は、無知な母親を馬鹿にしつつもその言動は瓜二つだったから、おそらく遺伝子の作用だろうが(まさに垂直感染)、誠に幸いなことにその遺伝子は胎内の私を素通りしてくれたらしい。
母親の態度は極端であったが、社会全体として差別を糾弾する風潮は未だ熟していなかった。祖母はよく私に「県外の人に嫁ぐんじゃないよ、氏素性が知れたものじゃないから」と言い、母も「何度か引っ越しすると、元の戸籍は分からなくなると言いますからね」などと同調していた。(その挙句、国外の人に嫁がせたわけだ。)
祖母が最も恐れていたことが起きたのは、私が中学生の頃である。私の従姉、つまり祖母の孫娘の一人が、被差別部落の男性を好きになり駆け落ちしてしまった。祖母にとって幸いなことに彼女は「内孫」ではなく、伯母には 4 人の子供がいたので、そのうちの一人の不始末は「勘当」という形で処理されて以後一切の接触を絶った。気の毒なことに結婚生活は長続きせずやがて別れることになって、しかし帰ることは許されず、現在は生死も分からない。今なら私も、父母や親戚を敵にまわしてでも従姉妹として付き合う気持ちはあるのだが。
この「シン」の問題はその後も私について回った。高校時代のことだが、よく隣に座るので親しくなった一人があるとき私に「ねえ、知っている? Yさんって部落の出身なんよ」と重要な秘密を教えてあげるという口調で囁いた。この二人は同じ地域から列車で通っていて、Yさんはしっかりした良い女生徒だったが、仮に彼女が手に負えない不良少女だったとしてもそんなことをなぜ私に打ち明ける必要があるのだろう。以後私はこの噂好き娘を避けるようになり、そのまま卒業まで言葉を交わすことは稀だった。
高校時代の同級生といえば、その中の一人が後日高知県内の、しかも偶然にも私たちの母校に近い地域で、公務員として部落解放に関係した仕事に何年か従事していた。そこには部落解放同盟高知市連絡協議会という組織があるので、それとの連携で役所として被差別者の生活向上が図られていたのだろう。当時彼女自身いくつか家庭問題を抱えながらずいぶん遅くまで働いている様子だったので、あるとき一体どんな仕事をしているのかと尋ねると、部落の人達に読み書き算盤を教えているとのことで、それも中高年者が対象だという。もう 30年近い昔の話だが、それでも当時まだ字を書けない人がいるということが驚きであった。
50 歳・60 歳まで読み書きができないままに、間もなく老いの坂を登ろうとしている男女のこれまでを想像することは容易ではなかった。還暦を迎える時期になっても、生まれたときに巻き込まれた負の連鎖から抜けだせずにいるわけだ。友人もだいぶ前に退職して、その後の進展は聞いていないが、団塊の世代以降には非識字率がゼロになっていることを望むばかりである。
以上、「えた非人」に関連して自分の体験を記してきたが、この問題についてはずっと関心があったので、あるとき欧州でもきっと「差別」は存在したはずだと調べて、二つの民族のことを知った。一つはイェニッシェ(Jenische)と呼ばれるグループで、彼らはかつてライン川沿いに多く見られた。フランスにもいたが大半はラインの右側で、一部はバイエルンやオーストリアにまで広がっていた(写真 1 )。この人達についてはウィキにも紹介されているので、興味のあるに方はそちらを読んでいただきたい。

もう一つの集団はカゴ(Cagots)と呼ばれる。スペインからピレネーを越えてフランスの南西に散在していて、暮らしぶりはイェニッシェよりも悲惨で差別も苛酷だったらしい(写真 2 )。近親結婚による弊害も大きかった。欧州の非可触民という説明もある。このカゴの説明もウィキで読める。

非可触民で思い出したが、かつての「穢多」はそれと同等の存在だった。「えた非人」の中で「アフリカやアメリカの黒人に似た境遇」と書かれているのは当たっていないと思う。アメリカでは黒人を召し使いや料理人として雇うことに抵抗がなかったようだが、日本では非人を家の中に、ましてや厨房に、入れることなどありえなかった。「畜生」に等しい身分の彼らに調理させるなど問題外だったのである。黒人は白人中心の社会の周辺で奴隷・労働者として生き延びたけれど、「穢多」は周辺にすら姿を見せることを許されなかった。
そのことを仏教の渡来・伝播と関連付けているのは間違いではないにせよ、日本においては四足の動物が「獣」と呼ばれ、そして仏教に輪廻という概念があることとも無関係ではないのではないか。仏語でいう六道の中に「畜生道」があって、それによると前世での悪業のため死後には畜生として生まれるというが、穢多はその畜生に等しい存在だったのである。優しく穏やかで和を重んじるはずの仏教に、いつこのような恐ろしい教えが入り込んだのであろう。人類の誕生以来、この世で狂気と無縁の宗教など一つもなかったことを改めて考えさせられる。

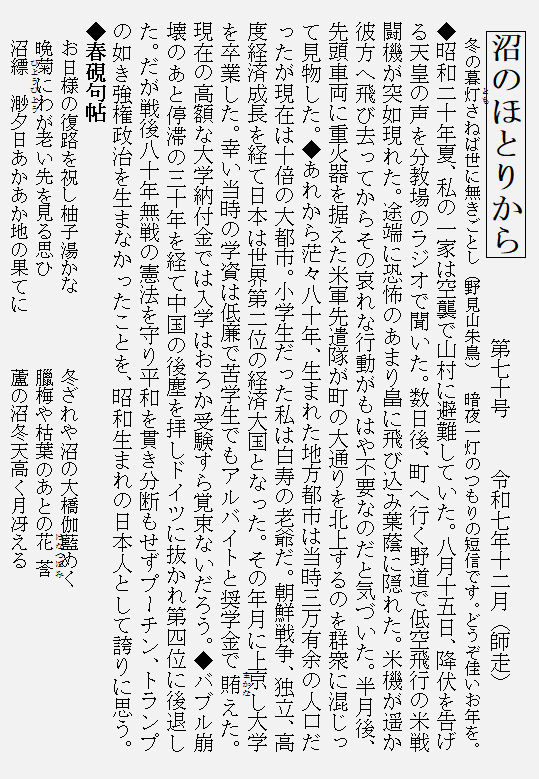


人は生きていくために意に沿わないこともしなければならない。妻子を養うために厭な上司に追従せざるを得ないこともあるし、女一人で生きるために男に媚びて機嫌を取り結ぶことだってある、老いてのちの身の安泰を考え守銭奴になって金貸しに精を出す男もいる。
でも、ただただ自分が優越感に浸るために周りを蹴落とし侮辱し、打ちひしがれる人の姿に満足感を味わうというのは、生きるためには全く不要なことで、弁解できる部分は微塵もありません。
その心理はある程度は人間に固有のものかもしれません。いわば原罪のようなもの。しかしほんの少し情理を働かせば、それが「悪」に近いこと、ときには悪そのものであることは誰にも明らかで、そういう心理を恥じずにはいられないはずです。第一に、もし自分自身が貶められ虐められ、「生まれ」のゆえに苦海に沈められるとしたら・・・そう想像するだけで、他の人間を差別する言動は思いとどまるのではないでしょうか。
それができない人間が私には分からないのです。そしてそういう不可解な人々が身近に、ほとんど常に、そして今でも、大勢いることは、自分の人生にどういう意味を持つのだろうとよく考えます。呪われているのは差別される側ではなく、21世紀の今も快感を味わうために差別を止められない人達です。しかも、それを天の配剤だとか神の御心などと正当化するに至っては、彼らこそが別の人種だと思わざるを得ません。
昨日たまたま知りたいことがあって源実朝の和歌を調べていたら、私の積年の疑問に呼応するような歌に出くわしました。
・神といひ 仏といふも世の中の 人の心のほかのものかは
今メールにブログアップの知らせが来て、スマホを開いて、えたに関するびすこさんのブログを読みだした…お手洗いに行くのも忘れ貴重な証言に「裏」が補強された思いです、用を済ませて、改めてゆっくりと拝見させていただきます…ありがとうございました😭