俳句で締める1年――ドイツの黒い森から 59(びすこ)
- クレマチス

- 2023年12月25日
- 読了時間: 10分
師走に入ってからも当方の興味を刺激する事件・事象が続出した。日本でどれだけニュースバリューがあったかは知らないが、2022 年度の国際学力比較 PISA の発表が 12 月 5 日にあったときは、大げさに言うとドイツ中が上へ下への大騒ぎとなり、早朝のインターネットのニュースでこれを知った私はさっそく夫や社員の一部に知らせてあった。
その日私は、わが家の管理人の M さんとスイスまでクリスマス菓子セット約 100 人分を受け取りに行く役目を言いつかって出かけたが(郵送料が高い上に送ると税関が煩いので)、車内で聴く正時のニュースは全部この「ドイツの災厄」の話題で盛り上がり、いや盛り下がり、私が思わず「しつこいわね、何を今さら」と文句を言ったほどだった。
ご存じのように、シンガポールの他にマカオや香港を含めた順位ではドイツは 24 位となった。だが、その前にこのランキングのリストはちょっとおかしいと思う。台湾やシンガポールはかなり特殊な国で、しかし小国というならスイスやベルギーなども同じだからリストに含まれるのはまあ許せるとして、香港・マカオを対象にするのであれば、日本も東京を別途に分類してもらってもいいし、どこかは知らないが、日本で最も学力の高い県を日本代表にしたっていいわけである。
もっとも新聞やテレビによっては、「 OECD 国の比較で言えば日本が一位」と真面目に(?)報道していたメディアもあった。シンガポールなんて、人口が限られるだけでなく、とにかくファイナンスつまり金融だけの国なので、そこと比較するならチューリッヒあたりかリヒテンシュタイン、ルクセンブルクなどが妥当であろう。その金融センター・シンガポールと、農林漁業あり製造業あり、もちろんサービス業も、という日本とを比べてシンガポールに軍配を上げるのは無茶というものである。
この国際比較に矛盾や偏りがあることは 2003 年の発表以来気がついており、そうはいっても自分は教育業界の人間ではないので目くじら立てる気にならなかったのだが、未だに誰もそれを指摘しないことが腹立たしい。
さらに、数学・理科はいいとして、読解力というのはその国の言語の構造に左右され、これは文化的な側面でもあって必ずしも学力とは言えないのでは、と思っていた。日本は前回それがあまり好ましくない成績だったのに、どんなトリックを使ったのかは知らねども、今回の順位は大幅に上がっていた。
トリックなんていうと睨まれそうだけれど、この読解力の比較に懐疑とは言わぬまでも敢えて注釈を加えた専門家はいて、このたび英語圏つまりオーストラリア、カナダ、英国などの成績がよかったことについて、英語での設問が分かりやすかったためではないか、とあったのには、「ほら、やっぱり」というところだった。
おそらく、或る同じような内容・趣旨の文章をそれぞれの言語で示し、それに関する生徒の理解度を測ったと思われるが、内容は同じでも言語表現はそれぞれの国に任されているので、例えばフランス語の文章が構造上ちょっと分かりにくかったり、中国語が平易だったり、という違いは不可避であろう。そのこと自体は仕方ないが、そういう言語の差異を無視して順位を云々するのは公平さを欠くと思う。つまり、日本の生徒の読解力がフィンランドや韓国より低いとか言われても、少々の違いは誤差のうちともいえるので、そうキリキリすることもないだろうに。
しかし、それではドイツ語も文章が難しかったのでドイツの生徒の成績が悪かったかというと、これはちょっと当たらない言い訳である。というのは同じドイツ語のテキストを読まされた生徒の間でも、オーストリアやスイスの学童の成績はドイツに比してかなり良かったからで、ドイツの惨めな結果に関しては残念ながら弁解のしようがない。
どの国に関しても弁解できないことが明白なのは数学で、こればかりは言語は全くと言っていいほど関係がなく、要するに「出来が悪い」ことの言い訳が立たないのである。
上に「しつこいわね、何を今さら」という私の苛立ちをお聞かせしたが、これは私がとうの昔、特にここ 3, 4 年ずっと予想していたことだからだ。コロナによる通学・授業の制限は先進国全般に似たようなものだったろうが、ドイツ人を見ていて、生徒も教師も怠ける口実を公にもらったといわんばかりの反応だったのに呆れた。さらにフライデー・フォー・フューチャーとかいう環境保護の運動がどこかの国の娘の扇動でドイツ中に広がり、金曜日には都市の中学では特に、街に出かけて道路に寝そべったり張り付いたりというジェスチャーが大流行。ドイツの学校はそれでなくとも春夏秋冬やたら休暇が多いのに、そこへ毎金曜日は授業にならない、というのでは、真面目に授業を受ける東アジアの国に叶わないのは当然である。一言でいえば、今のドイツ人(の多数)の問題は「思い上がり(Arroganz)+ 油断」であって、先進国に共通の病気ともいえる。日本も心せねば。
もちろん移民が増えたこともマイナス要因で、これは政治的な問題ともされ移民推進派の左派が責められた。その指摘は的外れではなく、ベルリンなどではドイツ語を解する生徒が半分に満たないというような学校もあるという。しかし移民のせいにするとそれに対して予想通りの反論があって、英国や特にカナダは移民の多さにも関わらす成績は(比較的)よかったではないか、という声が国の内外から聞かれた。いや、それをいうなら、移民を送り出した国のレベルが問題なのであって、英国などはインド系、オーストラリアやカナダならそれに加えて中国系が多いが、これらの移民は「学ぶ」ことを知っている。
ところが移民受け入れ新興国とも言えるドイツが「いい国ぶって」引き受けたのは、アフガニスタンやシリアやイラクからの自称難民の子女が多く、その大半は文字が読めず、そもそも学校というものに通ったことがない子どもが珍しくないので、他国の学校制度に容易に順応できるはずがない。親の方も教育の意義を認識していないばかりか、西洋の悪しき慣習や「退廃」に染まることを恐れて、子供の同化防止に懸命である。異教徒であるドイツ人の子供との交友すら許さない。
まあ、そんなわけで、この国に関しては惨憺たる結果に終わった PISA であったが、夫やその社員に私が言ったのは、「安心して下さい。ドイツは 24 位ですが、お隣のフランスはその二つ下の 26 位ですから」という意地の悪い慰めであった。
それにしても、子供を持つ親は大変だなあ、と思っていたのだが、学校の成績と並んでこのところ教育界が頭を悩ませているのは、大学に進む人が増え、それもある学部・分野に集中するので人気のある学部を卒業した人は競争にさらされて就職しにくく、一方で実業学校への入学者が減って手を使う職人の仕事に就く人がいなくなった、という現象である。
先日の新聞に出ていたその社会現象についての解説によると、高校から大学へ、という進路は嘗ては親が望んだもので、子は何も言われずとも親の意を汲んで大学に入ったものだが、現在では、若者が気にして影響を受けるのは親ではない。今時の青少年は親の見栄などは無視する一方で、周りの人々、つまり友達、同級生、隣人、文字通り同じ町に住む人たちの目に映る自分の姿を判断の基準にするという。ソーシャルネットワークで「繋がって」いる人たちから承認を得たい、羨ましがられたい、という欲求が年々強まり、周囲の反応を考えるとイメージの悪い学部なんか行きたくないし、ましてダサい昔ながらの製造業に就職するのもマッピラ、という若者が普通になった。
この際、喜寿間近の年齢に免じて、また自身の人生への反省をこめて、はっきり言わせていただく。自分の一生にかかわることを決めるのに、周りの目や反応を判断の基準とするのは、自尊心の完全なる欠如である。
このように、今は親の教育よりソーシャルネットワークでの繋がりに子供が大きな影響を受ける時代となり、それもまた子育てを一層むずかしくしている。子供たち自身そのことを感じているため、いずれ自分も家庭をもって子供を育てようなどという気をなくしているのかもしれない。そうなると少子化問題は深刻さを増す一方である。
ところで、今回のブログ、「俳句で締める云々」とあるが、一向に俳句が出てくる気配がないではないか、と思われた方。申し訳ありません。ここまでは長い「序」でありまして、子供の話になったのでようやく繋がるのだが、今年は知り合いに子供を亡くした人がいて、もらい泣きしてしまうこともあったと同時に、成人した息子さんをもう 20 年近く前に事故で亡くした夫婦の、奥さんの方が、その悲しみを乗り越えられないままに認知症になってしまったと聞き、ただもう胸蓋がる思いだった。
死に別れはそれが配偶者であっても、恋人や親しい友人でも、その悲しみの深さに順位はつけられないものの、女性の場合にはやはり子供を失った痛手からは立ち直りにくいのだと今さらのように実感させられた。
これもまた「今さら」というのは、幼い頃に出会った高齢の婦人の中に戦争で息子を亡くした人が何人かいたためで、子供のこととて当時はその胸のうちなど慮る由もなく、ただある人は悲運にもかかわらずいつも優しくて、またある人は暗く刺々しかったという記憶が残っている。そして、私本人は忘れていたはずのその昔のことが、近年は自分の年齢のせいだろうか、ふいに意識下から浮かびあがって来ることが増えた。
そんな中で、最近何人かの俳人の作品を読んでいたときに、ああ、と思わず嘆息を漏らしてしまう句に遭遇した。俳人の名は竹下しずの女、漢文の素養があり理知的で男性的とも言われる句風で知られるそうだが、子育ての真っ最中に俳句の友でもあった夫君を失い、女手一つで 5 人の子を育てあげる。その怱忙の日々の中で生まれた句。
・ただならぬ世に待たれ居て卒業す
これは長男が高等学校を卒業したときの句で、その後彼は九州大学に進んだものの、やがて招集されて若き命を戦場に散らす。母親の危惧した通り、まことにただならぬ世に生まれ育ち、学んで、そして戦いに赴く、という短い生涯だった。兵士として差し出すために子を育てた母親の想いはいかばかりだったか。竹下しづの女は決して例外ではない、どころか、当時の日本でそのようにして子を失った親は 100 万人単位でいたはずである。
息子をお国に捧げた、だって?? 冗談じゃない、と、これまた今さらのように、戦争へと突進した昭和初期の日本に憤りが募る。なんという世の中だったのだろう。戦争を知らず子も持たなかった私ですらこれだけの怒りを覚えるのであれば、その当事者である母たちの悲しみ・恨みの深さは計り知れない。
ついでにこの竹下しづの女の数ある名句の中で、私が一番好きなのは
・緑陰や矢を獲ては鳴る白き的
という句。緑と白の見事なコントラストは、「千里鶯啼緑映紅」で知られる七言絶句を思わせる。
こんな傑作の後に我が拙い句を披露するなど恥知らずの極みではあるが、ここのところはひとまずそんな比較なんか忘れていただき、老女の素朴なつぶやきとしてお聞き下さるようお願いする。以下は 2023 年の冬の感想である。

・小春日や物乞いの鉢未だ空
・聖堂の御使いの頬に片時雨
・短日や寝衣のほつれに千鳥掛け 1)
・冬立ちて手鏡に見る母の面
・父に似し癖毛のままに木の葉髪
・底冷えの身廊に座しバッハ聴く 2)
・不機嫌な雪掻き娘を労いぬ
・蜜蜂の巣箱静もり聖夜更く
・一つ星厩に冬仔の鳴き止まず 3)
・汝が夢と取り換えてみん浮寝鳥
1) 千鳥掛けをご存じない殿方(最近は女性も)のために、写真を添付する。ちょっと所帯臭いですか。嘗てよく言われた「台所俳句」風の家事俳句。

2) 身廊というのは、これも上の写真に見る通り、教会の真ん中の、両側を柱で挟まれた部分を指す。柱の両外側は側廊といい、真正面が円陣、その円陣と身廊/側廊との間に横長の袖廊がある。つまり平面図では十字形。この写真はゴシック建築だが、それよりも古いロマネスク様式でもバジリカ建築でも、小さな礼拝所は別として教会内の構造は基本的に変わらない。
3)冬仔とは冬に生まれた動物の子(下の写真参照)。我が家の裏手の農家でもこの時期によく羊や山羊が生まれたものだった。その家業を継ぐ人はなく、建物も古いので次世代が改築してペンションにし、動物たちは姿を消した。

以上。失礼いたしました。
それでは皆さま、どうぞ良いお年を。

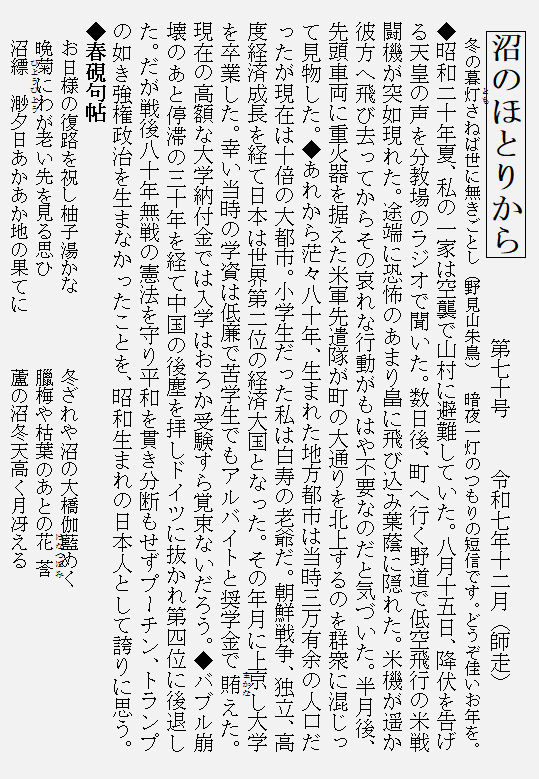


いつもながら、ご丁寧なコメントをありがとうございます。
急に寒くなった朝鏡をのぞいて、普段思い出しては未だに腹を立てている自分の母の顔をそこに見てぎょっとすることがあります。
父の癖毛はかなりなもので、それを受け継いだ私の髪も、子供の頃は湿気が高いと余計にくるくる巻くので、縮れが顕著になると「あ、この子の髪!これから雨になる!」と母や祖母は言っていたんですって。
こっそり(誰に?)父の縮れ毛をお目にかけますね。これは二十歳の頃みたいです。
小春日や物乞いの鉢未だ空 鉢は空だけど小春日和やからまぁいいや 聖堂の御使いの頬に片時雨 子供にとってはもっと遊んでいたいのに用を頼まれて、中ぶらりんな気持ちのような雨?かな、だったら子供にとってお使いも遊びのうち、、 短日や寝衣のほつれに千鳥掛け ほつれにタスキをかけるようなものですね…もうちょっと頑張る気にさせる微笑ましさ 冬立ちて手鏡に見る母の面 母の顔に思いをいたす冬にご自分を投影なさる、、どんな気持ちなんですか 父に似し癖毛のままに木の葉髪 癖毛、かぁ、、そこまで似てしまう、それを発見できるのも血筋がたどりついた年の功なのですね 底冷えの身廊に座しバッハ聴く 荘厳の中にも朗々とバッハの曲が身廊に響きわたれば寒さもまた快い 不機嫌な雪掻き娘を労いぬ あはは、不機嫌な娘はどうねぎらっても不機嫌、そういう娘に限って嫌な仕事が回ってくる、持て余しているどなたか 蜜蜂の巣箱静もり聖夜更く みつばちも丸まって暖をとっている巣箱の中の聖しこの夜 一つ星厩に冬仔の鳴き止まず 厩は消えても鳴き声は長く記憶に留まり泣き止まぬ 汝が夢と取り換えて見ん浮寝鳥 見たいのは浮かぶ水鳥に託す人の夢 以上どの句もびすこさんらしくもあり、そうなの?と思わせる微妙さが面白いですね、まあ、独りよがりな批評、失礼があったらごめんなさい