ユダヤ考――ドイツの黒い森から 58(びすこ)
- クレマチス

- 2023年11月11日
- 読了時間: 19分
先月 7 日、ハマスのテロリストが奇襲でイスラエルに侵入し外国人を含む数百人を人質にしたというニュースが世界に流れて以来、いずれイスラエルとユダヤ人の問題を取り上げたいと思っていた。このテーマは現在の戦闘が発生するずっと前から頭を占めていたのだが、どこからどう見ても広すぎ重すぎて焦点を定めるのも難しく、時期を見て、目下ドイツその他の欧州諸国がそれぞれ国内で抱えているイスラム教徒への対処の課題に絡めて話題にするつもりだった。
現段階でもイスラエル対ハマスの交戦のゆくえは見通しがつかず、世界中がイスラエル擁護派とパレスチナ同情/ハマス支援派に分裂している感がある中で、今回あえてユダヤ(人/教/国)についてブログを書くことにしたのは、先月末のライントークでクレマチスさんがパレスチナの最新の状況に関するオンライン講演会をリンクで示してくださって、それが放送大学名誉教授の高橋和夫氏による解説だったためである。
何を隠そう、私はこの高橋教授の大ファンで、それも昨日今日の俄か贔屓ではない。あれは母が入院することになって帰国した際だったので 20 年近く前になるが、看病の合間に自宅に戻りテレビで放送大学の番組を見ていたときこの人の講座に出会った。テーマが中東情勢に関するものだったからたちまち惹きつけられたのだったが、それも通り一片の学者の論説ではなく、教授自身の豊かな見聞に裏打ちされた講義だったのですっかりファンになってしまったのだった。(クレマチスさんが紹介してくださった二番目のリンクでわかるように、高橋先生はユーモアもあって話術に長け、45 分の授業はあっという間である。)
以来帰国すると、実にくだらない他のテレビ番組を罵りながらこの放送大学にチャンネルを合わせるようになった。
お目当てはもちろん中東問題に関する講義だが、他にも私が見逃すまいとしている講座がある。見逃すまいったって、1 年の大部分は日本を留守にしているからほとんど見る機会はないのだが、放送大学では結構再放送があり、帰国中にかなりの講義を聴ける。
それらの一つは島内裕子教授の古典、それも中世の文学に的を絞った講義で、徒然物語と方丈記が中心になっている。ご夫君も同じ古典文学者なので、ときには夫妻で古址を訪ねたりするのも興深い。
もう一つは青山大学教授で放送大学でも教えておられる大野昭彦氏の開発経済の講義である。これには「アジアの農村から」という副題が付いていて、そのタイトル通り東南アジアやインド等の農業問題が論じられる。四国の片田舎に生まれ育った私は、どこに住んでも何才になっても農業という分野を視野の外に置くことができない。農業開発や農業経済にはずぶの素人で何の貢献もできないながら、農村の状況というのはわがこととして気にかかる。大野先生は実際にアジアの農村で地道なフィールドワークを続けておられ、その真摯な姿勢に感服している。
また森津太子教授の社会心理学の授業に教えられるところも多い・・・などと話していると、さなきだに広すぎるテーマに一向に手がつけられなくなるから、国際政治の中東問題に話を戻して。
そもそも今回のブログのタイトル、変なの、と思われた方も多いだろう。説明させていただくと、ユダヤへの関心はわが人生のわりに早い時期からあり、長じてそれが別の事情で深まり、さらに今はドイツという、ある意味ユダヤ問題でがんじがらめになっている国に住んでいることから、「ユダヤ考」は私の人生の一部になっているのであります。
ユダヤという言葉を初めて目にしたのは小学生の頃、少年少女文学全集に収められたチャールズ・ラムの「シェイクスピア物語」の中だった。シェイクスピアの作品は戯曲で多くは韻文なので英国人の大人にさえも難解だから、それらのあらすじを散文で子供にもわかりやすく記したのがこの本である。そこにはハムレットやリア王などの悲劇と並んで「ベニスの商人」も含まれており、悪役としてシャーロックという強欲な冷血ユダヤ人金貸しが登場する。
それで、ユダヤ人、高利貸し、人でなし、というイメージが子供心に定着してしまったわけだ。
さて、私が 16 歳のとき父親がキリスト教徒になった。高等学校時代に既にこの宗教に傾倒していたそうだが、中年になって何かの会合で改革派教会の牧師と知り合い、その手引きを得て何年か後に洗礼を受けた。その前にしっかり教会に通って準備は整っていたけれど、祖父母が「耶蘇」嫌いで、それでなくとも家の中は祖父の女性問題や嫁姑の不仲で陰鬱だったため、父としてはそれ以上にいざこざの種を撒くのを控えたのだろう。それで祖父の死去を待っての入信となったことについて、最近もう一つ気づいたのは、祖父の存命中に「耶蘇信者」になると長男である父が仏式の葬式をあげることができない、という事情を踏まえての延期だったらしい。明治生まれの男とあって、何教の信者になろうとも「家」が自分のアイデンティティの重要な一部であることに変わりはなかった。
父に続いて家族の全員がそれぞれのやり方で信徒となり、私の場合はちょうど 20 歳の春であった。その前に、腎臓を悪くしてほぼ 1 年間の入院を余儀なくされた時期、私は旧約・新約聖書を一通り読んでいた。
大学に入り、それがミッション系の学校であったことと、また英文学にはキリスト教の知識が不可欠であることから、「聖書と文学」、キリスト教史、西洋史などは必須科目で、もともと私の場合は英文学より史学を専攻したかったのを周りから「そんな潰しの効かない分野はお止し」と言われて諦めた経緯があるので、それらの科目はいずれも比較的真面目に勉強した。
一方、熱心な信者となった父の方は、専門が全く違う上に戦前の学校で習った世界史など限られたものだったせいか、最初は、ユダヤ人にとっては旧約の世界が全てだということも、そこから脱して新約の世界に入って行ったのがキリスト教だということも知らなかったらしい。時々、トーラー(モーセの五書)って何のこと、とか、タルムードというのは何、などと娘の私に質問してきたほどである。
少し長居をしてから学校を出た私は、専門とした外国語を活用できる仕事を探し、通産省の外郭組織である途上国援助団体に就職した。そこで初めて外国人だらけの中で働くことになったのだが、彼らは全員途上国からなので英語を母国語とする人はおらず(一部インド人は堪能だったが)、といってどの国の言語にも対応するのは無理だから、スペイン語、マレー/インドネシア語などは別として、アフリカ、中東、東南アジア等の地域の人とは専ら実用英語でのコミュニケーションとなった。
その職場で、私は中東の人間、特にアラブ人・イラン人と親しくなることが多かった。キリスト教が身近だったため、同じくユダヤ教を母体として生まれたイスラム教にも大いに興味があったのである。(ただし、私は今に至るまで、宗教の中身やその起原・歴史には関心があるが、信仰の話は一切しない。)
折しもイスラエルとアラブの間での度重なる紛争を背景として起きた石油ショックが世界を揺さぶり、日本政府は産油国のご機嫌をとるために日本企業の中東進出を促したので、サウジアラビアやリビアなどからの研修生が急増した。彼らはエンジニアという触れこみではあったが富裕層の暢気な坊ちゃんが多く、可愛げはあるものの全く勤勉ではないので職員が手こずることもあった。
その人たちの面倒を見つつ、あるとき私は同年代のクエートからの研修生と親しくなった。エチオピア人のアベベに似た風貌で、非常に真面目で紳士で、だけどユーモアもある人だった。その E さんはクエートに工場を設けた H 社の研修生として来日したのだが、話しているうちに彼がパレスチナ生まれということが分かった。イスラエル建国でそこを追われヨルダンで子供時代をおくり、中東で最高レベルのカイロ大学の工学部で学んだというからよほど優秀だったのだろう。(中東のエリート大としては、もう一つベイルートのアメリカ大学があった。)
あとで聞いたのだが、パレスチナ人にはいわゆる IQ の高い人がよくいるそうで、アラファトなどもカイロ大学工学部卒である。科学技術の分野でのユダヤ人の優秀さについては今さら語るまでもないが、旧約聖書にペリシテ人として登場する人々の土地がパレスチナと呼ばれており、そこの住民はユダヤ人のいけ好かない親戚みたいなものだったから頭脳優秀であることに不思議はない。
あるとき E さんと歓談していてイスラエルのことが話題になると、彼が顔色一つ変えずに「ヒトラーの最大の失敗は、彼がユダヤ人全員を殺さなかったことです。全滅させておけば、私の家族は今でもパレスチナで暮らせたのに」と言ったのには絶句した。
この会話のことはずっと頭の中に残っていて、ほんの最近のことだが、ベルリンでハマスの急襲に沸き立つアラブ人難民のデモ隊が E 氏と似たようなことを叫んでいたのにまたしても唖然とした。またパレスチナ支援グループにはロシア系反イスラエル派もいて、大都市においては、ポグロム(ユダヤ人を対象とした集団迫害を意味するロシア語)を再び、という声が聞こえたりする。
ドイツには刑法で定められた「民衆扇動罪」という犯罪があって、ヒトラーを称賛したりナチの再来を願ったり、またどこかの国の王子さまがしたようにナチ SS の制服を着たりすると、刑務所行きになる。言うまでもなく第二次大戦中にドイツが犯した罪への反省からで、最近も右翼の若い政治家が逮捕されて話題になったが、奇妙なことに、自称難民としてドイツに侵入した反ユダヤ主義のイスラム教徒たちが街頭で何を言っても罰せられることはない。彼らの中には難民と認定されていない人たちも非常に多く、といって母国に返そうにもそちらで拒否され(彼らはしばしばパスポートを破棄しており、政府も「ウチの子じゃありません」と言う)、いわば存在しないはずの人々だから、逮捕してもどうにもならないのである。
E 氏がクエートに戻った翌年か翌々年のこと、私は 3 か月の休暇をとり職場で知り合ったレバノン人を頼ってシリア/レバノンに旅した。当時はレバノン内戦がピークは過ぎていたとはいえまだ終結していなくて、ベイルートの友人の家から銃撃戦が聞こえることもあったし、前述のアメリカ大学を卒業した彼もそこでは活動できないので、シリア生れの母親の親戚がいるダマスカスを仕事の拠点としていた。
そのため、シリアから土漠(砂漠にあらず)とベカー高原を越えて海辺のベイルートまで往復することが重なったが、国境の検問所の辺りにはいつもベレー帽をかぶって銃を手にした国連職員がたむろしていた。
ダマスカス市内でパレスチナ人の巨大なキャンプを目にしたことがある。傍を通り過ぎただけでそこでの悲惨な暮らしが見て取れた。だが友人を含めて一般のシリア人もレバノン人も総じてこれら難民たちには冷たく迷惑千万といった風で、石油ショックのときアラブ諸国が禁輸の根拠とした「パレスチナ人への共感」など、どこの話かと思った。

写真1 ヨルダンのパレスチナ難民キャンプ
この疑問は今も消えず、ヨルダンやシリア、レバノンなど経済的には不利な中東国が難民キャンプにパレスチナ人を押し込んでいる一方で(写真 1 )、豊かな湾岸諸国やサウジアラビアなどは自国内の治安維持を理由に難民を拒否し、キャンプの維持費は主に国際機関からの援助で賄われる。パレスチナ人が人口の 6 割を占めるというヨルダンなどはその支援金が目当てで、難民は政治家や王家のいわば収入源なのだ。
支援金ならパレスチナ人の住むガザにも西ヨルダンにも世界中から多額の寄付金が流れ込んでいるが、その大半は自治区の上層部の懐に入る。インテリのアラファトもそうやって私腹を肥やしパリに大邸宅を買って、彼の未亡人と子供はそこで王侯貴族並みの暮らしをしているという。問題の一端は、一般のパレスチナ人がそういう汚職を一掃してまともな国を作ろうとしないことにあり、凄まじいまでに腐り切った、頭の良い指導層は、イスラエルへの憎悪を煽ることで自分たちの悪行から民の目を逸らすことに成功している。
シリア・レバノンへの旅からちょうど 10 年が過ぎた春に、私は父を旅に誘った。行先は同じ東地中海地方、ただし今度の目的地はイスラエルである。父は団体役員だったので当時としては珍しく 71 歳まで働き、さらに何年か勤めることもできたのに「死ぬまでに勉強したいことがあるから」とある日スパっと辞めてしまった。
それから文字通り晴耕雨読の暮らしが始まり、彼が勉強したかったことの中に神学があって、恐ろしく難解なカルヴィンの注釈書などを毎日熱心に読んでいた。翌年早々に彼が喜寿を迎えるという年の春、元気ではあるが腰痛持ちなのでいずれ歩行が不自由になるのではと思い、イスラエル旅行を提案すると吃驚しながらも嬉しそうに同意してくれた。
私の方も元の職場を退職し、フリーになった当初は仕事も少なかったがやがて次第に注文が増えて経済的な余裕もできたので、この旅行を父への最後のプレゼントにしようと考えたのだった。
父はさっそく準備を始め、まあ、なんと生真面目に山のような資料に取り組んだことだろう。スカンジナビア航空でまずデンマークに飛び、そこからローマへ、そしてテルアビブというルートの機内で、ずっと本やら小冊子を読み続けていた。
昨今は特にそうらしいが、幾度かの紛争に片を付けたあとのイスラエルはすっかり観光地化されて、80 年代後半には聖地エルサレムはもちろんイエスの生誕地ナザレやその近くのガリラヤ湖畔、死海からさらにキブツまで、主に欧州からの観光客で賑わい、特にドイツ人が多かった。
エルサレムにはイエスが十字架を担いでゴルゴタの丘まで歩いたという「悲しみの道(ヴィア・ドロローサ)」を筆頭に数々の名所旧跡があるが、遠藤周作がその小説「死海のほとり」で主人公「私」の友人に言わせているように、どこも「義経の腰掛石」のようなもので、真偽のほどは分からない。というよりほぼ全てが「偽」であろう。
また、世界最古の町の一つとされるエリコのごとくに、敵に攻められて破壊され灰燼に帰した集落の上に新たに町を築き、それを何度も繰り返して小高い丘になってしまった場所がいくつかある。そういう丘をアラビア語でもヘブライ語でもテルと言い、テルアビブとは春の丘という意味だそうだ。イエスの時代の遺物はそれらの丘の数十メートル下に眠っている。
しかし一つ一つの古跡の信憑性など私たち親娘には重要ではなかった。ローマ帝国に続き十字軍やオスマン帝国によって集落が次々と破壊され地中に埋もれてしまっても、そこがユダヤ人にとっての「約束の地」であることには変わりなく、ナザレの町がイエスの故郷であったことは確かである。古代にはレバシリ(レバノン・シリア人)の先祖フェニキア人の貿易活動によって栄えた地中海の東端にあって、三つの宗教を育んだ地の空気を吸えるだけで満足だった。
父は最初物珍しい光景を写真に収めていたが、そのうち「俳句を作りたい」とカメラを私に渡し、以後撮影は私の担当となった。帰国後私が作ったアルバムに、父は写真の説明代わりに自作の句を書き込んでいった。
それから数十年の後、コロナ禍で日本に閉じ込められていた時期にアルバムを繰って一連の俳句を見ながら、私も当時を思い出して父の真似をしてみた。それがうららかな季節だったせいか、「棕櫚生ふるナザレに春の雨しずく」、「死の海を渡るのどけき春の月」、「クムラン*の永き眠りや千の春」など、春尽くしになってしまったが。(*死海文書と呼ばれる、紀元一世紀ごろの写本が壺に入れられて隠されていた洞穴。)
しかし当時の旅を思い出して最も鮮明な記憶が蘇ったのは、ネゲヴの風景であった。今回のハマスによる襲撃でイスラエル人が多数殺され数百人が人質に取られたのは、北ネゲヴのガザに近いキブツでのことだ。この辺りは大半が荒涼たる不毛地帯で、当時でもバスから見た景色ではそこここに灌木が生えている程度だったが(写真 2 )、時折インパラか羚羊のような動物が駆けているところを見ると生命を拒む地ではないらしかった。イスラエルでの生活が長い案内役の日本人の話では、第一代・第三代の首相を務めた建国の父ベングリオンは70 歳で夫人とともにここに入植し、キブツを建設して老いの身で開拓に励んだという。

写真2 ネゲヴ砂漠の風景
この開拓こそはイスラエル建設後の全ユダヤ人の使命となって、それまでのディアスポラ(離散)の二千年にわたりアラブ人にもパレスチナ人にも、またそこを数百年間支配した(オスマン)トルコ人にも放置されていた地域を、徐々に農耕可能な国土に変えていったのだった。歴史上どの国においても土地の所有を許されず金銀や宝石など動産に頼るほかなかったユダヤ人が、初めて自らの手で開墾することを許された土地、それがネゲヴだった。その風景を思い出しつつ私の頭に浮かんだのは、「低木のネゲヴ砂漠に希望の芽」という句である。よりによってその希望の地が今回の惨劇の舞台になるとは、何という皮肉であろう。
ハマスによるイスラエル襲撃のニュースに加え、彼らが人質として拉致した人々の中に自国民がいたことを知った欧州諸国は驚愕し、ただちにこぞってハマスを非難する声明を出したが、政府の表向きのハマス批判の後ろには各国の左派や学生たちのパレスチナ支持があって、事はそう簡単ではなかった。さらに自国民が人質になったといっても、そのほとんどが二重国籍を有するユダヤ系の人たちだったことも、反ハマス・親イスラエルの声に不協和音をもたらした。
現在のユダヤ人の人口は世界全体で 1500 万人弱とされ、最大はむろんイスラエルの 613 万人、次がアメリカの 543 万人、そして三位はフランスの 50 万人となっており、英国とカナダがそれに続く。ドイツが 7 位で 12 万人とぐっと少数なのは、ナチの迫害でドイツを脱出したユダヤ人が多く、また戦後もイスラエルやアメリカへの移住が相次いだためだが、私などからすると、自分たちをあれほど残忍な目に遭わせた恐ろしい国に 12 万人も残っていることの方が驚きである。
フランス在住のユダヤ人が多いのは、戦前・戦時中にドイツや東欧から遠すぎる米国やイスラエルの代わりに西隣のフランスに逃れた人々がかなりいたためで、現在のフランスではユダヤ系知識層の活動が目立つ。近年はその人たちが中東・北アフリカからのイスラム教徒やイスラム左派グループの攻撃の的になっていて、身の安全が保障されないことから、ここ数年フランスからイスラエルへの移住者が増えている。
ドイツにおけるユダヤ人の立場は現在も極めて複雑かつ微妙だが、フランスのようなあからさまな暴力には曝されておらず、第二次大戦の経験から「反ユダヤ主義」をおおっぴらに口にすると厳しく罰せられるなど、一見ユダヤ人は保護されているように思える。しかし逆にそうした配慮が、国民の対ユダヤ人感情に大きな影を落としている。
ドイツにはユダヤ人中央評議会というのがあり、ドイツ人の言動を厳しくチェックしていて、公人や著名人の発言に僅かでも反ユダヤ的な匂いが嗅ぎ取られるとたちまち非難の嵐となる。言葉のあやで、うっかり昔のユダヤ人や彼らの慣習を引き合いに出そうものなら、即座にさらし台に立たされ謝罪を迫られる。また、ドイツ国内の監視機関に加え、米国に本拠を置く反ユダヤ監視組織シモン・ヴィーゼンタール・センターの存在も恐ろしい。ここに睨まれると大抵の人はそのキャリアを絶たれる。
ヒトラー政権下で 600 万人のユダヤ人が虐殺された恨みから言えば、戦後の 60 年や 70 年でそれを忘れるわけにはいかないだけでなく、うっかり見逃せばあの時代の再来になるという恐怖が今も彼らを捉えて離さない。しかし、自分の国で何か意見を述べるにも細心の注意を払わねばならず、片言隻語が上へ下への騒動になるという事態に、ドイツ人は正直うんざりしているのである。自分たちは一体いつまで、このように痛罵され譴責されて悔悟の涙にくれなければならないのか。
ホロコーストを持ち出されれば弁明は一切できないだけに、逆恨みといわれても、この苛立ちは活動家や思想家よりも普通の、それも良識派とされる庶民の間に地下の地震波のように広がっていて、それがいつか何かの形で表面化するのではないかと私は危惧していた。
だからメルケルが 2015 年に中東からの難民を無条件で受け入れると発表したときには、アッと思った。難民の 99 %はイスラム教徒で、自国では幼年時代からイスラエルへの憎しみを植え付けられている。ある人の言葉によれば、イスラエルを潰せ、ユダヤ人を殺せ、というスローガンをバックグラウンドミュージックのように聴きながら育った人々である。
ドイツの世論が圧倒的にメルケルを支持し(これで善い国になれる!)、先進国の大半が彼女の人道主義を褒めそやしていた時期に、「ようこそ、難民のみなさん」というメルケルの言葉は、実際は「ようこそ、反ユダヤ主義のみなさん」と言うに等しいと激怒したユダヤ系のジャーナリストもいた。彼の怖れがパラノイアでなかったことは、目下のドイツの状況が証明している。
ローマ帝国がキリスト教を国教と定めた紀元 4 世紀末から 1600 年余り、ユダヤ人に対するキリスト教世界の憎悪と軽蔑と排斥は、ユダヤ教徒たちが旧約の世界に閉じこもり、イエス・キリストを神の子と認めないからという理由をはるかに超えて、西洋世界全体にアメーバのように広がっていった。
その憎しみに確たる根拠や理由などない。私は時々、心理学の用語である「投影」という言葉について考える。自分が誰かを忌み嫌っている場合にその理由として、それは相手が自分を憎んでいるからだ、とその憎悪を正当化する。相手も同じことを言う。
これではまるで、二つの鏡を向かい合わせに立てたときのようではないか。相手の鏡に映る姿は自分の鏡にも映り、それが際限なく投影されて留まるところがない。
その論拠として、これまで、パレスチナ人の領土を奪ったイスラエルが悪いとか、いや、自国の委任統治領をユダヤ人の新たな故郷とした 20 世紀初頭の英国の二枚舌外交が元凶だとか、そもそも彷徨えるヘブライの民が自身の国を求めるようになったのは英国島からシベリアに至るユダヤ人迫害のせいだなどと、今も百家争鳴である。どれも的外れとは思えないが、一つ確実に言えることとして、私はユダヤ人の苦難の歴史と現在の彼らの状況に関しては、この 1600 年間のキリスト教世界に責任があると思っている。
だが明らかに被抑圧者であるはずのそのユダヤ人が、今日では陰に陽に世界の政治経済を牛耳り(米国代々の FRB 総裁は、現在のパウエル氏を含む僅かな例外を除き全てユダヤ人である)、世界の大銀行はユダヤ人の掌中にあり、学術分野では世界人口の 0. 2 %でしかないユダヤ人がノーベル賞受賞者の 26、7 %を占め、経済学賞に至っては 4 割にのぼるという現実から、彼らが世界制覇をもくろんでいるというユダヤ陰謀論なるものも蔓延っている。また左派メディアの力もあって、それをまんざら嘘とは思わない隠れ反ユダヤのドイツ人も多い。
そういう嫉視や妬み・誹謗など歯牙にもかけず、近隣国はもちろん世界のどこからも愛されようとは全く思わない。それが受難の歴史に鍛えられたユダヤ人である。疫病や災害はユダヤ人への神の怒りとされて集団殺戮が続いたとき、真冬の雪原を着のみ着のままで遠い町に逃れたとき、数知れぬ同胞が強制収容所で差し迫る死の恐怖に震えていたとき、どこの誰が助けてくれたか。他民族の「人道」になど一切頼るつもりのない彼らであるから、国際世論を大きく巻き込んだ今回の戦争、はてどのような帰結を迎えるであろう。

(最後の写真は、出エジプト記でモーセが辿ったルートを逆にイスラエル側から進んで、シナイ半島のホレブ山の麓で私たちが泊まった宿。シナイは当時既にエジプトに返還されていた。)

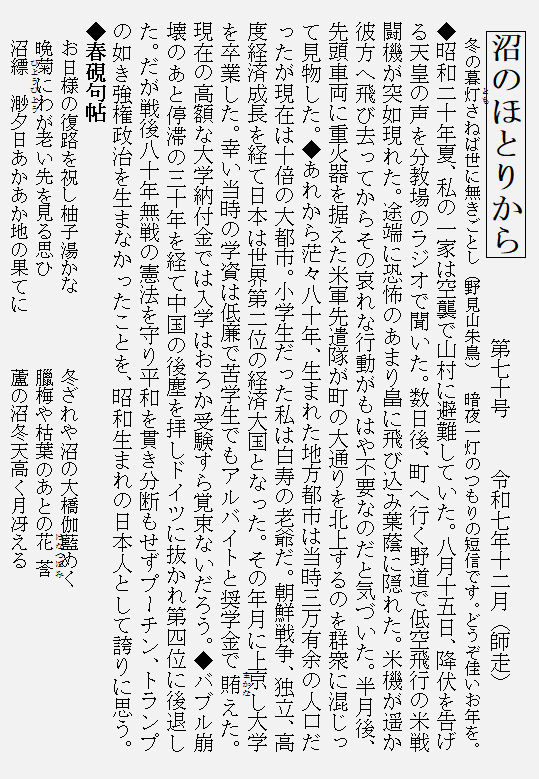


もう一つ思い出したこと。
連日ニュースでガザという地名がしょっちゅう出て来ます。昔何かでそこはガーゼという言葉の起源だと聞いたことがありますが、今でも一つの説ではあるものの、定説というほどではないようです。それよりも私が思い出したのは英国人作家オルダス・ハックスレーの「ガザに盲いて」という小説で、これ、私は読んでいませんが(ハックスレーの作品は超暗いので一冊で終わり)、このタイトルが英国で最も有名な詩人の一人ジョン・ミルトンの「闘士サムソン(Samson Agonistes)」の詩からというので、こちらは学生時代に読みました。
それで今頃になってふと、ガザとサムソンの関係を思い出し、旧約聖書で確認すると、神から人間離れした怪力を授けられたサムソンは、当時ペリシテ人(パレスチナ人)に支配されていたイスラエルを救おうとする。ところがペリシテ人の女デリラにたぶらかされて自分の唯一の弱点を教えてしまったために、ペリシテ人に捕えられ目をえぐられ、牢に繋がれる。その場所がガザでした。
イスラエルとパレスチナの関係は相当悪かったみたいで、その敵方の女に騙されたサムソンがバカだったのですけどね。デリラは英語でデライラ。昔はやったトム・ジョーンズの歌に「デライラ」というのがあったでしょう。
She was my woman As she deceived me, I watched and went out of my mind My, my, my, Delilah Why, why, why, Delilah
ミルトンがサムソンの詩を書いたのは、彼自身が40歳そこそこで失明したことと関係があるようです。ということは「闘士サムソン」を書いたとき盲目だったので、娘たちに口述筆記さえたと言われています。
イスラエル人にとってガザは因縁の地ということですね。
昔、50年余り前ですが、「日本人とユダヤ人」という本がベストセラーになったことがありました。作者は山本七平氏。私はこれを読んで、どうしても不愉快な気分をぬぐうことができませんでした。その理由を分析すると長くなるのでここでは踏み込みませんけれど。
一般に、日本の作家の中でクリスチャンとして有名な人たちをわたしは好きになれません。遠藤周作が日本でキリスト教徒であることの特異さについて語っていて、これはよく分かる。身に染みて分かる。遠藤周作はその特異性を追究して行って、いくつかのが傑作まれたわけですが。
ユダヤ人社会は決して一枚岩ではありません。それについて叙した本にガリチア(ポーランドからウクライナに跨る地方)で生まれたユダヤ人のアイザック・ドイッチャーという人の「非ユダヤ的ユダヤ人」があります。(アイザックはドイツ式にはイツァークと発音すべき、古代ヘブライ語ならイサク、アブラハムの子です。ドイッチャーはドイツ人という意味だから、先祖は長くドイツに住んだのか、ユダヤ人であることを隠すカムフラージュだったのか。)
これは1971年に翻訳が出たので、「日本人とユダヤ人」とほぼ同じ時期、イスラエル建国から20年ちょっとしか経っていませんが、すでに国内での分裂が明らかにされています。読みやすい本ではないので、ベストセラーにはなりませんでしたが、学べることはたくさんあります。
ユダヤ人といえば、ドイツ・東欧から来たアシュケナジムのユダヤ人(最もエリートとされる)、イベリア半島からスピノザのように一部オランダを経て(オランダやベルギーはスペイン領だった時期があるので)イスラエルに辿り着いたセファルディム。そして、これは半ば忘れられた存在になっていますが、ミズラヒム。これは東方のユダヤ人と言う意味で、出身地は北アフリカ、アラビア半島、インドなどです。銘記すべきは、この中に、2000年余りにわたって現在のイスラエル/パレスチナに住み続けて来たユダヤ教徒も含まれるということです。ユダヤ人は決して全員が故郷を捨てたわけではありません。ところがこの故郷を離れなかったユダヤ教徒、に加えイエメンや北アフリカなどからやって来たユダヤ人の身分が、現在のイスラエルでは最も低いのです。1948年の建国直後にイスラエルに移って来た時から、既に彼らは自分たちが歓迎されざるユダヤ人だと感じていたといいます。
日本でどの程度報道されているか分かりませんが、今回の紛争が起きる少し前から、ネタニヤフ首相が憲法改正を持ち出したことで、特にインテリ・エリート層からコテンパンにやっつけられ、欧米のユダヤ人知識層からも彼は「建国以来最低の首相」と批判されています。
ところが、このネタニヤフが上記のミズラヒムのユダヤ人に非常に人気があって、彼のファーストネームがベニヤミンであることから「ビビ」という愛称で慕われています。
この現状は、あれほどインテリから非難が集中しているトランプが、アメリカの田舎の州や産業が衰退した都市で人気を維持していることと共通点があるように思います。
こういう問題も含めて、ユダヤ人のイスラエルから私は目が離せずにいるのですが、だからと言って、安全と水をタダだと思っている日本人が愚かなどとは全く思いません。海に囲まれ森林の多い国で、砂漠の民と異なるメンタリティが根付くのは当然ではありませんか。安全を守るために多少の自由を犠牲にする、というのも国として一つの生き方ではないでしょうか。なぜ私たちが、イスラム教徒やユダヤ教徒やキリスト教徒のように生きねばならないのでしょう。
どの写真も2000年前のものと言われたってあーそうなんだと僕なんかは納得してしまいそうです。 旧約聖書に書かれていることにすぐにつながる風景があるということは人間の考え方にも反映しそうですね。日々歴史と向き合わざるを得ない。 わが日本民族が忘れっぽくて根無し草のような気がしてきました。 ユダヤ教とキリスト教、イスラム教ともこれからの人たちは向き合っていくことになる。それぞれが求めていることを知ることから勉強ですね。日本に住んでいればそのような問題を真剣に考えなくても良いという時代でもなくなってくるんでしょうね。 日本が来世紀も残っていればの話ですけど。 おとなしいから紳士淑女というわけではない日本人、追放の歴史が昨日のことのように日々の暮らしの中で浮かんでくる人たちには、言葉と土地はなくならないと思っている静かな日本人は、口に出さないまでも異星人と見られているかもしれないなとふと思いました。 僕にとって日本の風景は世界中にある。畳と障子と格子戸、軒先があって縁側の1つもあればそこは日本。そういう精神構造である僕自身もやはり根無し草かもしれない。