マッキンゼーが来ると――ドイツの黒い森から 50(びすこ)
- クレマチス

- 2023年2月2日
- 読了時間: 13分
昨年末、2022 年最後のわがブログ(「利他主義の破綻――ドイツの黒い森から 48」)に年末の不快な出来事の一つとして、フランスのマクロン大統領と米国コンサルティング会社マッキンゼーとの黒い噂に言及し、ついでに数年前に浮上したもののそのまま蓋をされているドイツの元国防相・現欧州委員会委員長ウルスラ・フォン・デア・ライエン女史とマッキンゼーとの癒着の疑いにも触れた。
火のない所からの煙ではないはずだが、相手がこうも大物とあればそのスキャンダルは欧州全体を揺るがすことになり、この人たちも too big to fail で壊すわけにはいかないから、大銀行と同様に制度・法律によってしっかり守られているわけだ。おまけにマッキンゼーもその業界では世界最大ときている。巨大化したらシメタもの、大きい者勝ちは、官と民を問わない。
それでもフランスのル・モンド紙などはかなりしつこく、マクロンが 2017 年と 2022 年の選挙戦でマッキンゼー社をコンサルタントにして、脱税まで幇助させた疑いがあるので検察庁が調査しているというニュースが昨年 11 月末に何度か報道された。それに対してマクロンは平静を装い、検察が行っているのはあくまでも通常の調査で自分には何もやましいことはなく、それはすぐに証明されるであろうと述べている。
マクロンへの疑いは別として、この件で欧州ではマッキンゼーの存在そのものが注目を浴びるようになり、今年に入ってからドイツやスイスの新聞にも関連記事が掲載され、ある新聞には「お偉方はマッキンゼーがお好き」という見出しの下に「ここのコンサルタントの評判は落ちているが、同社なしにやっていける大企業はほとんどない」という小見出しがあって、マクロンの写真が添えられていた(写真 1 )。

「そらま、そうでっしゃろなあ」というのが当方の反応だったのだが、この記事によって私は最近ニューヨーク・タイムズ社から「マッキンゼーが町に来ると―世界最強のコンサルティング会社の知られざる影響 When Mackinsey Comes to Town:The Hidden Influence of the World's Most Powerful Consulting Firm 」という一種の暴露本が出てそれがベストセラーになっていることを知った。
おや、それは面白そうだこと、と私もフライデーを買いに走る野次馬根性丸出しで、さっそくこの本を取り寄せた。出版は左派リベラルで知られる新聞社ニューヨーク・タイムズ(確か朝日新聞がル・モンド紙と並んでこの新聞と提携している)で、著者は同社の二人の記者、彼らは調査報道記者というふれこみになっている。いや、実際に彼らの、またこのグループに属する記者たちの、調査の腕はたいしたものらしい。後ろに大新聞社が控えているから比較的容易に取材の協力も得られるし、費用の心配もない。そういえば、昨年春にドイツで親ロシア派のシュレーダー元首相とのインタビューに成功したのも、ニューヨーク・タイムズのベルリン支部の記者だった(「プーチンの家来はかく語りき――ドイツの黒い森から 38」参照)。結局、新聞だって大きい者勝ちなのだ。
近年脚光を浴びるようになったこのタイプの報道者は、よく知られている通り 70 年代前半にニクソン大統領を辞任にまで追い込んだウオーターゲート事件報道のワシントン・ポストの記者をもって嚆矢とするが、私がどうもこの人達に良い印象を持てないのは、一世代以上前に彼らに与えられていた名称のせいもある。
学生の頃、必須科目でしょうことなしに齧ったアメリカ文化・文学概論にマックレイカーmuckraker という言葉が出て来た。muck は牛馬の糞、raker は熊手で掻く人、という意味で、臭い醜聞を掻き混ぜるように詮索して記事やストーリーにすることをマックレイキングという。
正義感に駆られて、あるいは真実を知らしめるという使命感から、この種の活動に情熱を燃やす人も多いのだろうが、若い私は父親の職業を訊かれてマックレイカーと答えるのは恥ずかしいと思ったものだった。いくら「職業に貴賤はない」とはいえ。あれから 50 年余り、暴露記事、いや真実を語る記事への需要も増えたし、社会的にも一定の評価が与えられているというので調査報道記者という聞こえのよい呼び名に変わったのだろう。
余談だが(本当についでの話)、muckraker という言葉について英語その他のウィキはあるけれど、日本語はない。ところが中国語ならあって、そこでは何と「扒粪记者」となっている。いや、こういうことを面白がっている私も私で、子供がいたら「恥ずかしいお母さん」と言われかねない。
さてそれで「マッキンゼーが町に来ると」の内容であるが、これをくどくど語りまた下手な解説などしているとブログ 10 回分くらいの長さになるので、ほんのサワリだけ紹介する。全 14 章からなり、1. やましさのない富―マッキンゼーの価値、2. 勝者と敗者―不平等マシーン、3. 両サイドでプレイ―政府を助けることはマッキンゼーを助けること、4. マッキンゼーと ICE(米国移民・関税執行局)―担当は政策でなく執行、5. 中国政府のお手伝い、6. 黄泉の門の守衛―タバコと電子タバコ・・・と続く。そしてその後の 7 章がハイライトとも言える「オピオイド販売の猛促進」(写真 2 )で、パーデューという今は消えた製薬会社の、45 万人の死者を出したと言われるオピオイド被害については、これも 2021 年 7 月のわがブログ(「ノーベル賞再考――ドイツの黒い森から 14」)で取り上げた通りである。

ただ、そこで憤慨したのは欲望に憑りつかれた製薬会社とそれを取り締まる米国版厚生省FDA の杜撰さで、パーデュー社がマッキンゼー社をコンサルタントとして獰猛といえるほどの販売促進を行っていたことは、当時の新聞・雑誌では言及されていなかったので私も知らずにいた。また、全米で裁判が起こされている中で、医師や病院・薬局に対しオピオイド系のオキシコンチンという薬を使うよう勧めた場合のリベート制度を考案したのがマッキンゼーということも、なぜか不問に付されていた。
この話は長くなるし、既にインターネットでいくつかの記事が読めるのでこの程度に留めるが、新刊「マッキンゼーが町に来ると」の中でもこの章は被害の程度と悪辣さで耳目を集めており、https://toyokeizai.net/articles/ にその要約があるので参照されたい。
また最近になって報道されたことだが、例によって「わが社が行ったのは助言であって、実行する・しないは顧客の自由」と嘯き、どんな被害に対してもわれ関せずだったマッキンゼーもさすがに世界中で非難囂囂となると聞こえぬふりもできず、どういう名目だか不明だが被害者に対し合計 6 億ドルを支払ったという。日本円で 780 億円、マッキンゼーの規模と収益から見てそれで社が傾くような金額ではないものの、賠償金としても慰謝料としても、主犯の製薬会社はともかくコンサルタント会社からの支払いとしては破格である。
全 14 章のいずれも、マッキンゼーという企業に馴染みのない人が読んだらほぼ間違いなく「ええええ!!」という反応になると思うが、今では日本支社もあることだし新聞・雑誌にも企業名やそこの花形(元)コンサルタントの名前がよく出るから、日本人の大多数はそれなりのイメージを持っているだろう。とにかく世界有数の頭脳集団で、ほとんどがアイビーリーグの大卒、そして大半はハーバード大で MBA(経営学修士号)を取得した超秀才である。中には経営学の博士号を持つ人もいるし、世界各地から集まって来る人材の中にはアメリカ人も含めオックスフォード大で学んだ人が少なくない。その新入社員の入門式のプロセスも「ほう」というところで、選りすぐりの若者にまず企業のヴァリュー(価値)についての徹底的な教育が為される。ちょっと洗脳的な感じもしないではない。モットーはまず世界をより良い場所(better place)にすること。人類のために尽くすこと。
しかし、お金は善行の後からついて来る、とはいかない。それぞれに客を連れて来る暗黙のノルマが課されているのである。顧客の事業モデルや理念に違和感があるなら、そこのコンサルタントになることを拒否してもよいが、客選びをして収益に貢献しなければ「仕事を変えるように助言される」ので、早い話が首になるリスクも大きい。それよりは、自分の意に染まずとも、社是のバリューとやらとの齟齬を感じても、四の五の言わずにコンサルタント業に励んだ方がいい。実際ほとんどの社員はその道を選んでいるようで、そうでなければ有毒なオピオイドの販売に猛進したり、保険会社にうまく保険金を踏み倒す術を教えたりできるわけがない。普通の感覚の人間としては、心中に自分のしていることに関して疑問や疚しさが生じることはないのかと訊いてみたくもなる。しかし彼らは「普通の感覚」など持ち合わせていないのだ。それならばいっそ、バリューがどうのこうのときれいごとを並べるのは止して、とにかくある所からできるだけ多くの金をとって来い、と命じればいいのである。
矛盾の最たるものは、5 章の「中国政府のお手伝い」を読めばこれでもか・これでもかというところで、マッキンゼーはこの国でいくつもの中央・地方の政府機関や官営企業のお手伝いをしているのだが、文字通り、一方でどんな矛にも突き破れないという触れこみの盾を売り、その裏でこれはどんな盾でも突き破れると断言して矛を売る、という商売を長年に渡って展開している。言い訳としては、それぞれのコンサルタントには厳しい守秘義務があるので社内で互いに情報を漏らすようなことはせず、従って利害の衝突があっても問題にはならない、のだそうである。
中国のほぼあらゆる分野、軍事、金融、エネルギー、インフラ整備、もちろん一帯一路の構想・実施にも関与しており、守秘義務の堅持を自慢するだけあって、同じ国の別の分野で同僚が助言している内容が自分の業務に支障を来たしても干渉しない。自家撞着も商売のうち。
しかしこの中国の章で圧巻なのは、あのしたたかな中国相手に甘い汁を吸っている、さらにしたたかなマッキンゼーが、会社の研修と慰労会を兼ねたような大イベントを新疆ウイグル地区のカシュガルで開催した話で、砂丘に赤いじゅうたんを敷きテントを張って西域の美女たちを踊らせ侍らせ、自分たちもアラビアンナイトさながらの扮装で饗宴を繰り広げたという事件である。
著者も書いているように、これは社内のイベントだからそれがジャーナリズムの注意を惹くということは通常はないのだが、問題はこのカシュガルでほんの数キロのところにウイグル人の危険分子(と中国政府が見なした人達)を収容するキャンプがあることだった。
ほとんどが無実でただ漢民族の苛酷な支配下から抜け出したいと望んでいるだけのイスラム教徒を、中国政府はかつてのソ連のグラーグのような場所に閉じ込めて「再教育」を施す。その収容所の存在をマッキンゼーともあろうものが知らぬはずはないのに、よりによってその近くで酒池肉林の宴を催すとは、というので記事になり、それを受けてマッキンゼー社は自分たちの行動が不適切であったことを認めたという。しかしまあこの話は、中国という国家やマッキンゼーという企業の正体を知る者には、別に驚きではないだろう。
それよりも私が驚嘆し、そして余りの面白さに大笑いをしたのは、12 章に記されたマッキンゼーの南アフリカでの事業展開、というよりその大失敗の顛末だった。とにかく何をやってもことごとく失敗する。どんな有能・辣腕の社員を送っても、まるで役に立たない。南アフリカの政府(という言葉すら当て嵌まらないが)の支離滅裂ぶりは、矛盾などという生やさしいものではない。不法行為というのでもない。そもそも法律などあっても無きがごとくの無法地帯なのである。
よく言われるのは、タイのバンコックなど全員が交通ルールを無視して車を運転しており、それで何とかしている中に妙にルールを守ろうとする車が混じると、道路はとんでもない事態になってどの車も動きが取れなくなるそうだが、マッキンゼーが南アで直面した状況もそれと似ている。中途半端に契約とか約束とか、南ア人からすれば何の意味も持たないことをベースに動くので、マッキンゼーも躓いたり転んだりで困ったろうが相手としても迷惑千万だったに違いない。しかも南ア側はそれを計算してやっているわけではないので、天下の秀才たちには予測不可能で一層始末が悪い。
屁理屈とこじつけの中国には、理路整然を旨とするコンサルタントたちが同じく屁理屈で対処できるが、理論などというものは無縁の南アでは彼らも丸腰状態なのだ。「それまでマッキンゼーが米国で学ばなかったことを、ほんの 20 年足らず前にようやく脆弱な民主主義国となった南アフリカで学んだわけである」とあるのが可笑しい。ここに書かれているエピソードを脚本化して映画にしたら喜劇の傑作ができるだろう。
この本の評判を調べてみると、平均が 5 点満点で 4 点となっているのがやや意外だった。今の世界の風潮からして、この種の内容なら欧米では圧倒的な好意を以って受け入れられるに違いないと思っていたからだ。
その前に、本が手元に届いてから裏表紙の推薦・宣伝の言葉を読むと、最初の二つが絶賛だったのは、彼ら自身がニューヨーク・タイムズの記者だから当然とも言えるが(そのうちの一人はオピオイド・スキャンダルの張本人で製薬会社オーナーだったサックラー一家の悪事を暴いた「痛みの帝国」の著者 P. R. キーフェ)、三人目はかのジョセフ・スティグリッツ教授の評であった。2001 年にノーベル経済学賞を受賞したこの人は、米国なら民主党、英国では労働党を支持しており、つまり完全な左派でそれだけにニューヨーク・タイムズ紙の覚えもめでたい。
日本でも「知の巨人」とか呼ばれてもてはやされているようだ。私は以前たまたま帰国していたときにNHKで放映された日本の経済学者宇沢弘文氏の追悼番組みたいなものを見る機会があって、そこにこの宇沢氏の弟子だったスティグリッツが登場し、師が毛嫌いしていたというミルトン・フリードマンのことを口を極めて罵っているのが面白かった。なるほど宇沢/スティグリッツと、小さな政府支持で共和党寄りのフリードマンとではさぞ相性が悪かったろう。
当然スティグリッツ教授のマッキンゼー批判も激烈で、企業の利益と欲望を満たすためには手段を選ばないこんな会社のせいでアメリカの不平等が加速され、彼らの偽善と貪欲は世界の汚染と麻薬の問題に手を貸していると述べて、「どの頁を読んでも怒りで煮えくり返る思い」と言っているのは、さもありなん、というところである。
しかしこの世はスティグリッツ型の人間ばかりではないということを示しているのが、インターネットで見られる読後感想文である。もちろんこの本の読者層や彼らの嗜好・傾向からして、著者を褒め称えマッキンゼーへの怒りをぶつけた所感が多いのであるが、おや、と思ったのは二人の記者の偏りを指摘した声で、彼らが綴っている内容はジャーナリストとしてバランス感覚を欠くと批判している。また、この本を書くにあたっての情報源が、主に昔の勤め先に恨みを抱く元社員であることも問題視される。驚いたのはその意見に賛同する人が50 人近くいたことで、数多くの称賛の声にはいずれもせいぜい一人か二人が同意しているのと対照的である。
賛否両論どちらが正しいとも言い難く、あるいはそれぞれの言い分に理があるとも言えるが、こういう異なった反応があること自体は、今の世の中で望ましい現象のように私には思われる。特に米国人の若者たちは(近年はドイツ人やフランス人もだが)集団でヒステリックに誰かを糾弾するという傾向を強めており、まさに彼らのバランス感覚の欠如にはすっかり怖れをなしていたので、サイレント・マジョリティの健在を感じて一面ほっとした。
最後に、この書物に関してのどの批評でもどの紹介文でも引用されている、エピローグの中の元社員の言葉がマッキンゼーの現在を端的に伝えていると思うので、私も引用させてもらう。
「世界は陰謀集団によって支配されていると確信する人々が通常挙げるのは、イルミナティやレプティリアンといった秘密結社、あるいは<グローバル主義者たち>であるが、彼らは間違っている。重要な決定を下して人類の歴史の方向を定める秘密結社などというものは存在しない。しかしマッキンゼー社がある。」

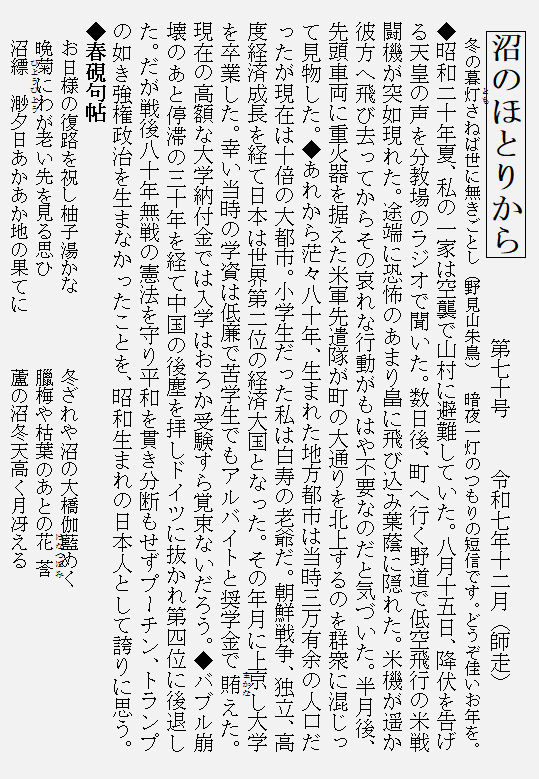


この本を読んで感じたのは、米国や欧州のみならずインド、中国などの大新興国におけるマッケンジー文化の急速な浸透と、日本での同文化の浸透度の薄さでした。欧米はそれを日本の保守性・閉鎖性に帰して批判し、あるいは嘲笑するでしょうが、現代の世界におけるこの日本の「特異性」は誇りにすべきではないでしょうか。
日本でもエリート層においては無論、マッケンジーやベイン、BCG(ボストン・コンサルティング・グループ)など世界的コンサルタント企業への憧れは強く、出来ることなら自分もその中で、と願う人は多いはずですが、一方で少なからぬ日本人が僻みや嫉妬ではなしに、それらから距離を置こうとしているように見えます。あるいはほぼ無意識に、関わりを持つことを避ける。
以前にどこかで引用した福田恒存の言葉を借りるなら、このような忌避は、日本人がそこに一種の「穢れ」を感じ取るためではないでしょうか。雄弁なキリスト教の宣教や経営者/株主優先の企業文化にどうしても馴染めずにいる心性と通底するものがあるように思えます。そしてこの精神性こそが日本を救うような気がしています。
頭の良い人たちが何を考えているかには大変興味がありますが彼らの頭の中が整理できているとは到底思えません、とにかく優秀なので右往左往している連中がバカに見えてしょうがないのではないでしょうか…びすこさんの解説を伺いながらそう思いました。誤謬を認めるなんて事は人生においてありえない、だって誤謬ではないと言い張った途端、利害関係者に支持される仕掛けがシステムに織り込み済みでは牛耳っている連中の人数が少ないとしても一人一人は一騎当千、一般庶民はゴミ同然、ごまかされておしまいのような気がします、追求する気力さえ起きない…これが問題でございますね。