ノーベル賞再考――ドイツの黒い森から 14(びすこ)
- クレマチス

- 2021年7月1日
- 読了時間: 9分
オピオイドというのはその名の通りオピウム(阿片)に関連しており、芥子から取れる成分の合成化合物で、鎮痛効果があって手術の麻酔にも使われる。問題はこのオピオイドに陶酔作用があることで、痛みの緩和ではなくモルヒネやヘロインのように麻薬としていわゆるジャンキーの間で売買されるようになった。医師が介在していた場合でも、このオピオイド過剰摂取による死亡事件が近年頻発し(プリンスとかいう歌手の死もその例)、時折英字新聞で opioide という単語を目にすることがあったがさして気に止めずにいた。
さて数週間前のこと例のエコノミスト誌の書評欄を覗くと、そこにルーブル博物館(美術館)の入口にそびえるガラスのピラミッドの前で横断幕を広げ旗を振る数人の写真があった。横断幕には「サックラーの名を外せ」と書かれている。
その隣のページがたまたま、ナポレオンがヴェニスから奪って返していない大作の話だったので、ルーブルの展示品を元の所有者にという運動かと思ったが、どうも違う。
書評の対象は Empire of Pain (痛みの帝国)という題の本で、それの著者キーフェというアメリカ人はいわゆる調査報道記者として(この分野はウォーターゲート事件の真相を暴いたワシントン・ポストの記者二人をもって嚆矢とするらしい)、オピオイドの効果を強化したオクシコティンを 90 年代に市場に出した製薬会社の元オーナー・サックラー一族の悪行を500 頁あまりにわたって暴露している。

サックラー家はウクライナからのユダヤ人移民夫婦から生まれた 3 人の息子の商才によって巨万の富を築き、米国有数の富豪として官・産・学界に影響力を行使し始め、博物館など世界の名だたる文化施設に気前よく寄付をし、サックラーと記した看板を立てさせ、また「サックラー・ルーム」など設けてその力のほどを示威してきた。
問題は薬の開発よりもそのマーケティング手法で、副作用や危険性について嘘っぱちを並べ、監督官庁やら大病院の医師たちをカネの力で骨抜きにし、この鎮痛剤を摂取した病人の多くを中毒患者にして死に至らしめた、ということで、犠牲者とその家族はもちろん米国の多くの州及び連邦政府からも訴訟を起こされている。
訴えが認められれば億でなく兆単位の賠償金を払うことになるが、それを見越してサックラー一族は早い時期に店じまい、つまり会社の計画倒産を実施して、原告たちが何ももらえないようにし、そのことがキーフェらジャーナリストや活動家の憤怒の炎に油を注いだ。そしてこの悪辣な手法による富の分け前に預かった欧米の博物館もまた、弾劾の対象になっているのである。
キーフェはこの本を書くに当たりサックラー家の歴史を徹底的に調べ、最初のかなりの部分は一族の「私」の部分に割かれているらしい。そのせいかインターネットで調べても、サックラー家の三兄弟に始まりその妻たち(いずれも数回離婚している)、彼女たちとの間で生まれた子供(妻の数に比例して子供も多い)、さらに孫に至るまで関係者が列記されており、「正義」というなら悪徳商法で潤った一族全員に責任を取らせるべき、という世論になっている。まさに「罪九族に及ぶ」というところである。
ゴシップやスキャンダルを娯楽とする一般市民には好個の話題だが、今回のブログでは実はそれは焦点でなく、ここまでの部分は「前置き」なんです。
悪漢三兄弟の行状はさておき、開発された薬はどのようなものだったか調べると、彼らはいずれも精神科医だったので、治療の対象は双極性障害など精神疾患であった。精神科の患者への薬物治療が始まったのは比較的最近のことで、それまでの数十年間はポルトガルの神経科医アントニオ・エガス・モニスの開発した「ロボトミー」と呼ばれる手術が最適の治療法とされていた。
今の世の中でロボトミーという言葉を耳にすることはほとんどないが、ブリタニカ国際大百科事典によればこれは、「脳葉(→大脳)の神経回路を脳のほかの部分から切り離す外科手術。前頭葉白質切断術ともいう。かつては、→総合失調症,双極性障害(→うつ病)、その他の精神疾患をもつ重篤患者に対する抜本的な治療法として実施された」そうである。
さらに「ロボトミーを受けた患者の大部分は、緊張、興奮などの症状が軽減したが、無気力、受動的、意欲の欠如、集中力低下、全般的な感情反応の低下などの症状も多く現れた。しかし、こうした副作用は 1940 年代には広く報じられず、長期的影響はほぼ不明だった」そうで、にもかかわらず「ロボトミーが幅広い成功を収めたとして、モニスは1949 年にノーベル生理学・医学賞を受賞した」と記されている。
他の資料によると、前頭葉の白質の部分を切開し神経線維を切断するこの外科療法で、人格変化や知能低下を起こしたケースが少なからずあって、極端な表現をするといわば「廃人」になってしまった患者もいたようだ。にもかかわらず副作用は隠蔽され、患者にもその家族にも正しい情報が与えられることなくこんな治療が続けられたということは、現在の常識からみて信じがたい慣習が医学界に横行していたわけである。時には政治犯にこの手術が強制的に施されたとも聞く。旧ソ連のラーゲリなどではあり得た。あるいはスペインのフランコ政権でも。
実は私がこのロボトミーという言葉に嫌悪感を催すのは若い頃見た映画のせいで、以来この療法を呪いのように感じている。映画の題名は「去年の夏、突然に」、原作はテネシー・ウィリアムズで主演はエリザベス・テーラーとモンゴメリー・クリフトだった。簡単に筋を紹介すると、エリザベス・テーラー演じるキャサリンは同性愛者の従兄との旅行先で「男漁り」の餌として使われるのだが、従兄は暴徒たちに残虐な殺され方をし、そのショックでキャサリンは精神を病む。息子の秘密を知られたくない母親は、精神病院に入れた姪のキャサリンにロボトミー手術を受けさせて記憶を消そうと考える。そこに登場したモンゴメリー・クリフト演じる医師がキャサリンに会って手術は不要と判断し彼女を救い出す、という話。
この映画の記憶で、私としては悪質な商法でのし上がったサックラー一族にはむかつきながらも、兄弟の薬物療法の研究開発によってこのロボトミーに終止符が打たれたという事実には、一定の評価が与えられてしかるべきだと思った。
しかし私が一連のスキャンダルについて調べた中で最も大きな衝撃を受けたのは、ロボトミーという、害の方が効果に勝るいかがわしい療法の開発により、神経科医のモニスがノーベル賞を受賞したという事実だった。FDA (アメリカ食品医薬品局)他の管轄官庁がロボトミーの効能とダメージとに関する調査を怠ったということと、ノーベル賞選考委員会が治療の実態を把握していなかったということとは、話が別である。
そもそも私はこのノーベル賞なるものに近年とみに不審の念を抱くようになっており、数年前に文学賞の審査委員会メンバーの不正が摘発されて以来、文学賞など止めちまえと思っているが、止めてほしいのは経済賞と、それから平和賞も同様である。
経済賞など大半の受賞者が米国のユダヤ人なのはまあいいとして、彼らの知能指数がいかに高かろうと、金と数値を扱う世界に「普遍的な真理」があるとは思えず、「証明」も極めてむずかしく、それがどれほど人類の幸福・安寧に貢献しているというのか。(経済オンチのゴマメの歯ぎしり。)
平和賞というのも、今や政治的な思惑に左右されてばかりで、大体ゴアなんて政治家がなぜ賞をもらうのか、オバマがどんな特別なことをしたのか、こういう人選は賞の名を貶めるばかりだ。政治家が平和を目指すのは魚屋が生きのいい魚を売ろうとするのと同じで、仕事柄為すべきことを為して賞(プラス懸賞金)をもらうなんて鉄面皮とも思える。
ビルマのアウンサンスーチーさんなど、さんざんもてはやされ賞をもらったのはいいが、実際に政権についた途端ロヒンギャ難民事件が起きて危機への対処能力の欠如が露呈し、一部の平和運動家や人道主義者たちから賞を取り消せという声が出ている。何を今さら。私はテレビなどで彼女の挙措を見て、まるで王族さながらの態度にいささか呆れ、あんた、それで国を治めるのは無理やで、と思った。
世界のどの国・地域を見ても、第一回の平和賞を受賞したアンリ・デュナンや戦後のアルバート・シュヴァイツア-のように品格溢れる清廉な人間(しかも彼らは私人として活動した)は、今や地を払うごとき状況になっている。それなのに、お祭りは続けなくちゃと、無理やりどこかから誰かを引っ張り出してきてみんなで喝采なんて、笑劇でしかない。
だがそういう中でも、科学部門のノーベル賞だけは確固たる根拠があってごまかしや損得勘定や政治的思惑などとは無縁だと思っていた。化学も物理も医学・生理学も確立された学問分野で人類の進歩に貢献するものだから、それらにおいて大きな業績を達成した人が表彰されるのは当然であろう。
しかしこちらの賞にもどうも胡乱なところがあると気づいたのは、先回のブログの最後で触れた「免疫の意味論」(多田富雄)を読んでいたときだった。
内容がこの私にはあまりに専門的で高度なので、自分の疑問すら人に説明するのは難しいのだがごくかいつまんで話すと。
ロンドン生まれのデンマーク人医学者ニール・K・イェルネは免疫学的認識構造について「天文学的多様性を持つ抗体分子が、お互いにその多様性を認識し合ってネットワークを作っている」というネットワーク説を打ちだし脚光を浴びる。
しかし彼の理論はその後に出てくる新説により打ち消されて「崩壊」し、今ではネットワーク理論はそれに言及することさえタブー視されているのだそうだ。
「免疫の意味論」が書かれた当時イェルネはまだ存命で、このエキセントリックともいえる学者はフランスの古城に閉じこもったきりだったというが、その奇矯な性格はともかく、ノーベル賞を受賞するほどの学者の説がこのような扱いを受けるというのは、ノーベル賞の選考自体に問題があるのではないかと思わせられる。
著者の多田富雄はイェルネを「悲劇のノーベル賞学者」と評しており、彼によると、ネットワーク説は全面的に否定されたわけでなく、一部の免疫学者は「いつかはそこに戻らなければならない」と考えているそうである。(ちょっと楽しみ)
この話で、ノーベル賞っていったい何なの、と大いに戸惑っていると、同じ本の中に著者自身がその疑問を呈している箇所があった。
主要組織適合遺伝子複合体(MHC)というのは移植に関連した遺伝子座のことだが、このMHC の発見とその働きの研究に対し、1980 年にスネル、ドーセ、べナセオフの三人の学者にノーベル賞が与えられた。しかし・・・多田氏はそれについて次のように叙している。
「一般に、ある研究にノーベル賞が授与されたということは、この研究領域が既に完成してしまったことを示す。さまざまな二次的な問題は残されるが、もうノーベル賞級の大発見は期待できない。同じ売り場から宝くじの特等が二度と出ないのと同じである。
ところがMHCに関しては、その後になってから重大な発見が続出した。今になってみると、1980 年のノーベル賞はいささか早まった感さえある。いまの時点だったら、違ったコンビの受賞者を考えることさえできるだろう。」
考えてみると、ノーベル賞のあり方にも、その創始から120 年を経て当初は予測不可能だった複雑な問題が生じているのだが、一方で、これほど情報の入手がしかも大量に可能となった現在、人々はそれらを賢く用いて、いかなる世界的権威といえどもそれを崇めたり鵜呑みにしたりはしないという知的訓練を自らに課すべきだと思う。

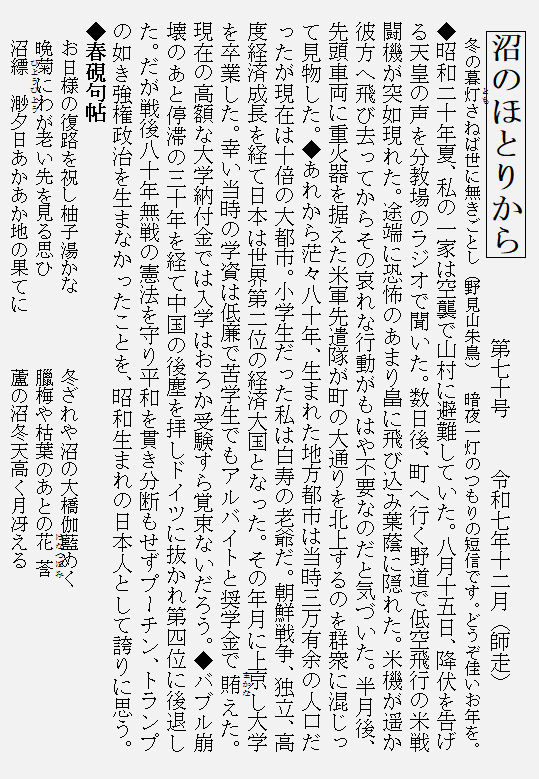


このブログを拝見して思った事は人間の業:カルマ、因果応報です。かのチャールズ・ダーウィンが控えめにそれでいて今も彼の先見性において舌をまくものであるとある学者は述べていましたが今回の話題はそれとは対極にある事柄でした。 オピウムからパリのルーブル博物館前の告発横断幕、ノーベル賞のあり方さらには現代人が備えるべき社会リテラシーまで話がいつものように明快かつ物語的:ナラティブ、俯瞰的にしてピンポイントな縦横無尽なびすこ特派員の、、、名前ばかり有名な新聞社も少しは見習えと言いたくなる位の筆先冴える報告、面白かった!ありがとうございました。 (オピウムをめぐる今回のブログは商業的側面に重点があったような気がしますが、、歴史的、政治社会的、芸能興業的?視点での追求もそのうちよろしくお願いします、僕は化学的なオピウムに変わる器質的、つまり取り上げてくださったロボトミー志向、偏向が、またぞろ頭をもたげてくるような社会的傾向が気になっています。世界中で議論の焦点にすべきだと思っていますので🥺)