シュヴァイツァー博士との再会――ドイツの黒い森から 25(びすこ)
- クレマチス

- 2021年11月2日
- 読了時間: 12分
イタリアから流れてきたわが家のビアンカは元気な甘えん坊だったが、あるとき足の裏を怪我したのか、棘でも刺さったのか、妙な歩き方をし始めた。前脚を掴んでひっくり返して触ると、キャンキャンと悲痛な声でなく。
病院に連れていくことになり、我が家から 20 分ほどのケーニヒスフェルトという閑静な町の外れにある獣医を紹介してもらって、夫の運転で出かけた。そのケーニヒスフェルトの通りを走っているとき病院らしき建物に Albert Schweitzer という名前を見たような気がして、おや、と思っていると、間もなく「アルバート・シュヴァイツァーの家」という看板が立っていて、ここを左折するとその家だという矢印があった。(Albertは日本ではアルベルトと表記されるが、ここではドイツ人の普通の発音に従ってアルバートとする。)
この町とシュヴァイツァーとどんな関係があるのかと夫に訊くと、シュヴァイツァー博士はアフリカで医療活動に従事していた数十年間、夏になるとこの地で静養するのが常だったという。え、だってシュヴァイツァーはアルザス出身でしょ、どうして故郷でなくてここを休暇地に選んだの、とさらに尋ねると、さあ、それは、と要領を得ない。アルザスには生家が残っているという。

アルバート・シュヴァイツァーの家
ビアンカの怪我はたいしたことがなくて一度の診療で済んだが、博士の別荘のことが気になったので、次の日曜日に夫に頼んで一般に公開されているその家に連れて行ってもらった。この人物にふさわしく、シンプルで品があって程よい大きさの住まいだった。こんなところにいらしたのですか、と昔初めて博士の偉業を知ったときの感動が蘇った。
しかし受付で挨拶して中に入った途端に感じたのは全体を覆う病室のような雰囲気で、クレゾールの匂いが漂ってくるような錯覚に捉われた。それはどの部屋にも最小限の家具しか置かれておらず無菌といいたいほど清潔だったためもあるが、壁にかかっている写真に添えられた説明を読んでいて、そうだったのか、と納得したのは、この家が博士の夫人の療養所を兼ねていたということである。ヘレーネ夫人は結核にかかっており、当初は博士とともにアフリカに住んで妻・病院の共同設立者・看護師として彼を支えたが、ランバレーネの気候は病む体には厳しすぎた。
この家にシュヴァイツァーが越して来たのは 1923 年とあるから、二つの世界大戦の間の時期で敗戦国ドイツが勝者のフランスから要求された賠償の重さに喘いでいた頃である。ベルリン生まれの夫人は当時 44 歳、一人娘のレーナは 4 歳。そして彼女はここからケーニヒスフェルトの学校に通った。
私がこの事実からシュヴァイツァー博士に特別な敬慕の念を覚えたのは、アルザス人として独・仏の争いに翻弄され続け、幾度も国籍を変えさせられ、第一次大戦時にはドイツ国籍だったためアフリカで仏軍による軟禁も経験し、最終的には両次大戦で勝利したフランスに属する身となるが、そのフランスではなく敗れたドイツに保養地を求めてそこに妻子を住まわせたことにある種の気高さを感じたためだった。
シュヴァルツヴァルトからアルザスはライン河を越えてすぐで、少し山の方に入った生誕地のカイザースベルクですら 2 時間足らずの距離である。しかし 20 世紀全体を通じ、独・仏二つの国は遠く隔てられていた。その憎悪は一般に言われているようにドイツ側にだけ甚だしかったわけではなく、当然ながら相互の感情で、私たち第三国の人間が信じさせられている「ドイツによるフランス虐め」は、戦後の「連合国はすべて正しい」というプロパガンダに洗脳された部分が大きい。
一例を挙げると、私たち団塊の世代以降の子供が小学生のころ使った教科書にはアルフォンソ・ドーデによる「最後の授業」という話が載っていたが、後に判明したところでは、これはアルザスになど足を踏み入れたこともないドーデが愛国心の鼓舞を意図するフランス政府に頼まれて書いた物語で、彼の言うフランス語の禁止(実際は「望ましくない言語」程度の規制)は 1870 年代の普仏戦争におけるフランスの敗北による。
しかしアルザスの宙ぶらりんの状況は実のところ、ハプスブルク家を頂点としてドイツ人が統治していた神聖ローマ帝国からルイ 14 世がここを取り上げた 17 世紀末に始まり、それまでドイツ語圏だったのが、18 世紀以降はそれぞれの時代における両国の力関係次第でフランス語が半ば禁止されたり、ドイツ語が排斥されたり、ということの繰り返しになった。
フランスが終始被害者だったというのはこれもまた与太話に過ぎず、それに乗ってドイツを悪者とする時流に媚びた観のある戦後日本の教科書選定は、同じ敗戦国としての配慮も慎みもない、いわば武士道に反する行為だったと私は思う。
私が初めてアルザスを訪れたのは 2001 年にドイツに渡って間もなくのことで、可愛らしい絵本のような町で何よりも驚いたのは、そこの本屋に並ぶ「反ドイツ」の書籍の多さであった。店先にはナチの腕章をつけたドイツ人兵士の写真を表紙とする本や古い雑誌が所せましと並び、あたかも「ドイツ人の蛮行を忘れるな」と叫んでいるように見えた。
その光景に衝撃を受けたのは、アルザスの住民が再びドイツ人になることを決して許してはならない、戦後国力が低下したフランスに比してのドイツの繁栄を見て「ドイツ人だった方が良かった」と彼らに思わせるようなことがあってはならない、というフランスの国家政策が醜いほどに露わだったからだ。(反独の書籍販売への報奨金もあったと思われる。)
それが 20 世紀から 21 世紀への変わり目の現象であってみれば、このドイツ人憎悪扇動は 20 世紀の前半には何倍も激しかったに相違ない。ライン河右岸は敵地であった。
そういう感懐があったので、その 5,6 年後に見つけたドイツの町(しかもわが家の近く)のシュヴァイツァーの家には胸を打たれた。そのときの思いには、戦争で父親を失い辛酸をなめたドイツ人を夫に持つ、敗戦後の貧しい農村に生まれた日本人としての、感謝の念すら混じっていた。
かつてのケーニヒスフェルトは保養地としても知られており、郷里から地理的に近いこともあって 1920 年代に訪れたこの地の空気と風景と住民気質がシュヴァイツァーの気に入り、病身の妻の療養と娘の教育には最適の地と判断したらしい。
また、このケーニヒスフェルトという町には一般にモラヴィア兄弟団と呼ばれる、チェコのフス派を源流とする共同体が設けられていて、かつてドイツ東部や東欧からの宗教難民を受け入れた経緯があり、プロテスタント牧師の息子で神学者でもあったシュヴァイツァーにはこの町の文化的背景やエートスが親昵しやすかったのだろう。
シュヴァイツァーにとってここは妻や娘と過ごしてランバレーネでの深い疲労を癒すとともに、資金集めのためにオルガン演奏会の準備をしたり、その後世界中から依頼されるようになった講演の原稿を書いたりする場所だったという。
見学を終えてから受付で私は彼の著書を数冊買った。よく知られているのは「水と原始林の間」で、これはアフリカでの日々の記録なので当時の私のドイツ語力でも読めた。また博士の動物好きはつとに有名だが、それをユーモラスに綴ったペリカン飼育記などもある。

仲良しのペリカンと
しかし私が見つけて、これは是非とも読まねばと思った「生命への畏敬」という本は、薄手ながら相当難しく読み進むのに苦労したが、その中で「今日の世界における平和の問題:ノーベル賞受賞時のスピーチ、1954 年オスロにて」という章に出くわしたときは、ああ、これが読みたかったのだ!と飛びあがるほど喜んだ。
講演原稿だから僅か 16 ページなのだが、結構な難物である。そして中身が非常に濃い。ドイツ語初心者の私は同じ文を三度くらい読んでようやく理解するという具合であった。それでも、読み終えずにおくものか、というこのグータラ女に珍しい気力で臨んだのは、それが、ケーニヒスフェルトで「ドイツにおけるシュヴァイツァー」に遭遇したときの感銘を増強する内容だったからである。
(シュヴァイツァーの受賞は 1952 年だがそのスピーチが 1954 年となっているのは、今と違ってアフリカからノルウェーに一飛びとはいかず、アフリカでの医療とともに寄付集めの活動にも多忙を極めていたためではないか。実際彼は受賞講演で訪れた北欧に一定期間滞在し、予想外の寄付金を得ている。)
オスロでの彼の講演は、「戦勝の結果として今日の世界の形成を担う政治家たちは、決して幸運な人々ではない」という言葉で始まる。それに続いて、<彼らの多くにとってはとにかく勝利という事実を確認することが先決で、実り豊かな未来を築くなどということは二の次であった。仮に彼らの中に先見の明や洞察力のある人間がいたとしても、戦争直後の状況は、理性や分別に導かれて判断することを彼らに許さなかった。>と述べている。
特に欧州における国家群の再構成に関し、古くは 4,5 世紀の民族の大移動に始まる歴史を連合国が無視し、人工的な国境線を引いて新たな国家としたことに警鐘を鳴らしているが、これはドイツとその周辺の地理・歴史を多少なりとも知るものには頷ける言葉である。
例えば、ルーマニアにはドイツの入植地があったが(そこで育ったことになっているのが、ベルンハルト・シュリンク著「朗読者」のハンナ・シュミット)終戦と共に 25 万人のドイツ人は着のみ着のままでそこを追われた。さらに悲劇的だったのは、これは実は第一次大戦直後のことだが、現在のルーマニアでハンガリー人が所有していた土地が奪われてハンガリーの領土はぐっと縮小し、ルーマニアの面積が大幅に増えたことである。そして第二次大戦後の処理でも、ハンガリーの土地は戻って来なかった。
ハンガリーが国土の大部分を失ったのは、かつてオーストリア=ハンガリー二重帝国の片割れとして枢軸国に組みしていたためである。影が薄かったルーマニアは善なる国、ドイツ/オーストリアの仲間だったハンガリーは悪しき国で、従って罰せられねばならない。それが連合国のいう正義であった。
現在のルーマニアとハンガリーを比較すれば、単純に国民一人当たりの GDP を見ただけでその力の差は歴然としている。特に農業の生産性の差に関しては、ルーマニアは恥じてしかるべきだ。数年前のことルーマニアのトランシルヴァニア地方をロマ(ジプシー)支援プロジェクトの実態を見るために訪れたとき、そこの大部分がただの荒地として放置されていることに私ですら憤りを覚えた。
ハンガリー側には、国土の活用などには関心がないルーマニアに貴重な土地を盗られたままという恨みがあり、ルーマニアには「かつての敗戦国のくせに」というやっかみがある。
シュヴァイツァーは特に東欧とバルカン半島における連合国の政策に危惧の念を示し、このように過去の経緯を顧みず恣意的に造られた国家で平和が保たれるはずがない、と述べているが、ソ連の崩壊後 1991 年に勃発したユーゴスラビア戦争でその予言は現実となった。
驚くのは、連合国に対する正鵠を射た批判が、戦後間もない時期に戦勝国のお歴々を前に為されたという事実である。祝受賞の講演会に居並ぶ聴衆の大半は英・仏・米の著名人であったろう。講演者がドイツの犠牲者アルザスのシュヴァイツァーとあって、聴く側はドイツを弾劾し連合国の勝利を寿ぐ内容を期待していたに違いない。その彼らの失望・不機嫌ぶりは容易に察せられる。
シュヴァイツァーがその後よく「あなたはフランス人かドイツ人か」という質問を受けたというのも、彼の姿勢を曖昧と感じて不満に思う人が特にフランスに多かったからであろう。その質問に彼は「私はアルザス人」あるいは「自分はアレマン人」と答えていたという。
アレマンとはゲルマン系の一族の名で、現在のドイツ西南部のバーデン地方(シュヴァルツヴァルトはその一部)、スイス北部、およびアルザスのあたりに定住した部族をさし、フランスは東でこのアレマン人の地域に接していたことから、フランス語でドイツをアルマーニュと呼ぶようになった。
勝ち馬に乗って敗者を叩くことほどシュヴァイツァーの倫理から遠い行為は無かった。ドイツをアルザスの敵と見なすことなど、連合国がどれほど望んでもこの人には論外であった。それについて夫人がドイツ人であったことを指摘する人もいようが、ヘレーネ夫人の出自がユダヤ系の家庭と知れば、この私ならずともシュヴァイツァー博士の寛容の前に頭を垂れるのではないか。
さて、この「生命への畏敬」を読みシュヴァイツァー博士への尊敬の念を深めて後のこと、ドイツに関しいろんな本を読んでみたがこのあたりで本格的なドイツ史を、と探し出したのは、林健太郎著作集であった。
この学者の名は団塊世代・全共闘世代には馴染みがあるはずだ。東大文学部の部長だった 1968 年、全共闘のメンバーに何日もカンヅメにされながら彼らの要求をすべて蹴った剛の者として知られる。(ろれちゃんがファンの林望先生の伯父さんでもある。)
かく言う私も「密かにお慕い申し上げていた」ひとりだった。当時から歴史学者ということは聞いていたが、専門がドイツ史と分かったのは比較的最近のことだ。
この人の著書ならば内容も立派であろうと全四巻を注文したが、第一巻だけは入手できなかった。いずれもドイツ史専攻の大学生・院生向けらしく私のような素人には知識・能力不足を痛感させる部分もあったけれど(ドイツの 18・19 世紀の思想史など)、それでも諦めずに読んでいて、思いがけない幸運にめぐり合った。
それは第三巻『ドイツの歴史と文化』の最終章「フリードリッヒ・マイネッケの生涯と思想」においてで、林健太郎氏がこの章を結ぶにあたり「その時代を最も忠実に生きたことによって、彼(注:マイネッケ)は真理の祭壇に、派手ではないが決して消えることのない燈火を点じたのである」と述べていることから、著者がマイネッケをドイツで最も重要な歴史家の一人と見なしていたことは確かである。
その前に林健太郎氏は、16 世紀前半にドイツ人が創設し欧州の若者が隔てなく学んだシュトラスブルク(ストラスブールのドイツ語読み)大学でマイネッケが教えていた期間(1901 ~ 1908 )の経験を次のように紹介している。
「マイネッケはこの大学で一人の変わった同僚を持った。それは神学の私講師であったが、大学の談話室で始めて会った時から、マイネッケはその人物と容姿に引きつけられた。しかし彼は専門の研究以外にいろいろのことをするというので神学部の教授たちからはよく思われていなかった。彼はオルガンの名手で、マイネッケ夫妻はシュトラスブルクのある教会でその演奏を感動を以って聴いていたが、まもなく彼は黒人に医療を施すことを念願して医学の勉強を始めた。この人物は言うまでもなく、後アフリカの聖者としてあまねく名を知られたアルベルト・シュヴァイツァである。」
敬愛する人物に導かれてその家に入っていくと、そこにはもう一人の敬愛する人物が懐かしい笑みを浮かべて立っていた・・・そんな嬉しさを感じた逸話であった。

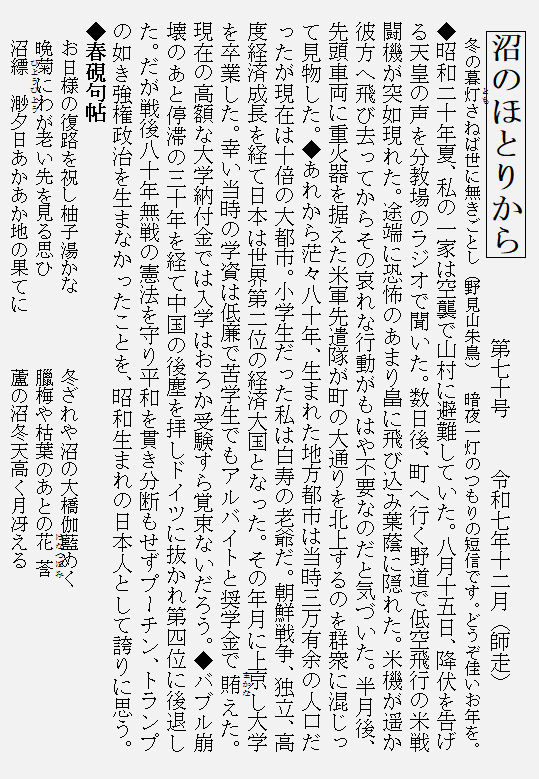


今回のブログはこれまでのどれよりも長くなってしまったので、ヘレーネ・シュヴアイツァーの生涯については触れなかったが、この有能で勤勉で献身的な夫人について日本では何の資料もないと思われるので、ごく簡単に触れておきたい。
彼女がユダヤ系の家庭に生まれたことはブログに書いた通りであるが、著名な歴史学者だったその父親は子供たちにはプロテスタントの洗礼を受けさせ、自分と妻とはユダヤ教徒のままであった。1879年生まれのヘレーネの子供時代にはユダヤ人迫害はなかったが、通常のドイツ人とはやや違った眼で見られていたことは確かである。
父親のハリ―・ブレスラウはその学識の高さをかわれて1890年、ヘレーネが11歳のときアルザスの首都ストラスブールの「カイザー・ヴルヘルム大学」に中世史の教授として招聘され、1912年までそこで教えた。(当時のアルザスすなわち1870年代の普仏戦争から第一次大戦の終わる1918年までのこの地方はドイツの支配下にあり、大学もドイツ皇帝の名前で呼ばれていた。)
ブレスラウ教授はその間に学長にまで昇進し、ドイツ語圏で最初のユダヤ人学長ということで一大センセーションを巻き起こしたという。
従ってシュヴァイツァーが大学で神学を教え、フリードリッヒ・マイネッケが歴史学の教授だった時代と、同じ大学でヘレーネの父親が教鞭をとっていた時期は一致する。そしてこの時期に19歳のヘレーネは、知人の結婚式でシュヴァイツァーと出会う。
二人は恋人同士にはなったが、互いに目標があったので結婚に至るまでには14年の歳月を閲した。ヘレーネは10代で教師資格をとったのち英国に渡ってチエホフやゴーリキをドイツ語に翻訳したり、再びストラスブールに戻って孤児院の監督官の任に就いたり、さらには未婚の母のための施設を設立するなど多岐にわたる活動を展開したが、恋人のアルバートの意思を知ってフランクフルトの看護学校で学び始めた。
第一次大戦後にアフリカでドイツ国籍のシュヴァイツァーが逮捕されたときには彼女も一緒だった。その時期に健康を害し、ケーニヒスフェルトに移るが、そこで日々療養に専念していたわけではなく、特にナチが政権を取ってからは米国に旅して夫の病院のための資金援助や医薬品供給の約束を取り付けている。また娘とパリにいた時期もあったがそこがナチに占領されるとユダヤ人迫害を逃れて南仏に移り、そこからポルトガルとアンゴラを経て再びランバレーネの夫のもとに赴いた。
第二次大戦終了後は娘とケーニヒスフェルトで穏やかに過ごすも、ドイツのサナトリウムでの療養で健康状態が改善されたこともあって、アルバートの度々の海外講演旅行にも同伴している。最後はチューリッヒの病院で亡くなり、その遺灰はランバレーネに運ばれた。夫に先立つこと8年、78年の生涯であった。
保谷硝子は…昔光学機器メーカーにいた時、そのメーカーがメガネのレンズに手を出したときその確かガラスの仕入れ先になっていたもんで…なんとなく気になっていただけです、同じ日に買った唇を強く当てると割れてしまいそうな薄い仕上げで…ステム?とのつなぎもわからない見事なワイングラスが2コあったので30円× 2 = 60円払ってゲットしました…ほんとに素敵なものはそこら辺に転がってます😀
死ぬとはモーツアルトを聞けなくなることだと言う名言で知られたシュバイツアーの裏が取れた心地がしますね、名声も名誉もお呼びじゃない、というか興味がない方だったんだろうか。まぁ僕には難しい事は分かりませんがオルガンが好きだったとうかがっただけでとても親しみがわきますね。子供の頃この人の名前を聞いたとき偉い人がいるもんだなぁと素直に感動できました。子供って不思議ですね偉い人がわかる。大人になった僕は空気を吹き込んで鳴らす楽器、風琴の連想から…同じ空気を吸う人間ならば、共通に着目して外は四捨五入する、何が大事で何が大事じゃないかはっきり見える人にはそれ以外は全てノイズだ。シュバイツアーを身近に感じるびすこさんも同じ土地で同じ空気を吸う、たったそれだけの符号の一致だけでシュバイツアーに興味があるわけではないでしょう…行動の人だからだと思います、そうするしか、行動するしかない自分を納得させる道がない人の歩みに興味がある人はその人もまたそういう人であると言うことだと思います。ずいぶん遠くまでいらして…
探し物は見つかりましたね、びすこさん😌僕は迷子のまま…これもまた迷子であってもいいと思う自分がいます。時々、わかっている人が気の毒になります。何が何だか分からずに生まれてきて何が何だかわからずに死んでいくそれでいいと思いました。
(この文章は実は昨日菊正の樽酒を図書館のリサイクルで買った50円の保谷硝子製のコップで冷やで飲んで、書いたもので何か失礼があってはいけないと思い載せなかったのですが、びすこさんの文をもう一度ちゃんと読み直してさて感想をと思っても…浅学の身、ままよ、このままが面白いと思い載せました、失礼があったらごめんなさい…)