コロナでスター誕生――ドイツの黒い森から 13(びすこ)
- クレマチス

- 2021年6月19日
- 読了時間: 10分
昨秋コロナでてんやわんやのドイツに戻ってすぐ、インターネットでクリスチャン・ドロ―ステン博士の人形が販売されているのをみて、お、可愛い、と思ったのだが、自分で買うつもりはなくジョークのように眺めただけだった。(写真 1)

ドロ―ステン博士は後述の「シャリテ」という欧州最大の医療・研究機関で働くウィルス学者である。欧州委員会の何とかパネル・アドバイザーでもあるらしい。コロナで俄然脚光を浴びるようになり(そういう人、日本にもいますね)、日本でドイツのニュースを見て顔は知っていた。まだお兄さんと言ってもいいような、どちらかというと童顔の 50 前の男性で、居丈高なところや偉そうな言動は全くない。くるくるカーリーヘアーがトレードマークだ(写真 2)。

そのあとたまたま事務所で人形の話をして笑っていたら、夫の秘書の女性が「それ買いませんか。注文しましょうよ」と言う。ええ~、と思ったが、一つには夫もそのドロ―ステン博士に好感をもち信頼していたのと、そしてこれが重要なのだが、その人形がドイツ東部ザクセン州のチェコとの国境に近いエルツ山地の村で作られているというので、「それならいっそ 5、6 個買おう」ということになった。
エルツ山地について説明すると、ここは昔、銀・銅・錫などの鉱山で栄えた地域だが、そのうち鉱脈が枯渇し衰退してしまった。しかしこの地の人は男女を問わずガッツがあって、未亡人になったある女性は意を決してベルギーに赴き、レース編みの技術を習ってそれを郷里の町に導入した。一方男たちは、おそらく鉱石の精錬などが減って燃料だった木材が余っているのに目をつけたのだろう(私の推察)、木工細工を始めた。
どちらも軌道に乗り、19 世紀には星や雪の結晶のレース編みも木製玩具も特にクリスマス飾りとして大人気を博すようになった。第二次大戦後の共産政権下でもその伝統は守られ、売るものなんかほとんどない東独で、エルツ山地ザイフェン村の産品は欧州の他の国にも輸出されるなど、外貨稼ぎに貢献した。
さて、2010 年頃に夫がたまたまザクセン州で倒産しかけた同業社から見に来てほしいとの依頼を受け、東独時代にはカール・マルクス市と呼ばれた現在のケムニッツに何度か出かけることになった。そのときホテルに飾られた人形とパンフを見て、仕事を早めに切り上げてきた夫がザイフェンに行こうという。(ザイフェンというのはドイツ語で石鹸のことなので、どうして石鹸を見るの、とアホなことを尋ねた私であった。)
ザイフェンは同州内のケムニッツからも結構遠く、公共交通機関などまったくない。車であちこち迷って漸く着いたところは確かに「村」で、有名な鉱山夫の人形のでっかい模型が立っていたり、クリスマス時に窓辺に置く大きなキャンドルスタンドの店があったりで、木工品製作を生業としていることは分かったが、季節もあり特に賑わっているわけではない。
ところが、小腹が空いたのでお茶をしようと入った喫茶店(カフェなどという洒落たものじゃない)で、入口近くにあった来客のサイン帳を面白半分に覗いて驚いた。ほとんどが日本語なのである。それも「この有名なザイフェンに来られて幸せ」とか「交通の便が悪くて苦労したけれど(←そうだろうとも)来てよかった」などと書かれている。喫茶店の女将さんに訊くと、そうですよ、日本の方はとても多いんですよ、とくにクリスマスが近づくとね、とのことであった。日本にはいろんな分野で趣味・趣向を世界的に追求する人がいるとは聞いていたが、ほー、こんな伝統玩具の世界まで。
子供の頃からそれらクリスマスグッズを知っている(でも貧乏で買えなかった)夫は、そのあと入ったかなり大きな店で熱意溢れる優秀な女性販売員と出会い、例の如く惚れこんでこの地の産品を買いあさり始めた。何年間かは定期的に訪れていたが、そのうち関係していた同業社がつぶれケムニッツから足が遠のくと、その女性と電話で話してカタログの品を次々取り寄せる。
我が家にあるエルツ山地の工芸品はしまう場所もないほどで私はお手上げだが、ときどきこっそり、それもごっそり、日本に持ち帰りいろんな人にお土産としてあげている。(夫は気づかない。)
それでドロ―ステン博士の人形も、その人形自体がどうのこうのという前に、それがザイフェンで作られているという事実が気にいったわけである。
この人形を思いついて制作し始めたギュンター工房というのは彼も知らなかったが、思い込みの激しい人だから「エルツ山地ザイフェン村のギュンターさん」というだけでファンになったのだ。
さて、12 月初めに注文すると、納入は 2 月になります、という。クリスマスには間に合わないけど別にいいんじゃない、と承知した。ところが 2月になって、納入は秋まで無理かも、などという。ドイツ中でこの人形に関心を持つ人が急増し、大量注文に対処しきれなくなったらしい。全部手作りで、助手といっても急遽雇った新米数人だから、無理もない。
しかし実際には今月になって届いた。ワクチン接種が広がってコロナの話題が徐々に後退しそうなので、今のうちに早くたくさん作って売ろうというマーケティング戦略か。
この人形を作るにあたって、ギュンターさんはエルツ山地の伝統である「煙を吐く鉱山夫」をモデルとした。これらの鉱山夫はパイプを手にしている。そして丸く開けた口から煙が出る。その仕掛けは、胴体と下肢をスポッと外すと中に円錐形の線香のようなものを置く台があり、火をつければ煙が上体の管を昇って口から出る、という次第である。
ところがドロ―ステン博士はマスクをしている。(マスクなんぞと馬鹿にしていた欧州で、彼は当初から強力なマスク推奨者だった。)それでギュンターさんは、頭のてっぺんに穴を開けてそこから煙が出るようにした。燻蒸の煙? 仮にマスクしてなくても医学博士がパイプを吸うなど言語道断だから、窮余の策が名案になったわけだ。
頭から煙を出すドロ―ステン博士を見つめるギュンターさん、手塩にかけたわが子を慈しむ父親の眼差しである(写真 3)。上の全身像に見られる通り、足元にはコロナウィルスがあって、博士がそれを踏みつけている。

実はコロナ禍のドイツには、ドロ―ステン博士以外にも医学畑で活躍しメディアでの露出度の高い人は何人かいる。弁の立つ政治家もいて、夫も私も社会民主党員のこの人を嫌いだったが、疫病・公衆衛生が専門とあって言うことは至極まともなのでコロナで見直した。
もう一人有名なのは、ロベルト・コッホ研究所(RKI)の所長ロタール・ヴィーラー氏で、彼は微生物学者であり「人獣共通感染症」の専門家としても知られる。RKI はドイツ連邦保健省の管轄下にあるので、政府の公式発表の席には保健大臣やメルケル首相と同席する。日本でいうと、尾身茂氏のような感じ。
しかしこの人はただもう堅そうで、仕事がら正確と簡潔を期しているのがとっつきにくく可愛げもないので(任務には必要ないが)、彼をモデルに人形を作ろうという人は現れないだろう。
さてそれでドロ―ステン博士の職場「シャリテ」であるが、これについては実は一昨年に「ひょこむ」に投稿したブログがあるので、その抜粋をコピーする。何の反応もなかったブログだが、自身のためにやはり記録しておくものですね。
『数年前、夫が共同研究の支援をしている大学があるドイツ北部のクラウスタールでロベルト・コッホの生家を見て、コッホとその愛弟子だった北里柴三郎に興味をもった。
その延長で当時世界の最高水準にあったドイツ医学界について少し調べると、1901 年の第一回ノーベル医学賞以降多くの受賞者を出したこの国で、19 世紀末から少なからぬ日本人が学んでいたこと、そして彼らの師である医学者の受賞にこれら日本人が深く関与していることが分かり、そのことがもっと広く認められてしかるべきだと思った。
この件を忘れかけていた今年の早春 (2019 年 3 月)、やはり北ドイツに夫の出張に付いていったとき、宿泊のホテルで「シャリテ」という三部作の長いドラマを見た。
ドラマの舞台はベルリン大学の病院「シャリテ」で主人公は若い看護婦。向学心に燃え強い意志をもつこの女性が研究者に恋心を抱いたり、男性のみに許されている講義を聴こうと階段教室の階段下に隠れていて追い出されたり、という「女性の社会進出」のキャンペーン的な側面もあるのだが、何しろ世界に名をはせた医療・研究機関が舞台とあって実在した著名な医学者が次々登場し、それだけで十分に刺激的であった。
物語は 1888 年に始まる。当時の医学界の権威といえばもちろんロベルト・コッホ。ついでジフテリアの血清療法で第一回ノーベル医学賞を受賞したエミール・フォン・ベーリング。
コッホより一回り若いベーリングは後にベーリング社を創設し、その企業は今もフランクフルトの近くに本社を構えて優れた実績を上げている。
ベーリングの先輩のコッホが結核菌の発見でノーベル賞を受賞したのは、なぜかその発見から 23 年を経た 1905 年のことだった。ベーリングの方が早く受賞し、しかも後日企業家として大きな成功を納めたのは、このドラマにも出てくるが権門の令嬢を妻に選んだことも影響しているのだろう。
研究者の成功条件の 4 Gのうち Glück(幸運)をまず確保したといえる。
もう一人研究に励む有能な学者がいて、その名をパウル・エールリッヒという。ベーリングと同い年の彼は同僚に 7 年遅れてノーベル賞を受賞するが、彼の方は幸運に恵まれていたとは言えない。第一にユダヤ人だったからで、ドラマの中でも学生たちが彼を見て「汚いユダヤ野郎」と罵る場面がある。
綺羅星のごとき学者が出入りする広い研究室は歴史と伝統の色が深いが、実験装置が所狭しと並び動物までいるから猥雑な印象もある。
ジフテリアの治療に使う血清には馬が必要なので、なんとそれが研究室で飼われている。
その中で私の目にとまったのは、漆黒の髪にやや濃い肌の色をした痩躯の男性で、どう見ても東洋人、ということは当時の国際状況からして日本人らしい。
彼は常に上記の医師たちの後ろに影のようにいて、台詞は一言もなく顔がアップされることもないのだが、よく姿を見かけるので気になったのだ。
これはもしや北里柴三郎ではないか、と思った。北里は 1885 年にドイツに留学しベルリンで学んで 1892 年に帰国しているので、まさにこのドラマが描いた時期と一致する。
最初ちょっと疑いをもったのは、その感じが写真で知っている北里とは違ったからで、風貌でいうとむしろ秦佐八郎を思わせた。しかし秦は 1873 年生まれなので、このドラマの時期にはまだ 10 代でドイツにはいなかった。(後年、上述のエーリッヒと共同で梅毒の治療法を開発している。)
やはり影のごとき東洋人は北里柴三郎だったのだろう。この日本人が果たした役割は現在のドイツ医学界でも知られており、「シャリテ」での存在を無視することはできなかったが、そこで日本人をドラマに含めると話が込み入って焦点がぼやけるため、ドイツ人学者の背後霊のような扱いになったのではないか。』
ということで、このドラマを機に、20 世紀初めに数々のドイツ人ノーベル賞受賞者を支えた明治の日本人医学者の業績を知ったのですが、その詳細は省略。
ついでにこの「シャリテ (Charité)」、慈善という意味であるが、その前身はかのプロイセン王国のフリードリッヒ一世が 18 世紀初めに設立した「ペスト・ハウス」、すなわち伝染病の施療院であったことを付記しておく。
最後にわが家にやってきたドロ―ステン博士をお見せしよう。ほら、ちゃんとあるでしょ、ということで傍らに日本語の本を置いた。医学書はうちにはないので、それっぽい「免疫の意味論」(写真 4)。この本によると、「シャリテ」出身のエーリッヒは免疫現象の研究でノーベル賞を受賞したそうな。一応読み通しましたが「分からないところがあった」ではなく、「分かるところも(ぽつぽつ)あった」という書物でした。


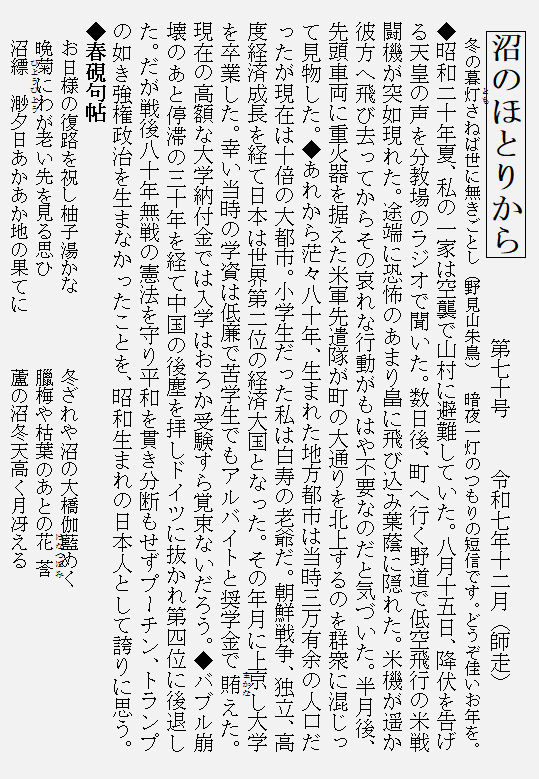


あはは🤣鉱山人形のハンマーのバッテンが日本の文字の父に見えますね、その隣のくるみ割り人形はこのままバッキンガムに立っててもいいですね、人形たちを見ただけで、なかなかいいところだなーていうのがわかります^_^
へぇーずいぶん密度の濃いお話ですね今回も!木工の民芸品は楽しいですよね。ちっちゃな細工小鳥を回すと小鳥が鳴いてるような音がするヨーロッパの民芸品がありました、ほんとによくできていて手元に置いておいても邪魔じゃないのでお土産にはもってこいだなぁと思いました。 頭から煙を出すお人形を笑えますね。お茶目なお人形を見る人、いい顔してますね。人形のほうのドローステン博士の目、生きてますね!ちょっとほっとできるものに囲まれているととてもほっとできますね。自分なりの物語をつけて楽しむのが僕の癖です。今回も盛りだくさんの話題をありがとうございました時々また拝見しますね、多田さんの免疫学の本読んだけど全部忘れちゃいました、早くも認知症予備軍です^_^