それぞれのケーニヒスベルク――ドイツの黒い森から 40(びすこ)
- クレマチス

- 2022年6月29日
- 読了時間: 14分
ケーニヒスベルクというのは、最近ロシアのウクライナ侵攻に反発してリトアニアがそこへの物資輸送を阻止したカリーニングラードのことである。またカリーニングラードというのは都市の名称であると同時に、その町のある州全体をも意味し、このカリーニングラード州の方はかつて東プロイセンと呼ばれていた。そして現在リトアニアがとうせんぼうしているのはカリーニングラード市を含む州全体で、ここは複雑な経緯からポーランドとリトアニアに挟まれたロシアの飛び地になっている(地図を参照)。

州というより嘗ては一つの領地を意味した「東プロイセン」という名前が消えたことにドイツ人はさほどの未練は見せない一方で、ケーニヒスベルクの町をカリーニングラードと呼び変えることにはっきり抵抗する人は戦前・戦中派を中心にまだかなり存在し、1940 年生まれのわが夫もその一人である。
戦前のドイツを知る人は今では少数派であるが、その世代を親とする現在の高齢者たちにとってもケーニヒスベルクというのは特別な響きを持っているらしい。一言でいえば、失われた故郷へのノスタルギーである。したがって私もカリーニングラードという名称は極力使わないようにしているが、夫に言わせると、ロシアに奪われたことが忌々しいだけでなく、よりによってその町にカリーニンという殺人鬼の名前をつけたことが許せないのだそうだ。
ウィキその他を調べると、カリーニンは同時代のスターリンと比べられるせいか相対的に穏やかな人物であるように書かれているが、実際は第二次大戦中に 4400 余人のポーランド人将校を惨殺した「カチンの森事件」にも関与しており、その手は血にまみれている。ドイツ語でいうゼーンズフト(憧憬)の対象であるケーニヒスベルクが、そんな悪漢の名で呼ばれるのは耐えがたいというわけである。
ケーニヒスベルクの歴史は長く複雑で、古くは 13 世紀の東方植民の時期にまで遡る必要があり、その植民と開拓に活躍したドイツ騎士団というのもえらくややこしい集団なので、あっさり数世紀を飛ばして、このバルト海沿岸の地域がプロイセン王国の領土となった 1700年から話を始めたい。
その前に、東方植民について少しだけ。この言葉から世間の人は、ドイツ人が東の方に勝手にずんずん侵攻し原住民を蹴散らして領地を奪ったかのような印象を受けるかもしれないが、当時はドイツという国はなく、もちろんポーランドやバルト三国なんていうのも存在しなかった。東には地味(ちみ)の良い広大な土地があって、現代では穀倉地帯とされるそのあたりには、当時は何人とも何族とも言い難い古くからの領主・豪族がいたが、人口は少なく、やる気満々の精力的な民というのはさらに少なかったので、領主たちは西方の、現在のドイツに当たる地に住んでいる人々に「こっちに来て開拓してくれませんか。土地はあげますから」と声をかけたのだった。
そういう活動にかけてはゲルマン人というのはスラブ系よりも積極的というか、欲深いというか、体力的にも勝っていたのであろう、当時の風潮に鑑み一応キリスト教騎士団という宗教的な衣を被って東へ東へと進んでいったわけで、盗賊集団だったわけでもなさそうである。これはドイツ人の妻として身贔屓でいうのではない。
さて、ではなぜ 18 世紀から話を始めるかというと、ウィキ(「プロイセン王国」の項) にもあるように1701年、ブランデンブルク選帝侯・プロイセン公フリードリヒ 3 世は神聖ローマ帝国の外にあたるケーニヒスベルクで王に即位、フリードリッヒ一世となりプロイセン王国がこの街で誕生したためである。(このブランデンブルク選帝侯の姓はホーエンツォラーンで、わがブログ 「ウニモクの雄姿――ドイツの黒い森から11 」で紹介したドイツ南西部の「天空の城」の主はその分家に当たる。)
このプロイセン王国は代々栄えて最後はドイツ帝国となるのだが、経済的・軍事的な繁栄とならんで特に東プロイセンでは学術文化の花が開き、その象徴となったのがケーニヒスベルク大学であった(写真 1 )。

そしてケーニヒスベルク大学とくれば、イマヌエル・カント(1724-1804)の名を挙げないわけにはいかない。カントを生んだことこそ、数知れない学者・研究者を輩出したこの町の金字塔と言うべきであろう。ということは分かるのだが、カントの哲学となると私などに歯が立つようなシロモノじゃない。純粋理性批判とか実践理性批判とか、題名を聞いただけでもう「堪忍しておくれやす」と言いたくなる。
その著書の中に「永遠の平和について」というのがあり、これは赤十字創設者アンリ・デュナンやシュバイツアーについて書かれた偉人伝みたいなのを読んでいるとよく出てきて、要するに平和を守るには個人の良心や善意に頼るだけでは不十分として、後の国連の原型を考えたのがカントなのだそうだ。わりと具体的な話だから、これなら私でも読めるかと苦労して手に入れたものの、古い本で印刷が不明瞭な上に恐ろしく難しいドイツ語で( 18 世紀の言葉だし)1 ページ読むのに半日かかる有様だったのであえなく放棄した。
従って私にはケーニヒスベルクの大偉人(本人は小柄で青白い男だったそうな)ともいうべきカントについて語る資格も能力もないのだが、この哲学者について書かれた日本語の本はたくさんあるから関心のある方はそちらを参考にしていただきたい。
その思想は別として、私がこの人物に一つだけ親しみを覚えるとすれば、彼が生涯を通じてほとんどこのケーニヒスベルクの町を出ることがなく、旅も好まなかったという点である。人間の身体的・物理的活動の範囲や頻度は精神の活発さとはほとんど関係がない、というのが無精な私の自己弁護を兼ねた持論で、世界の 20 カ国に住んだとか 40 か国を歩いたとか自慢する御仁の狭量・偏見をたっぷり見て来たせいもあり、カントの「出嫌い」の性格を知ったときは「ほらね!」と叫びたい気がした。
カントに続くケーニヒスベルク出身の有名人はたくさんいるらしいが、ここでまたもや 2 世紀ほど飛ばして、次は 1909 年生まれの女傑・才女について語ろう。
その名はマリオン・グレーフィン・フォン・デーンホフといい、長たらしいがグレーフィンはグラーフの女性形で女伯爵という意味、フォンは貴族の姓に付けられる前置詞である。その名の通り、東プロイセンのケーニヒスベルク郊外に広がる壮大な敷地の貴族の館に誕生したマリオンは、その自伝を読む限りでは家族・親族よりもこの生誕地の方に、つまり「血」よりも「土」の方に、強い愛着を抱き続けていたらしい。貴族の娘らしく、幼いときからその領地で馬を乗り回して過ごしたという。
この女性のことを私はまるで知らなかったのだが、旅先の本屋で彼女の〈私にとって重要なこと〉と題する本を店頭に見た夫がしばらくめくっていて、当時ドイツ語の初心者だった私に「この著者は立派な人物だし、書かれているドイツ語も全然難しくないから読むといいよ」と買ってくれたのだった(写真 2 )。今思うと、それはデーンホフ女伯爵の死去(2002 年)からほんの数年後だったからその名が夫の目に留まったのだろうが、彼女の生涯を知るにつれて夫の推奨を訝しく思うようになった。

彼女は「赤い伯爵」と呼ばれたほど革新的な思想の持ち主で最初は共産主義に傾倒し、後に社会主義者となって、現在も左派の新聞として知られているディ・ツァイトを立ち上げた。終戦直後の 1946 年初めのことである。零細とはいえ一応は事業の主であるわが亭主がそういう人物を称賛することに驚いたのだったが、彼に言わせると戦後まもなくの社会主義者、現在のSPD(社会民主党)の当時のメンバーたちは今とは比べ物にならないほど優秀で、自分の理想と党の原点に忠実な人間が多かったそうだ。
東プロシアやその周辺のプロイセン王国の領土は、第二次大戦中に反ナチの運動家を数多く生んでいる。そしてその大部分が貴族や学者の子息で権門の出自である。有名なのはヘルムート・ジェイムス・モルトケで、彼は普墺・普仏戦争でドイツ帝国を勝利に導いたモルトケ将軍(東郷元帥のドイツ版か)の家系に連なる教養人で、ナチスを批判し抵抗した廉で終戦の 3 か月前に絞首刑に処された。
モルトケのグループとは別に、ヒットラー暗殺を計画した同じく貴族や将校、著名人の集まりがあって、この計画は失敗に終わり首謀者のシュタウフェンベルク伯爵以下軍人は銃殺されるが、マリオン・フォン・デーンホフはこの企ての裏方を務めておりそれがゲシュタポにばれて逮捕され、一旦保釈されるものの差し迫る身の危険を感じたマリオンは、自分の愛馬を駆って東プロイセンからハンブルクへと逃れた。真冬の北ドイツの 2000 キロを 1 週間近く走り続けたというエピソードは、日本なら大河ドラマにでもなりそうな物語である。
東方政策を推進したブラントとも親交があったが、ディ・ツァイトの編集に共に関わったヘルムート・シュミットとは特に肝胆相照らす仲だった。一方、ブラント以下の親露路線を拒絶し、スターリンと組んで新生ドイツをという社民党の案を撥ねつけたアデナウアーに対しては非常に厳しい批判を浴びせているが、これについてはマリオンの姿勢の方に疑問を感じる。今日までのきわめて危うい独露関係とそれを取り巻く国際環境を見れば、スターリンを拒否したアデナウアーの方に理があると言わざるを得ない。
彼女の発言を聞くに、その親ロシア心情はどうも勝利者の連合国側(米・英・仏)への遺恨に源があるように思われる。シュタウフェンベルク伯爵のヒトラー暗殺計画に関与して上記のモルトケの後に処刑されたルター派牧師ボンヘッファーの伝記などによると、プロイセンの首都ベルリンから東プロイセン、さらには現在ポーランドの領地であるシュレージエン地方で反ナチ運動を起こした知識人たちは幾度も英米に支援を要請したが、ナチによるドイツの自滅を望むこれらの国々の政府は一様に手を貸すことを拒んだという。(抗ナチ運動に関わったドイツ人のほとんどが 1945 年の最初の数か月に処刑されているのは、敗戦を不可避と見たナチスが証拠隠滅と復讐を兼ねてその死刑執行を急いだためだった。)
上記の著書の中の「プロイセンの欧州的次元」と題した章でマリオン・デーンホフは、連合国がプロイセンを軍国主義と反動の担い手と見なして消滅させたことに関し、次のように記している。
「戦勝国側のこの一致了解は、一部にはドイツが引き起こした両次大戦への怒りによるのかもしれない。しかし今なお繰り返される主張、すなわちルターからフリードリッヒ大王、ビスマルクを経てヒトラーに至るまで一直線で結ばれている、という見方は、歴史の完全な無理解を示すものである。」
この文章に私がドキリとしたのは、その前に読んだ日本人の阿部謹也という西洋史学者の「物語 ドイツの歴史」に同じことが書かれていたからだった。阿部氏はトーマス・マンがルターに見たという反ヨーロッパ的なものへの嫌悪・不安感に同調するかのように、「このようなルターの評価は、一種のドイツ史批判として、今でも続けられている。ルター、ビスマルク、ヒトラーがドイツ史の基本路線だという評価である」と述べている。(阿部謹也はカトリック教徒で、中学時代に経験した修道院の生活に大きな影響を受け、著書の中でも修道士の生き方を礼讃している。いわば日本におけるアンチ・ルターの先鋒と言えよう。)
その見方に対し、マリオン・フォン・デーンホフは「連合国はヒトラーによるプロイセンの倒錯を(ドイツ)独特のものと捉え、彼ら自身が、多くのドイツ人同様にこのオーストリア人のペテン師* の尻馬に乗ったことに気づかずにいる」と激しい口吻で反駁している。冷静沈着で知られる彼女が、故郷の東プロイセンを擁護し彼(か)の地への郷愁を語るときの口調は、まさに声涙ともに下るという印象である。(*ヒトラーを指す)
実を言うと、マリオン・フォン・デーンホフの著書の中で最も私の印象に残っているのは、笑われそうな、本人も多分ついでに記したようなエピソードだ。女学校を出た彼女は西のフランクフルトの大学で学ぶことを望んだが、プロイセン帝室の女官でもあった旧弊の権化のような母親は、そう簡単に娘の要望を拒否できないことを見てとって、その前にまずスイスの花嫁学校で学んだら大学進学を許してもよい、と言った。(かのダイアナ妃もここの卒業生である。)母親としては、世界各国の貴族令嬢が集まるこの学校で 1, 2 年過ごせば学問への意欲など消え失せると期待したのだろう。
マリオンは言われるままに花嫁学校を卒業し、それからフランクフルト大学に進む。戦前の女子としては破格であった。そして彼女はそれ以降、料理というものを一切拒み台所に立ったことは一度もなかったそうである。花嫁学校で過ごした無為の日々は、彼女にとって悪夢だったのだろう。
長くなったのでマリオン・グレーフィン・フォン・デーンホフの話はこれまでにして、次にこの伯爵令嬢とは対象的なケーニヒスベルク出身のもう一人の女性を紹介したい。是非、彼女について知ってほしいと思う。
このケーテ・コルヴィッツという画家と出会ったのは全くの偶然であった。
私は森鴎外の矛盾だらけの女性観に興味があり、また矛盾してはいないが共感を覚えにくい漱石の創った女性たちにも関心があって、その点について書いた物はないかとインターネットを探していた時、宮本百合子の「歴史の落穂――鴎外・漱石・荷風の婦人観にふれて」というエッセイに出くわした。文豪たちの女性観はこのブログの趣旨から外れるのでそれは措いて、私が意外に思ったのは、共産党員の宮本顕治の妻でプロレタリア作家として知られる女流作家が、鴎外の愛娘たちに向ける優しいまなざしであった。
宮本百合子への自分の先入観をいささか恥じて、他にも何か面白い作品はないかと見ていくと(何しろ青空文庫には1200ほどが納められているのでそう簡単ではない)、 「ケーテ・コルヴィッツの画業」という題があった。明らかにドイツ人女性の話である。
すぐに読んで、一言でいうと、感動した。こんな人物が現代のドイツでほとんど話題にならないことを不思議に思い、夫にケーテ・コルヴィッツを知っているかと尋ねたら、「もちろん知っているよ」と言って即座に彫刻を含む作品を 3 つ 4 つ挙げたのにはびっくりした。こう言っては何だが、わが亭主ときたら普段は芸術などとはトンと縁のない現実一辺倒の人なので、その彼が知っているということはよほど有名なのだと悟り、要するに私が無知だっただけなのだとまたもや反省した。
上にあげた「ケーテ・コルヴィッツの画業」において知るべきことはほとんど網羅されているのだが、それを読んで下さい、ではあまりに芸がないからごく簡単にこの女性を紹介すると、ケーテは 1867 年にケーニヒスベルクの左官屋カール・シュミットの娘として生まれた。そもそもドイツでは本来職人の地位というのは決して低くはなく(カントの父親も馬具職人だった)、また左官というのも日本人がイメージするような鏝で漆喰をペタペタ縫っていくという作業以上に、石や粘土で壁を造り煉瓦を組み立てて家を築く極めて需要の高い専門職で、ケーテの父親はその親方として「なかなか大規模な生活を営んでいた」そうである。
加えてこのカールは苦学して大学を卒業し、その前途には官僚の道が開かれていたのだが、プロイセン王国/ドイツ帝国の最後の君主として悪名高いウィルヘルム二世に官吏として仕えることを潔しとせず、もとの左官業に戻る。
このことから分かるように父親は知性と気概にあふれる人物で、その堅固な思想と近代的な教育方針がケーテに与えた影響は計り知れない。さらに同じケーテという名の母親も、その父親(画家ケーテの祖父)のユリウスの優れた資質を受け継いでおり、家族というならマリオン伯爵令嬢などよりもよほど恵まれていたといえる。さらに生涯独身を貫いたマリオンと異なり、ケーテは貧しい港湾労働者の治療に当たる医師と結婚して共に労働者街に住み、そこの人々を観察し描き彫像として刻むことに情熱を燃やした。
その作品に関しては上述の優れた資料があるのでここで私が触れる必要もないと思うが、ケーテ・コルヴィッツのモノクロの絵を見ていて連想したのは、農夫や特に織工を描いたゴッホの作品群であった。19 世紀にシュレージエン地方で起きて悲劇に終わった織匠たちの蜂起を描いたケーテの絵画からは、貧しい人々への並外れた共感によって精神異常ともされたゴッホを思わせる大波のような慟哭が感じられる(写真 3 )。
大戦中にはナチ党員となることを拒否し、ヒトラーも国民から寄せられる彼女への支持と圧倒的な人気を考慮して拘束することこそなかったものの、ケーテは創作活動を禁じられたままドイツ降伏の 16 日前に世を去った。77年(と 9 カ月)の生涯だった。
昔日のケーニヒスベルクの水と土と空気に磨かれた宝石について語ろうと思った契機が、ロシアによるウクライナ侵攻に端を発するリトアニアの、ということは欧州連合の、カリーニングラードへの強硬措置によって与えられたことを私はどのように捉えたらいいのだろう。


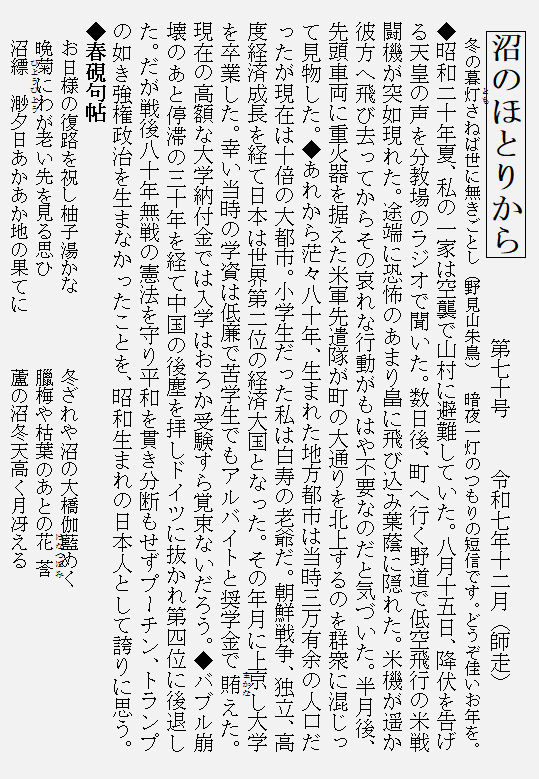


コメントで赤レンガの話をして下さったので、ちょうどよかった、私からは青瓦について。
もう40年ほど昔のことですが、仕事で知り合った年配のフランス人(もちろん二人の会話は英語)が私に、「日本人はどうしてプルシアンブルーの屋根が好きなの」と訊くのです。よく見かける青い屋根のこととすぐ分かったのですが、「プルシアンブルーって?」と尋ね返すと、プルシアンというのはドイツのプロイセンのことだと教えてくれました。へえ、あの青はプロイセンの青っていうんだ、とその時知りました。
それから少したって、来日したアメリカ人のグループが「俺たちもああいう青い屋根の家がほしいね、瓦は輸出されているのかな」と話しているのを耳にしました。カリフォルニアの人達だったから、そこなら似合うかもしれません。アメリカ人は一般に一般教養がないから、その青がプロイセンの青だなんて知らず、そもそもプロイセン(英語でプルシア)という言葉も聞いたことがないでしょう。(これには確信があります。)
ずっと後になって、ではこのプルシアンブルーというのはドイツ語から来ているのだろうかと調べたら、ドイツでは「ベルリンのブルー」と呼ぶとのことで、確かにベルリンはプロイセンの首都でしたけど、どうしてこんな名前になったのかといえば、1704年にベルリンの顔料製造者が偶然発見したからですって。
ウィキの英語版を見ると、その例として葛飾北斎の富嶽三十六景中の「神奈川沖浪裏」が紹介されていました。
今寝床で、図書館の電子書籍で宮本百合子の当の本を読んでみました。むくむくと起き上がり椅子に座って読みました。取り上げずにはいられなかった情熱が伝わって参ります。図書館に2冊ほどケーテ・コルヴィッツに関する最近の著作頼みました…機会を与えて下さってありがとうございます。びすこさん。 彼女のおじいさん(ループ祖父さん)の雄勁な気魄(※宮本百合子いうところの、、)とともに伝えられた、才能は一つの義務である、、その義務を、実践しきった生涯だったのだとわかります。 (職人の系譜を持つ彼女の環境から…の連想から 葛飾区の小菅刑務所がかつて東京駅の赤レンガ街の赤レンガの製造所だったことを最近知り、その働き手たちは囚人でもあり、明治維新の敗残者たちであり、安価な労働力であったことを知ったことを蛇足と知りつつ付け加えます😅)