すると光があった――ドイツの黒い森から 56(びすこ)
- クレマチス

- 2023年10月1日
- 読了時間: 16分
今回の話もきっかけは新聞記事だった。こちらはスイスで見たドイツの新聞の記事である。
もう 4 か月近く前になるが、日本からドイツに戻って最初の土曜日に夫とチューリッヒに出かけた。デュッセルドルフで 6 月半ばに 4 年に一度の業界メッセが開かれることになっており、それを観に来た日本人 30 人余りのグループがついでに夫の会社を見学したいということで、私たちは訪問者に渡すちょっとした記念の品のことを年初から検討していた。
メッセの都度見学者があってシュヴァルツヴァルトの産品はほとんど試しつくしたし、さてどうしたものかと話していたら大まかな予定を記したメールが来て、その日本人グループはここを見学したその足でチューリッヒに向かい、そこで一泊して翌日チューリッヒ空港から日本に発つという。ついてはその夜のパーティに私たちも出席してほしいとのことだった。
話を聞くとスケジュールはかなり慌ただしくて、みんなゆっくりお土産を探す時間もなさそうなので、私がいっそスイスの小物をプレゼントしてはどうかと提案し、あれこれ探して候補に挙がった品は木製の牛の置物だった。ウシ!? ときょとんとされるかもしれないが、これは歴としたスイスのシンボルで、例えば空港でパスポート検査と荷物のチェックを済ませて搭乗口まではるばる歩いていると「ムゥオー」という牛の鳴き声とカウベルの音が聞こえる。日本だとお琴の調べが流れるところを、スイスの空港では牛の声と首に下げたベルの音で旅人を送り迎えするというわけである。
乳牛の白黒の代わりに斑の部分をピンクや赤で塗った牛をインターネットで見つけ、なかなか可愛いじゃないかと注文することにしたのだが、初春にスイスの山奥のメーカーに問い合わせると 40 個だか 50 個だかをそっちから取りに来て贈り物用の包装は自分でして下さいという。気が利かないというか、そっけないというか。
それでふと思いついて、社員と一緒にチューリッヒの中心にある地場産市場のようなところに行ってみた。店頭には私が目星をつけた牛の置物があり、販売員に尋ねると、特に急ぐのでなければ 40 でも 50 でも包装して送ります、と言う。それが 3 月初旬のことでメッセまでまだ 3 カ月もあったから、「では宜しくお願いします、準備ができ次第請求書を会社に送って下さい」と頼んで帰宅した。
何かを依頼して受諾され、それがきちんと実行される、という日本では当たり前のことが決して普通ではなくなった今の欧州において、唯一日本人に近い信頼が置けるのがスイス人である。(だからスイスは EU の仲間入りをしないのかもしれない。)だがそれでも 100 %確実ではないと夫は言い、私が日本から戻るのを待ってチューリッヒに行き確認することになった。
店ではしっかり覚えてくれていて、包装もしてあるので何なら今日お持ち帰りになれます、とのことだった。しかし日本人グループがスイスに来て一泊する際にそれを渡すと聞いた店員たちは、それなら今日ドイツに運んで 10 日後にまたスイスに持って来るのはバカバカしいから、パーティの席に届けてあげましょうと言う。この辺は日本人も及ばない配慮である。
すっかり気をよくした夫と私は、小腹が空いたので近くに推薦できるカフェはありませんかと尋ねてみた。世界最高の物価を誇る(?)この町では金さえ出せば何でも手に入るが、軽食や喫茶となると今風の若者用だったりえらく古ぼけていたり、家族がワンサと来てうるさかったりで、それまでずっとイマイチのところばかりだった。
店員さんは、それなら店の前の細い道をチューリッヒ湖の方向に歩いて行くと川べりに「シュトルヘン」というホテルがあって、そこの食事がお勧めだと言う。初めてなのでちょっと道のりを長く感じたが、確かに川辺に由緒ありげで瀟洒なホテルが立っており(後で調べると町でも有数の高級ホテルだった)、その前庭のプラタナスの木陰に並べられたテーブルは全部ふさがっている。屋内にもカフェがあるというので中に入っていった。最高級ホテルであるにもかかわらずウェイターは親切で、多くがアジア系のせいか慇懃無礼という印象はない。
これまたクラシックな印象のカフェでテーブルに就いて、新聞はないかと探すと、カウンターの横にドイツの新聞が掛かっている。中道保守で知られるフランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング(FAZ)である。家ではスイスの新チューリッヒ新聞を購読し、フランクフルトに本社を構えるドイツの新聞をスイスに来て読むというのもおかしな話だが、以前に購読していた FAZ を NZZ に切り替えた経緯は長くなるのでここでは省略。簡単にいうと、メルケルのキリスト教民主同盟から支援を受けている FAZ が、特に政治欄に関しては同党の御用新聞のようになってしまったのが原因である。しかし学芸欄などは今でも質が高い。
新聞をテーブルに持って来て、経済欄と、私が最も興味のない金融欄とを夫に渡し、残りを開いてすぐ目に留まったのが何と日本の、それも明治・大正の時代と思しき頃の子供たちの写真であった。一体なんの記事かとびっくりして読んでいくと、それは現在の先進国が一様に抱えている少子化問題についてで、欧州各国もだが東アジアの韓国や日本においても出生率が下がって政府は頭を抱えているという話だった。内容そのものに新鮮味はないのだが、そういう記事にどうして昔の(写真の注によると 1910 年頃の)日本の子供が登場するのだろう。それも坊主頭の、当時はおそらく日本のどこでもいたような童が新聞を広げ、それを遊び仲間の男児・女児が取り囲んでいる光景である(写真 1 )。

記事の内容はそっちのけで私はこの写真に興味を奪われ、帰宅してインターネットを探したところ、さほど苦労せずに同じ写真が数枚見つかった。彩色してあるのは不自然な感じなので無視し、少し小さめだが下にはっきりと当時のキャプションのある写真に注目すると、英語で The Mikado's Loyal Subjects–Reading the War News とある。「帝(天皇)の忠実な臣下たちが戦争の記事を読んでいる」という皮肉っぽい説明である。1910 年と言えば日露戦争は終わり、第一次世界大戦の火種が現れ始めた時期で、ただし日本は大戦には参加していないはずだが、日露戦争後の中国大陸の利権をめぐって欧米の列強との摩擦が生じ始めていたのだろう。おそらくそれで、アメリカ人が日本で撮った写真にこんな嫌味な解説が加えられたのではないか。
日本やアジアに対するこの程度の嘲笑や誹謗は当時の世界では珍しくもなかったろうし、今さら差別の蔑視のと騒いでも仕方ないからそれはさておいて、一方で私が衝撃を受けた、年端の行かないちびっこたちが新聞を読む、という光景に何の言及もないのがかえって面白いと思った。FAZ が 100 年以上を経て新聞記事にこの写真を用いたのは、記者たちの間に私のそれと似たような驚きがあったからだろう。
1910 年当時には学校制度、それも義務教育制度がすでに国民の間に根を下ろしていたとみえる。明治維新後まもなく学制の必要性が説かれ、尋常小学校の授業料無償化で義務教育が本格的にスタートしたのは 1890 年だという。何かを始めようとしても当初はあれこれと手間取り、すぐにテキパキと手を付けることのない日本人の性癖にもかかわらず、基礎教育の必要性については政府にも早くから認識があったらしい。これが決して当たり前のことではないのは、欧米に比べてあらゆる点で遅れていた世界の他の国々の 19~20 世紀の状況を見れば明らかである。
それにしても思うのは識字率向上の速さで、これは政策の成功というより日本人の本来の資質によるところが大きいのではないかというのが私の勝手な説である。江戸時代に既に寺子屋があって、一部の女子ですら読み書き算盤程度ならこなせたというから、社会体制が大きく変わった時、教育文化面ではそれにスムーズに移行する下地はあったように思われる。特に「読むこと・書くこと」への関心は、日本人の間では千年以上も前から世界の民族の中で突出して高かったのではないか。
日本に 5 世紀か 6 世紀に漢字が導入されてからの文字の発達は目覚ましく、それまでの無文字の社会とはうってかわった時代が始まったわけだが、よく言われるように文字の本来の機能は統治に関する記録で、メソポタミアでもエジプトでも紀元前 4000 年から 3000 年頃に文字が誕生したのは国家というものの成立と軌を一にする。その時から人類の歴史は「有史時代」に入り、次第に記録が残され蓄積されて人類の遺産となった。それから数千年の歳月の後に日本に漢字が入り、早速古事記や日本書紀という国家起源の神話・伝説が編纂され英雄譚が文字となったのは、時間的に大きな隔たりがあるとはいえ、古代メソポタミアのギルガメシュ叙事詩の成立などと流れを同じくしている。
加えて日本では、漢字から生まれた文字を用いて和歌という形式の詩歌が大きな発展を遂げ(その起原は呪文であり祈願であり「国褒め」つまり国土礼賛だったされるが)、さらに小説や日記や随筆など、当時の世界には類のなかった文学形式が芽を吹き隆盛を遂げた。もちろんこれは社会学者に言わせるとほんの一握りのエリート層に限られた現象ということになろうが、9 世紀・10 世紀の欧州ではカール大帝に代表される支配者の権威やその生涯についての写本は残されていても、源氏物語のような「お話」や枕草子の如くに気の利いた身辺雑感が書物として残されたケースを私は知らない(当方の不勉強のせいも無論あるから自信を持っては言えないが)。
どうもこの読み物好きというのは、その頃既に日本人の遺伝子の中に居座っていた国民性のような気がする。21 世紀の現代でも国文科の生徒に人気のある平安時代の女性は「更級日記」の菅原孝標女だそうで、彼女は夢にまで見た源氏物語全巻を親戚のおばさんから贈られ寝食を忘れて読み耽るのだが、その楽しさときたら「后の位も何にかはせむ」という台詞に今どきの娘たちも大いに共感を覚えるのだそうだ。
先日この KBC の磯目春硯さんのブログ「風信 沼のほとりから」にサフランの句があったことから、ふと思い出して森鴎外の同名の短編に言及したのだが、それは冒頭の部分がとりわけ記憶に残っていたためだった。
「私は子供の時から本が好きだと言われた。少年の読む雑誌もなければ、巌谷小波君のお伽話もない時代に生まれたので、お祖母さまがおよめ入りの時に持って来られたと云う百人一首やら、お祖父さまが義太夫を語られた時の記念に残っている浄瑠璃本やら、謡曲の筋書をした絵本やら、そんなものを有るに任せて見ていて、凧と云うものを揚げない、独楽と云うものを廻さない。」
後の大文豪を彷彿とさせる話だが、ちょうどこれを目にした頃小説家田辺聖子のエッセイに、子供の頃からとにかく活字中毒で何も読む物がないと薬の瓶にある効能書きまで熱心に読んだ、とあったことが二つの思い出話の印象を互いに強化したのだった。
この御両人は有名人だけれども、普通の庶民にもこういう人は多いはずである。これはたまたま私の父の 17 歳年下の末妹のケースで、母親に甘やかされた彼女は素行も悪く当時でいうフラッパーのどうしようもない娘に育ち、終生親やら兄やら息子にまで迷惑をかけっぱなしだったのだが、あるとき父が「しかしワシの文学全集をよく開いていたのは、成績の一番悪い彼女だった」と言うのを聞いて、ふと彼女への気持ちが和らいだ。
読書というものが教養には不可欠で読書量がその指標になるという考え方は洋の東西を問わないらしく、英語では well-read、ドイツ語の場合は belesen(読むという動詞 lesenから)といえば博識・博学という意味になる。しかし少なくとも日本の場合には、アプレガールと顰蹙を買っていた私の叔母のような例も多々あって、それらは日本人の読書好きが肩ひじ張らないごく普通の楽しみであることを証明しているようだ。
そしてこういう手近な楽しみが与えられていることに感謝するにつけても、私はドイツが生んだ印刷術の発明者ヨハネス・グーテンベルクの功績に思いを致さずにはいられない。ディジタル化が進んで電子文書が出回っている現代でもその元を辿れば 15 世紀半ばに発明された活版印刷技術であり、現在文字に親しむこの世界の誰もが彼の恩恵をしっかり受けているはずである。
グーテンベルクの生涯は非常に興味深く、きょうび流行り言葉となっている「世界人」とか「国境を越えた文化人」などという言葉を聞いたら、ふん、何を今さらと言いそうだが、そもそも彼の生きた時代にはドイツという国も概念もなくて、彼も今の EU 圏のプロトタイプとされる神聖ローマ帝国の都市マインツに生まれそこで没している。後に欧州全体に巨大な権勢を誇るハプスブルク家が帝室として安定を得る少し前のことで、グーテンベルクが印刷技術を追究し成功させたのは、マインツでなく現在のアルザスのストラスブルクに於いてだったが、アルザスも当時はその全土が神聖ローマ帝国の領土だった。だからマインツからライン川を遡って 190 キロの距離にあるストラスブルクがグーテンベルクの活動の場の一つだったことには何の不思議もない。
アルザスは今では典型的な観光地のようになっている一方で、積年の独仏の確執や恩讐など忘れて冷静な目でその歴史をたどれば、これほどエキサイティングな地域もないように思う。ストラスブルクで完成させた技術をグーテンベルクはマインツに持ち帰り、そこで印刷業を商売とするがその存続に資したのは第一に聖書の印刷であった。
そしてこの聖書の印刷こそが、グーテンベルクの死から半世紀後に起きて野火の如く欧州中に広がった宗教改革の影の立役者であった。それまでは民草のほぼ全員が文盲で(この言葉は差別的で放送禁止用語かもしれないけれど、英語の illitterate やドイツ語の analphabet⦅仏語もほぼ同じ⦆には「盲」の意味は直接にはなく、といってそれらの外国語に頼るのも変なので敢えてこの日本語を遣わせてもらう)、教会で司祭や神父の言うことを無条件で信じるほかなかった。欧州の特にカトリックの教会に入ると、聖堂や礼拝堂の壁に所せましとイエスの生涯の物語を時系列で示した絵画が並ぶが、本来これは聖書を読めない信者のための絵巻のようなものだった。
つまり民の無知をよいことにやりたい放題・言いたい放題だった当時のカトリック教会に対し、ルターやカルヴィンは神と人間の間に介在するのは教会ではなく聖書に基づく信仰であるとして反旗を翻したわけで、それを受けた「寄らしむべし・知らしむべからず」の教会側の慌てようは想像に余りある。
さらにルターは、それまでラテン語で書かれていた聖書をドイツ語に訳して広く人民の読み物とした。それを次々に輪転機にかけて民に配るための印刷術なかりせば、宗教改革もあれほど急速に影響力を広げることもできなかっただろうし、その後のルネッサンスや啓蒙主義の台頭も、いつか起きたにしてもかなり遅れてのことだったろう。さらに、続く科学革命や産業革命の縁の下の力持ちとなったのも印刷業者たちであった。
よく知られているようにドイツにはロマンチック街道とかいうものがあり、アルザスはワイン街道とやらのおかげで特に初秋から観光客が押し寄せるが、私はマインツを出発してストラスブルクに至り、そこからセレシュタット(フランス語でセレスタ)を経てバーゼルを終点とするルートを「活版印刷街道」、ドイツ語でなら Buchdruckstraße(ブーフドゥルックストラッセ)と呼んでいいのではないかと思っている。
セレシュタットはアルザスの町の中でも目立たない地味な土地柄であるが、宗教改革の波のうねりの中で 16 世紀以降ここは哲学者・人文学者などルネッサンスの担い手が集う学問の地として栄えた。その時代の記念碑として今も人文学図書館があり、最近それが大規模に改築されてこの静かな町の観光資源になっている(二番目の写真)。

また、セレシュタットからさらにラインの上流へ 80 キロほどの、いわゆる三か国コーナー、ドイツとフランスとスイスの国境の地にあるバーゼルは、聖書印刷に端を発するビジネスを推し進めて欧州有数の出版業の中心地となった。世界的な製薬企業や化学産業で知られるバーゼルであるが、ライン河畔のこの町では現在も多くの出版業者・製本業者が活躍している。だからこのルートは活版印刷街道という色気のない名称よりも、古代文明の中心地に因んで「啓蒙の三日月地帯(enlightenment crescent)」と名付けた方が適切かもしれない。
さて、そのストラスブルクにはグーテンベルク広場というのがあり、私たちはいつもそのすぐ傍の地下駐車場に車を停める。そこを出てすぐグーテンベルクの大きな像を初めて目にしたときは、この人についてもドイツ・アルザス史に関してもほとんど何の知識もなかったのでドイツ人の像がどうしてこんなところにあるのかと思い、ドイツ人嫌いのフランス人がまたどうして、と不思議がったのであるが、そのうち少しばかり地理・歴史を学ぶに及んで背景を納得した。そして、まあマインツにはグーテンベルク博物館もあるし、マインツの国立大学はヨハネス・グーテンベルク大学と呼ばれているし、グーテンベルクの名前は十分使わせてもらっているから、この像は別にフランス側の文化の盗用には当たらないか、と自らを宥めた。
その後長くこの像には注意を払わなかったのだが、あるとき日本人青年を案内して行ったときに説明しつつ眺めると、グーテンベルクが広げた本のページに何か書かれている。おお、なんと Et la lumière fut とあるではないか。これはフランス語で「すると光があった」という意味で、旧約聖書からの引用である。

約 6 年務めた組織を辞めてフリーになった時、最初はろくに仕事もなかったから、この際フランス語をちょっと復習してみようと買った教科書(岩波書店、前田陽一著、1957 年初刊、カセットテープ付き)にこの聖書の言葉があった。
そもそもこれを選んだのは、最初店頭で開いた頁に Vous êtes le sel de la terre(あなた方は地の塩である)という新約聖書の句があったためである。これが「あなたは先生です、私たちは生徒です」なんて例文だったらそんな教科書には 100 円だって払わなかったろう。そのあとのレッスンでも、「~に過ぎない」という言い方の例として「人間は、自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない」というパスカルの言葉が引用されていたりして、ミーハーが服着ているような私は「わあ、カッコいい!」と即買ってしまったのだった。
そして大分あとの方の単純過去と命令・願望を表す動詞の活用例として、Dieu dit: Que la lumière soit; et la lumière fut(神は「光あれ」といわれた。すると光があった)という創世記第一章の言葉が出て来るのである。40 数年前の復習の成果などほとんどなかったフランス語の乏しい知識だが、こんなところで役立つなんて、と嬉しかった。
さらにこの像の言葉から、「光」の意味について改めて考えさせられた。啓蒙という語は蒙(無知蒙昧)を啓くの意で、英語の enlightenment は文字通り光を当てるという意味だし、フランス語ではずばり les Lumières というと啓蒙思想を指す。
ユーラシア大陸の西端で 15 世紀という遠い昔に放たれた光は、400 年余りの歳月を経て大陸の東のそのまた向こうの島に届き、そこの子供たちを照らしてくれたのだった。
最後に参考までに欧州における印刷物の急速な増加を示すグラフを添付する。「ヨーロッパの書籍の増加 500 年- 1800 年」とあり、Manuskripte は手書きの写本、Gedruckte Bücher は印刷された本のこと。部数は指数関数的な増加を示して 6 世紀の一万台から 18 世紀には 10 億部に達しており、1500 年を境に写本は姿を消した。


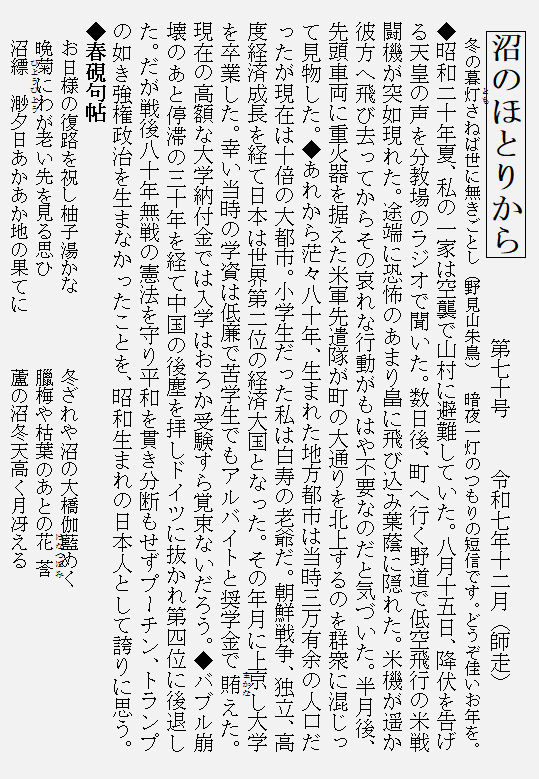


上のグラフの注を訳すのを忘れていました。一番下に「南ヨーロッパ(ビザンチン、後のオスマン帝国)とロシアを除く」とあります。これは大事なポイントです。少し前に読んだ本に書かれていたのですが、既に1485年の時点でオスマン帝国のスルタンはアラビア語での活版印刷を禁止したそうです。その理由は、一つには写本の写字を生業とする人たちの反対に考慮した面も多少はあるけれども、何よりも宗教上の権威を売り物にしている聖職者たちの独占が失われるという恐怖を宥めるためだったとか。1727年になってやっと、オスマンの印刷技術があまりに遅れていることを認め、最初のアラビア文字の印刷業者を許可したそうです。ロシアについては、盲目的服従を強いるその強権政治の歴史を示している話です。
無味乾燥とした歴史の記述がここへきて息を吹き返しその意味を探り歴史の来歴に新しい光が与えられましたね、ちょっと感動しています。
100年以上前の日本の子供が大人っぽく新聞を広げる写真から…それからそれと手繰り寄せて、決して身近ではないものを身近に見せてくれる。 さらにグーテンベルグの偉業を彷仏とさせるために、びすこさんは活版印刷街道なる言葉を編み出す、、いや待てよとさらに…大づかみに意味が取れるように「啓蒙の三日月地帯」と話を展開していく。
僕の最初の相棒が、ヨーロッパの貴族(といってもいろいろピンキリですよね😉)に少しばかりの伝(つて)がある輸出入業をしているその先輩(その人物にも後日、日本に来た時、相棒から紹介されました)のところに招かれてヨーロッパで遊んでいる時、、思ったこと…あんなとこ(ヨーロッパのこと)いちまるさん、何年いたって歴史を知らなければ何にも面白くないよ…と言っていました。
今それを思い出していました。 このシリーズもう1冊分ぐらいのボリュームありますよね…どうかこの調子で健筆ふるってください。 歴史を綴る人は学者をはじめ数多いるにしても、歴史を今に思い出せる人はそうそういないと思います。 楽しめました…「語り」はこうでなくちゃ😊ありがとうございました。