「流離譚」を読む-②―ドイツの黒い森から 67(びすこ)
- クレマチス

- 2025年1月15日
- 読了時間: 14分
文助の次男で覚之助の弟嘉助が京都で刑死したのち、勤皇党への関与から兄の覚之助も捉えられ、入牢して終身刑を言い渡されたあとに自宅での蟄居を命じられるなど、なにやらもたついた挙句、かの戊辰戦争に参加して最終的に会津で戦死する。
それまでの薩摩・長州の動きもそれに関わった土佐の志士の命運も、さらに奥州での戦況までも、章太郎が念入りにその仔細を述べているだけに煩瑣なことこの上なく、ここでさすがに私も投げ出したくなった。しかし何人かの土佐の郷士は昔からその名を知っているので親しみがあって、それが好奇心を支えてくれた。司馬遼太郎に再発見された坂本龍馬は別格として、近江屋事件で龍馬と運命を共にした中岡慎太郎などは安芸郡の庄屋の息子で県東部では人気があり、以前にこの人の業績を調べていたら照れたような笑顔の写真が出て来て、きっと育ちのいい坊ちゃんに違いないと私は好感を抱いた。彼の生家は海辺からだいぶ奥に入った北川村に今も残っている。写真で見る限り、私の隣村から出て日本中にその名を馳せた政商・岩崎弥太郎の生家よりもずっと立派である。
弥太郎の家は郷士で、子供の頃大人たちが彼のことを話しているのを耳にして母に「岩崎弥太郎ってお侍さんだったの」と尋ねたら、「侍なんかであるもんですか、ただの郷士よ、百姓と変わりゃしない」というつっけんどんな答えが返って来た。これが、自分より身分の低い者に対する N 家の典型的な反応である。しかし岩崎家が郷里で一部こんな風に侮られていたことが、あのターボチャージャーのような人物の輩出に繋がったのであろう。(借金を踏み倒して出て行った、との噂もある。)
土佐三伯(伯爵だったから)の一人の後藤象二郎にネチネチいじめられた気の毒な谷干城は県の西の人で、あまりに謹厳実直な人柄が仇となったらしい。エピソードをきくとピューリタンだったのかと思ってしまう。その出身地・窪川で私の又従弟が医師をしており、あるとき彼に谷干城の生家は残っているかと尋ねると「ナンノコッチャ」という顔をされた。当然ながら、土佐人がみな土佐人に興味を持っているとは限らない。
知名度は異なるが何人かの登場人物の中で興味を惹かれたのは、吉田東洋殺害に嘉助と共に加担した那須慎吾という若者や、同じ高知西部の梼原(ゆすはら)の出身者吉村虎太郎など今なら青春ドラマになりそうな男たちで、私は昨年 11 月に山奥のこの町を訪ねて景色にも住人にも好印象を持っていたため、彼らの生涯についてもっと知りたいと思った。次回帰国時にまた出かけて、親切な町役場の人たちにいろいろ訊いてみよう。章太郎自身、執筆にあたってこの地を訪れており、
「梼原へは、私も一度だけ行ったことがある。たしか高知を一時頃の汽車で立って、二時間ぐらゐかかって須崎まで行く、そこからバスで山道をまた一時間ほど上がったところが終点の梼原であった」
と書かれている。これは 1980 年頃のことで、自動車道路網が発達した今では東部の私の家からでも 2 時間半ほどだから、章太郎が今ドライブしたら驚くだろうが、現在この町は例のスター建築家・隈研吾の木造建築物で全国的に有名になっており、私もそれらを見に出かけたところ、観光シーズンでもないのに駐車場の車の多くが愛媛、香川、広島など県外のナンバーだったのが意外だった。考えてみればここは高知の中心地よりも山一つ隔てた愛媛県の方に近く、そのため東京から航空機を使う梼原の人は高知空港ではなく松山空港に飛ぶとのことだった。
ましてその昔には、高知といえばその三方をぐるりと深い山に囲まれた実にアクセスの難しい地で、ここから京阪への旅も、昭和の時代においてすらたいがいは船で室戸沖を回って行ったという。だから章太郎も言及している船酔いの薬「シーシック」(何と芸のない名前か)は必需品だったらしい。いや、それ以前に、そもそもここは日本有数の辺陬であるために、平安時代や鎌倉時代の貴族の遠流の地として選ばれたのだ。山内氏がその殊勲で手に入れたつもりの土佐藩だったが、実際は一豊もこの地に来てみてしみじみ「都落ち」と感じたのではないか。
その辺陬の地から、安岡覚之助が戦に向けて出立したのは、何やら曖昧な理由で獄舎から放免された翌年の 1 月のことで、幹部以外はすべて郷士から成る兵員 600 の大隊「迅衛隊」の一員として京に向かう。高松・丸亀を経て同隊が京に入ったのは月末であった。そこから彼らは 2 月になって濃州大垣に到着、迅衛隊の隊員の中には覚之助の弟道之助もいた。実際のところ安岡家 4 軒のうちで大隊に加わらなかった男子は老人、子供、病人のみであったという。大垣を出た迅衛隊の一部は上諏訪につき、そこから一部土佐藩の兵は本隊から外れて甲州街道を進む。素朴な彼らはしたたかな薩摩藩や長州藩、肥州(肥前・肥後)等の連中に援護されたり翻弄されたりしながら北上するのだが、その進軍道中の描写を読むと、降りしきる雨と寒さは別としてフィリピンのレイテやコレヒドールの日本軍を連想させる。
私が困ったのは地理的関係で、それでなくても東北地方の地理などをきちんと学んだことはないので、草加とか越谷、宇都宮などはまだわかるにしても(宇都宮に来て隊員の最大の不満は新鮮な魚が食べられないことだったそうな)、会津周辺となると皆目見当がつかない。鶴ヶ城という名が出て来ると、あ、そういえば昔「アイヅ~ワカァマツツルガァジョー(会津若松鶴ヶ城)」で始まる歌謡曲(橋幸夫)があったっけ、と思い出す程度の無知加減なのだ。しかしここで、私の読書意欲を甦らしてくれる材料が一つあった。「保科正之」という中公新書である。
11 月の離日の前日に少し時間があったので丸善に行き、かさばらない本をと探していてこの「保科正之」という題が目に留まった。この人物については、いずれかの将軍様の落胤として当初はひっそりと暮らしていたのが、あるときから幸運に恵まれてその本来の能力を発揮する機会を与えられ、「やがて立派なお殿様になりました」みたいな話を読んだことがあったので、そういう人の立志伝なら読んでも疲れないだろうと買って、さっそく帰りの飛行機の中で読んだ。身分の低い女から生まれたこの人の父親は二代将軍徳川秀忠で、正室於江与(お江)の目を恐れる将軍にはろくに親らしいこともしてもらえなかったが、異腹の弟家光とその子家綱に目を掛けられて目覚ましい出世を遂げる。最終的に会津藩主となり、松平姓を名乗ることを許されたにもかかわらず、不遇の時代に養子として自分を支えてくれた保科氏への感謝から、松平を名乗るようになったのは彼から三代目の正容の時代だというから、苦労人だけに殊勝で義理堅い人だったのですね。
なお、会津藩では最初は藩主の息子に「正」をつけるのが常だったが(これは安岡家の場合も同じ)、正容の代以降は容という字を用いるようになって、だから保科正之から 9 代目の最後の藩主はよく知られているように松平容保という名であった。それまでに、諸般の事情で正之の血は男系では絶えており、徳川からの養子で幕府との血縁は保っていたが、どこの系統なのか容保の美男ぶりには女中たちまでが騒ぐほどだったそうだ。全くいつの世も・・・
それにしても初代会津藩主は、家光との出会い以降の幸運にも拘らず女運は実に悪い人だったらしい。最初は側室として正之に仕えのちに継室となったおまんの方という女性は、他の側室が生んだ娘が加賀前田家に嫁ぐことになった時、自身の娘と比較してあまりに恵まれた縁談であることに嫉妬して彼女を毒殺しようと企み、間違って自分の娘を殺してしまったというから恐ろしい。そんな経験のゆえか、正之が推敲に推敲を重ねて作成したという「会津藩家訓」 15 か条には「婦女子の言一切聞くべからず」という条項があって、ああ、苦労したのねえ、と思わず同情してしまう。同情しただけでなく、こういうエピソードが、ミーハーの典型である私に会津藩と松平家を「生きた歴史」にしてくれたのだったけれど。
戊辰戦争における戦闘場面において、個人的な事情もあり「おや」と思った箇所がいくつかあった。いずれも兵器に関してで、例えば会津方の武器よりその性能が優れていた西軍のドイツ製「ゲヴェー銃」というのがあるが、ゲヴェーは Gewehr でこれ自体が銃という意味なので「銃銃」と呼んでいることになる。サハラ砂漠が「砂漠砂漠」なのと同じ。他にヤーゲル銃というのもあり、これは Jager(猟師)の銃こと。全般にフランス製などよりは、ドイツ製の方が威力を発揮したらしい。倒幕後の日本は当初軍事に関してはフランスに倣おうとしていたのが、1870 年の普仏戦争でプロシアが勝利を収めたので範をドイツ式に切り替えたと聞いているが、明治維新の前からドイツの武器は既に広く使われていたわけである。ただし、どこの国の物にしてもちゃんとした使い方の研修・訓練がなかったようで、弾を込めるのに時間がかかって相手にやられたり、まったく役に立たなかったりという場面がいくつもある。大砲隊の失敗などは笑うしかないというところだった。
この件は、近代兵器の調達を米国に頼って大枚をはたいている現代日本の防衛システムに関してもありうることで、160 年近く昔の兵士の不器用な闘いぶりを馬鹿にしていてはいけない。言語でのコミュニケーションはほぼ問題なくなったとしても、倫理道徳を説きつつ「隙あらば」という列強の姿勢は今も変わらないのだから。
ここでいよいよ覚之助の最期を語ろうとして、大事なことを言い忘れていたのに気がついた。「流離譚」はもともと雑誌新潮に昭和 51 年 3 月から昭和 55 年 3 月まで 55 回にわたって掲載されたものなので、各回を示してくれれば目印になるのだが、区切りなしでどんどん進むため後で戻って調べるのにちょっと苦労する。それが、途中で気づいたのだが、正俊さんの「流離譚を隙間から覗く」で各回の最初の文を書き出してくれていてそれが目次のようになり、大変助かった。
覚之助の戦死を語っているのは新潮掲載 43 回目で、そこで章太郎は信憑性の高い叙述として昭和 4 年に高知で刊行された著作から引用しているので、少し長くなるが私もそれをそのままここに記す。
「暫くたつと、土州(注・土佐のこと)の軍隊より長州の軍隊に合図する必要が生じた。何の合図であったか確かとは判らないが、多分追撃に関する合図であったと想像せらる。その合図をするため、安岡亮太郎が胸壁の上に登らんとすると、側にいた安岡覚之助が、自分はわらぢをはいてゐるも亮太郎は足駄をはいてゐるを見、「おらが上がる」といひざま胸壁の上に駆け上がり、その傍そばに突っ立ち、体の側面を敵に向けながら、ぬび上がって長州の軍に合図をした。その時早し、彼の時遅し、一発の敵弾、うなりを発して飛び来たり、覚之助の耳のすぐうしろ(覚之助の郷里山北村にてやろくがつぼと称するところ)に命中し、急所の傷手にはたと倒れ、その儘、そこに絶命した。」
これは安岡亮太郎の子息を取材して書かれたものなので、かなり確実であろうと章太郎は言っている。
戊辰戦争についての章太郎の記述の中でさすがと思わせられたのは、彼がこの戦争における「官軍」と「賊軍」という言葉の対比でアメリカの南北戦争に言及している箇所だった。自らの人生を顧みて落第と病いの繰り返しだったと述懐しているわりには、章太郎の優秀さは広く認められていたのか、ロックフェラー財団の奨学金で 60 年代初頭に公民権運動の盛んだったアメリカに留学しており、この経験が章太郎に新たな地平を開いたらしい。彼によれば、アメリカ南部の人々は南北戦争から(当時)100 年経ってもその戦いを civil war(内乱)と呼ぶことを拒み、あれはあくまでも州と州との戦争だと主張して譲らなかったという。勝ち組に属していた土佐の人間といえども、負ければ賊軍というのは理不尽に過ぎるとの思いがあったのだろう。
覚之助はこの地にて葬られ、墓は会津若松市の東明寺にあるそうだが、分骨されたとも聞いている。章太郎が「流離譚」の冒頭で述べている、親戚の中の「一軒だけ東北弁の家」というのは、覚之助の墓を守るために奥州に移住したその子孫というのはどうであろうか。実際には、系図の中の、養子である正煕(文助の妻の実家藤田家の次男だから、嘉助と覚之助の従弟にあたる)が東北地方に移り住むようになったのは、眼科医になった彼に養蚕業の盛んな東北のどこそこに行けば目を病む女工が多いので流行ると助言してくれた人がいて、それに従い妻の美名吉(みなえ)と彼女の母さらには祖母まで伴って遥か遠くの地に渡ったことになっている。もちろん、そういう助言が得られたのは、やはり覚之助と会津との縁からであろう。実際に正煕の医院は繁盛したらしい。
嘉助の遺児真寿が覚之助の長男つまり従兄に嫁ぎ、その娘・美名吉が正煕を婿養子にして男児が生まれるのだがその子も美名吉も奥州の梁川(現在の福島県伊達市梁川町)で亡くなり、美名吉の祖母・万喜は異郷に住まいを移して間もなく世を去っており、正煕の再婚後は真寿にとっては直接に血の繋がらない家族ばかりになって、彼女は一人土佐に戻って来る。そのことで、東北の安岡本家と高知の分家との間はしばらく疎遠になってしまった。
土佐では真寿は、覚之助の弟・道之助に嫁いで未亡人となっていた自分の妹と共に母の実家公文家に身を寄せる。この姉妹はしばらく前からクリスチャンになっており、その影響は真寿の娘にも及んで、美名吉は死の床で讃美歌を口ずさみ真寿がそれに唱和したという。この場面について章太郎は
「それにしても、その讃美歌の、
亡ぶるこの世
くちゆく我が身
何をかたのまん・・・
という言葉は、特に臨終の床にある人の口からもれることを想像すると、まことに悽愴なものがあり、傍に座ってゐる人は居たたまれぬ思ひがしたかもしれない。それにはキリスト教信徒といふより、この世に何かを求めながら、つひにそれを得られなかった人の無念の想ひがこもっているように感じられるからである。」と綴っている。
父の顔も知らず夫とは早くに死に別れ、娘と孫にも先立たれた薄幸の女性真寿は、「安岡の御叔母様」として寺田寅彦の日記に現れる。短編「どんぐり」にも記されているとおり、寅彦の最初の妻夏子は新婚まもなく結核を患う。感染を恐れる下働きの女たちにその世話を拒まれ、高知に戻って療養していた時に、真寿が頻繁に見舞うかあるいはその付き添いとして介護にあたっていたらしい。二十歳で世を去った娘・美名吉の死因もおそらく肺結核であった。章太郎はのちに「第三の新人」の仲間だった遠藤周作を代父として洗礼を受けるのだが、「沈黙」の作者がそこに母性を見たカトリック教への章太郎の帰依の背後に、安岡家の女たちの姿が垣間見える。
流離譚の第一回では、正煕が土佐・島村家から迎えた二番目の妻との間に生まれた息子正光がある日東京の章太郎の家を訪ねて来る設定になっていて、志那事変が大東亜戦争に発展する頃のこととある。正光の名刺に書かれた肩書には某営団の会長とあり、どこからどう見ても人品卑しからぬ立派な紳士である。東北の町の医師の息子として、二世代・三世代前の安岡家の男たちが夢見ることさえなかった順風満帆の人生を歩んでいたのであろう。後に正煕から秀彦(正俊さんの祖父)に宛てた礼状に、「今少しすればせがれも県知事くらいにはなるのではないかと思います」とあるのが、世の父親の典型として何だかおかしい。(と笑っていたら、実際 1940 年に山梨県知事になったそうである。)
一族のさすらいの物語はこの手紙をもって終わるが、昭和に入って桂浜に坂本龍馬の巨大な銅像が立てられるに先立ち、山北で村の青年団有志の手で覚之助・嘉助の碑が立てられたことが終章には述べられていて、正俊さんの解説書には「昭和 4 年に秀彦の幕引きで両烈士の碑の除幕式を行いました」とある(写真1)。会津戦争で倒れた覚之助は「明治 31 年、特旨を以って正五位を贈位され」、投獄され罪人として斬首された嘉助に対してはそれ以前「明治 24 年、従 4 位を追贈された」というから、嘉助の方もリハビリを経たわけだ。(Rehabilitation というのは昨今は専ら病後や事故後の身体的・心的機能回復訓練という意味で使われるが、この言葉の本来の意味は「名誉回復」だという。)

奥州の正煕から正俊さんの祖父秀彦氏への書状は、秀彦氏が碑の建立に尽力したのみならず本格的な両烈士伝を考えていることに本家当主として感謝を伝えるためで、中風を患って寝たきりとなり手も不自由な身で書き綴ったものである。
「・・・私モ申上ゲタキ事ハ山々アレドモ、字ハ書ケズ、眼ハ見エズ、哀シキ日ヲ送ツテ居マス。ドーカシテ今世ニテ今一度、故郷ノ方々ニ御目ニ懸リタイト思ツテ涙ニ暮レテ居マス・・・
幾世へぬらんふるさとは 人づてならで問ふよしもなし
古里に吾待つ人もなからまし 何恋しくてぬらす袖かな
末筆乍ラ皆々様ヘ宜シク御風声祈リ奉リ候。目モ見エズ半身不随ニテ書ケマセン。ヨロシク御判読ヲ願上マス。私家内一同与リも宜敷申出候。」

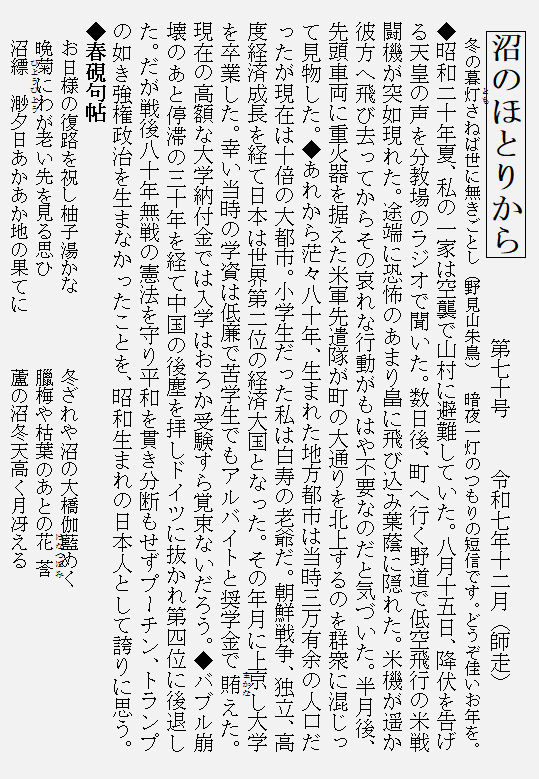


クレマチスさま
早速お助け下さってありがとうございます。また、ライントークの件も。おかげ様で数か月分見逃がしていた分をこれから拝見できます。昨年9月初めに夫の会社の件で慌ただしく、葛飾文芸クラブに目を通す時間もないまま中旬には帰国してしまったので随分溜っておりまして、これから少しずつと思っています。
ご紹介下さったリンクで最初に見たのがマルクス・ガブリエルのEhical Capitalismという講義で(1時間と長いので未だ最初の方だけですが)、これはこのところ考えていたテーマとのちょっとした関連で渋沢栄一の言う道徳的合本主義を思い出させます。
ところで、一昨年にはこちらの新聞・雑誌にずいぶん資本主義に関する記事や論文が掲載され、その流行に乗って私もアダム・スミスや社会主義に関する本を読んだのですが、取りあえず切り取っておいた記事を昨年読んでいて初めて気がついたのは、2023年がアダム・スミスの生誕300年に当たるということでした。
さらに、またまたミーハー的な話題になりますが、マルクス・ガブリエル氏はドイツ西方のラインランド・プファルツ州の生まれ、ここは夫の故郷なので私も同州については多少の知識があります。それにしても、彼のホームタウンであるレマーゲンというのはどこかで聞いたことがあるなあ、と考えていて、「レマゲン鉄橋「(1969年)という映画を思い出しました。お馴染み、ドイツ軍と連合軍の話です。ラインに掛かる橋が舞台になった映画としては、70年代のリチャード・アッテンボローの「遠すぎる橋」の方が有名ですけれど。
先ほどレマーゲンのことを夫と話題にしましたら、彼が言うには、戦後にこの辺りが連合軍に占領されたとき、レマーゲンはフランス軍占領地と米軍占領地との境界だったんですって。それで、そこから北の人は学校で英語(米語)を、南側では仏語を習わされたんですって。
いけない、こんな雑談ばかりしてないで、ライントークを読まなくちゃ。
平和を盾に環境保護の剣で諸般の事情を押しまくり切りまくり話をどんどん進めた結果快刀乱麻とはいかず状況はかえって混乱を極め怨恨思惑が宙に浮く。 それに紐付けて記録に残さなければあらすじさえもたどれなくなる。やがてそれは物語として残れば幸い、埋もれていったことの方が圧倒的に多いと思うのが普通。 骨の折れる仕事ですが形に残すために頑張っていただきたいです。評価する人判定する人がいなければ事実なんて泡沫のように別の事実で隠蔽されていく。 僕らの足元なんてその程度のものと思うと自分自身が危うい。何とか立っていられるのは頑張っている良心的な人がいるから、、またしても思い出すのは三木清の言葉。良心的な人々で世の中は保たれている。
おはようございます。お忙しい中、早速のアップをありがとうございます。
さきほどネットでDie Weltという新聞(中道右派の全国紙、ちょっと読売新聞に似ています。実際、提携しているようです)を見ると、わ! いきなり眼前に4人の元政治家の写真が現れ、
「Sanna Marin, Jacinda Ardern, Justin Trudeau und Emmanuel Macron galten als Hoffnungsträger einer neuen Form von Politik. Alle vier sind in dieser Rolle gescheitert. Aus welchem Grund?
サナ・マリン、ジャシンダ・アーダーン、ジャステイン・トルドー、エマニュエル・マクロン、彼らは新しい政治形態の希望の星とされてきたが、4人ともその役割を果たすことができなかった。それはなぜか。」
とありました。購読料を払ってないのでそれ以上は読めなかったものの、内容は推察できます。
特に最初の二人の女性については、私は本気で腹を立てていました。ニュージーランドのアーダーンは数年間マスコミの寵児としてその「人道的で進歩的な」姿勢がもてはやされ、日本でも極めて好意的な見方が多かったのですが、英国のブレア元首相の強力な支援もあってわが世の春を謳歌していたこの人の実力を私は全く評価できませんでした。極め付きは、最後に「全力を尽くして疲れ果てたので辞める…結婚もしたいし」と言ったこと。長年の同棲相手との間に数年前子供が生まれ、「自由な女」であることに加えてキャリアと家庭を両立させていると、それまた称賛の的でしたが、そこへこの発言。同じことを男性の政治家が言ったらどうなります?結婚もしたいし・・・? 疲れ果てた?
日本のメディアが(愚かにも)その美貌を称えたフィンランドのマリンも、退陣の理由について似たような発言をしていました。ドイツモコイツモ舵取りに真の手腕が問われる事態になったら、手に負えないと投げ出す。
感情的な見解と言われても、私はこんな政治家「女の風上にもおけない」という憤りを覚えます。そんな女性をチヤホヤしたマスコミにも腹が立ちますが、そもそも彼女らを選んだ国民は何を見ていたのか。「国民は彼らにふさわしい君主を持つ」と言ったのは誰でしたっけ。
マクロンだけは現役で、フランスも制度上大統領を退陣させるのは難しいため27年までこのままでしょうが、この国も大変なことになっていて、自分は大統領のままこれまで既に何人首相を入れ替えてきたことか。ドイツはあとひと月ちょっとで政権が変わります。マクロンさん、本音はショルツが羨ましいのではないでしょうか。
「・・・前回のブログをお送りして一週間も経っていませんが、一応出来上がっているのでお送りします。今回は少し短め、といってもやっぱりグダグダ書いてしまいました。でもこれで完結ですから、ご安心下さい。
さて昨今はリベラルと言われる政治家が不人気で、その顕著な例がカナダのトルドー首相の退陣。インフレや不況など原因が取りざたされていますが、この「多文化」「多様性」「寛容」の模範とされたような国で、移民やLGBTを推進していた国家の長(実際には元首は英国国王ですが)が辞任に追いやられるというのは、目下いわゆる左派・リベラルが真剣に考えねばならない事態に世界全体が陥っているように思われます。
今朝の日経に「トランプ流いじめ外交の本質・大国主義のヤルタ志向」というタイトルを見て、ちょうど昨夜のこと、ああ、今年は敗戦から80年になると考えていましたので、その偶然に考えることが多々ありました。トランプの件はさておき、「ヤルタ式外交」が今も密かに行われていることは事実で、一つには、80年前の戦勝国が未だにそのことをベースに全てを判断し実施しているけれども、当然それに反発を持つ国民もいるはずということです。ドイツなどはそれでもナチスの蛮行を持ち出されると何も言えず、日本も韓国・中国の侵略という歴史の前に頭を垂れるしかない、という事情がある一方で、実は現在の欧州の右派の台頭を見ていて、これはまさにヤルタ会議以降の体制への反乱という側面があると感じています。
それが明らかなのはハンガリーです。オルバーン首相は欧州では非民主的で専制君主のようだと非難され、EU で black sheep (もてあまし者) になっていますが、欧州メディアは彼に反対するハンガリー国民の動きは報道するけれど、オルバーンが常に国民の過半数の支持を得ている背景には触れません。ハンガリー人の間に見られる、第一次・第二次大戦で同国が戦勝国から受けた屈辱的な扱いへの怨嗟にどうしてヨーロッパの人が気づかないのか、気づかないふりをしているのか。
これは実はオーストリア人にも見られる心情で、オーストリアとハンガリーは長く二重帝国として繁栄していましたから、共感しあう部分がかなりあるようです。先日、オーストリアで極右とされる FPÖ が今第一党であることについての記事がネットにあったのでそれを夫に見せますと、彼はそこで初めてオーストリアが NATO 加盟国でないことを知って驚いていました (私は逆に彼が知らなかったことに驚きましたが)。オーストリアは国連加盟もかなり遅れましたし、EU への加盟も同様にしばらく渋っていました。(その点はスイスも似ているけれど、事情は異なります。)
オーストリアもハンガリーも今では小国ですが、一寸の虫にも五分の魂というところがあって、今なお敗戦以降の不利な条件を甘受せねばならないことへの憤怒は、私が日本人であるためか、理解できます。具体的には国土の多くを失い、それの回復が今の情勢では不可能ということへの怒りです。ハンガリーなどは、自国に比べてはるかに国力 (国民力) の劣るルーマニアにトランシルバニアなどかつて豊かだった地域を奪われ ( 戦勝国がそれを与えたのですが )、そのルーマニアに残ったハンガリー系が差別を受けていることへの「やるせなさ」をぶつける場がないのでしょう。私自身 2017 年にそのトランシルバニアに行ってそこの農地ならぬ荒地を見て、ハンガリー人の気持ちが分かるように思いました。
現在国連の在り方にも大きな疑問が呈され、EU もその権力の集中に批判が出ています。とにかく、戦後 80 年経った今も、基本的に何も変わらないことはおかしいと思う人は多いのではないでしょうか。これまでの歴史の中で欧州の前提・共通認識 (特に国境) が 80 年間も変わらなかったことはなく、4, 50 年すれば戦争や小競り合いやその結果の交渉でリセットされて来たのに、第二次大戦以降は「平和」が続いていることから敗者は敗者のまま。これでは、いくつかの国にとって今の平和は恩恵でなく呪いと感じられてもおかしくありません。
無論そのために戦争を望むなど馬鹿げていますが、同じ欧州内でこういう不満や恨みや、ときには復讐心まで抱く人々がいるという事実にしっかり目を向けて適切な対処をしていくのがEUの役割なのに、口を開けば人道主義と環境保護ばかり主張していることに、欧州人の大半はウンザリしています。それは昨年7月のEU議会議員の選挙において、左派やエコ・環境党がほとんどの国で大敗を喫したという事実によって証明されています。
・・・
というわけで、改めまして、今年も宜しく、お見限りなきようお願い致します。」
今回で「流離譚」を読むは完結ですが、このメールの内容も私信の域を超えた重要な示唆に満ちているので、独立したブログにまとめていただきたいと思っています。というのはひとつには、このホームページのバックアップはWixのサイトで保存していますが、バックアップではコメント欄は保存されないので、時間をおいて読み返すことができません。
さて今回の内容で一点だけ気になった部分がありました。それは吉村虎太郎に関する部分で、「梼原出身者の・・・」とありますが、私の調べたところでは「梼原の大庄屋」(出身地をWiki は高岡郡芳生野村、日本歴史大辞典では津野山郷など)とすべきではとおもいましたが、私の参照したものよりもびすこさんが典拠とされたもののほうが一次資料に近いのでとりあえず原文通りとしました。
さて、フォーラム欄を拝見しますと大村さんが浅井忠のことに言及されていますので、取り急ぎ1月のライントーク82 を工事中としてアップしておきました。関連のハイパーリンクのみ有効になるようにしておきましたので、ご興味がありましたら、Google レンズの活用で読み上げサービスが使えるスマホでご覧ください。これは「ヤスマサ 5 年」や山本をサンホンなどのミスもありますが、十分実用の域に達していると思います。