「民主主義に万歳二唱」他―E. Mフォースター――ドイツの黒い森から 47(びすこ)
- クレマチス

- 2022年11月29日
- 読了時間: 14分
今でこそ、E. M. フォースターと言えばその原作に基づくアイヴォリー監督の映画「ハワーズ・エンド」が複数部門でアカデミー賞を受賞し、またデヴィッド・リーン監督の「インドへの道」がアカデミー賞に加え世界各地で数々の賞を手にしたことなどからすっかり有名になったが、私が大学生の頃には、二十世紀を代表するこの英国人作家の名を知る人はほぼ英文学関係者に限られていた。
ジェーン・オースティン並みに寡作でその小説はせいぜい 6, 7 冊、しかも比較的短いという不純な動機でこの作家を卒論にしようかなどと考えたこともある。気が変わって別の作家にした四年生の初夏にこの人が亡くなり、そのためゼミで話題になって一連の作品が取りあげられた中で、ついでのように Two Cheers for Democracy という著作への言及があった。そのタイトルに訝る私に、教授は「民主主義は結構な制度だが、といって万歳三唱と手放しで喜ぶことはできない、せいぜい二唱程度ということだね」と説明してくれた。
その件がずっと頭にあり、社会に出てからの経験で民主主義の限界を実感するたびにこの万歳二唱という言葉が蘇ったが、仕事に追われて読む暇がないというのを自分への言い訳にし、また英語の本を取り寄せるのは面倒なのでとうとう読まずに終わった。その無精ぶりはドイツに来ても改善されず、民主主義への懐疑とまでは言わぬが不満を感じることはむしろこちらの国での方が多かったのに、いずれ読まなくてはと思いつつ 20 年余りが過ぎた。
それが突然、これはどうしても読まねば、さあ、読むぞ、と奮起したのは、このブログで既に何度か話題にした「孝子蔵書」の中の一冊のおかげである。孝子さんの本は圧倒的に小説が多く、エッセイや実用書みたいなのもちらほらあるが、そんな中で「いかに生きるか」を説くような書物は昔から好きではないのでパス。
小説・随筆や人生訓などの中に入らない、ほとんど唯一の例外を見つけたのは今年の夏のことだった。題名は「日本を思ふ」、著者は福田恒存である。この人は私が学生の頃はシェイクスピアの翻訳や演劇指導で知られ、英文学と無関係ではないのでもちろん私もその名をよく耳にしたが、当時必修科目だったシェイクスピアの講義をわが母校で担当しておられたのが名物教授の小田島雄志氏だったこともあって、福田恒存の訳本を読んだことはない。
因みに、入学してすぐの授業でさる教授に「英文科に来た以上は翻訳で読むことは恥だと思いなさい」といきなりかまされたこともあり、大学後半から極力それは守ってきたけれど、シェイクスピアだけは翻訳書を傍に置いてないと読み進めなかった。フォースターの「民主主義に万歳二唱」の和訳は古いのがあるらしいが、それを探さずに原書で読もうとした背景にも、この最初の教えがある。劣等感だらけの小心者は、この種の訓示には弱いのである。
福田恒存が保守派論陣に属することも「日本を思ふ」で初めて知ったが、「思ふ」などという仮名づかいから分かるように日本語に関しても筋金入りの保守派である。特に日本語表記に関しての頑固一徹な姿勢には、丸谷才一や山崎正和の大先輩かと思わせるところがある。しかし今回は日本語の議論や思想の傾向に触れることはしない。
福田恒存が展開する評論・持論は時期的にみてかなり古く、昭和 22 年(1947年)から最新でも昭和 40 年(1965年)までの時期に書かれている。ただ、私が小学校低学年だった昭和30 年頃まではともかく、その後の社会の動きは比較的よく覚えているので、遠い昔の話という印象を受ける箇所はほとんどなく、むしろ現代に通じるコンテンポラリーな課題が俎上に載せられているように私には思われた。
その中の「進歩主義の自己欺瞞」と題した章に、
〈E. M. フォースターは第二次大戦勃発当時、「私の信条」といふ短文の中で、かう言つている、「私が憎むのは大義の観念だ。もし私が国家を裏切るか、友人を裏切るか、そのどちらかを選ばねばならぬように追ひこまれたなら、私はむしろ国家を裏切る勇気をもちたい。」この国家といふ言葉の代わりに「階級」という言葉を持つてきたらどうするか。日本の進歩主義者はフォースターのように言ひうるであろうか。〉
というくだりを見てはっとした。それでその短文がフォースターのどの本にあるのかと考え、おそらく上記の「民主主義に万歳二唱」の中だろうと推測したのだが、少し読み進んで、
〈フォースターは、あらゆる信念を狂信として憎むが、もしお前は何を信じてゐるかと問われれば、それは人と人との結びつきだと答えてゐる。それは人類とともに古めかしい。人は、それが真であることを認めたにしても、そんなことを言つてみてもどうなるか、どうしたらいいのか、さう応じるであらう。方法論はない。当たりまへである。めいめいがやることだからだ。〉
とあったことから、これはとにかくフォースターを読むほかないと決めた。それで、町の本屋がコロナで商売を畳んでそこから注文してもらうことができないので、渋々我が家の管理人のMさんに頼むと(彼はネットで買い物するのが大好きなのである)、翌々日にはもう届いた。この 50 年余り頭の隅に置かれっぱなしだった書物がこんなにあっさり眼の前にあることに、なんだか拍子抜けしてしまったほどだ。
案じていた通り文字は小さく、読み始めて数時間後には頭痛がしてきたが、やがて少し慣れたのと、たまたま知人宅で便利そうなランプ付きの大ルーペを見てそれもMさんを通じて入手したことから、頭痛なしに読めるようになった。
「私の信条」という短文はすぐに見つかった。というより、全体で 370 頁ほどの「民主主義に万歳二唱」は二部から成り、第一部の The Second Darkness が約 60 頁、残りが全部What I Believe なので、ちっとも短くないのであるが、幸いそれがいくつもの章に分かれていて、そしてさらに幸いなことに、What I Believe の部の最初の方に私が探していた箇所があった。
このブログの題に関連した用事をまず済ませるために、なぜフォースターにとって民主主義が二唱かという点についてであるが、
Democracy is not a Beloved Republic really, and never will be. But it is less hateful than other contemporary forms of government, and to that extent it deserves our support. It does start from the assumption that the individual is important, and that all types are needed to make a civilization. It does not divide its citizens into the bossers and the bossed ― as an efficient regime tends to do. The people I admire most are those who are sensitive and want to create something or discover something, and do not see life in terms of power, and such people get more of a chance under a democracy than elsewhere. (少し長いが英語は決してむずかしくなく、また翻訳ソフトで簡単に訳せるでしょう。)
要するに、民主主義は完璧ではないが、他のどの政治形態よりもまともで、人民を支配階級と被支配階級に分かつものではなく、その点で支持するに価する制度だと言うのである。
さらにいろいろと説明しているが、その後にフォースターはあっさり二唱の理由を要約してくれていて、
So Two Cheers for Democracy: one because it admits variety and two it permits criticism. Two cheers are quite enough: there is no occasion to give three. Only Love the Beloved Republic deserves that.
多様性と批判つまり言論の自由を認めるのが民主主義だから、それでよろしい、二唱とする。理想的な「わが愛の共和国」などは望めない以上三唱とはいかないが、まあよかろう、と述べており、はい、半世紀余り前にゼミで説明された通りでありました。
これでフォースターが 3 分の 2 を支持する民主主義の話は片付いたので、実はそれ以上に以前から気になっていて、フォースターの叙述と福田恒存の引用で喚起された第二の点、すなわち「人と人の結びつき」に移りたい。
なぜこの言葉に飛びついたかといえば、それこそが名作「ハワーズ・エンド」のテーマだからである。自慢じゃないが、映画化などされずとも私は最初からこの作品が断然気に入っていた。当時あまり知られていなかったことも当方のシケた虚栄心をくすぐった。そういうことってありませんか。他の人たちはほとんど注意を払わないけれど、それだけに自分が価値を知るマイノリティであることが嬉しい、ちょっと得意。
ところがそれが映画化され、それも同じフォースターの「眺めのいい部屋」に続きアイヴォリー・マーチャンダイズ・プロダクションズの制作だという。知る人ぞ知る隠れた傑作なのにと、何だか面白くない。制作会社は資金も人材も豊かだから、さぞかし凝りに凝った風格のある映画に仕上がって、日本でも人気を博すことであろう。チェッである。同好の士なんか欲しくないのだ。
友人の間でも話題になり 4 人で見に行ったが(仏文学系が 2 人で彼女たちはこの小説を知らなかった)、な~んだ、というのが私の印象だった。映画は美しい。どの場面も、その細部も、際立っている。配役もよい。そしてハワーズ・エンド邸のゆかしさ。(写真 1 )

だけど、フォースターの主張が最もシンボリックに、つまり優れて芸術的に伝わるはずのシーンがないのである。そのことに私はがっかりしつつ、ジェイムス・アイヴォリーともあろう人がなぜ大事な場面や暗喩を無視したのだろうと首をかしげる一方で、こちらの積年の思い入れに手が触れられていないことに安堵のような気分もあった。
ここでちょっと白状すると、このブログを書き出して一旦民主主義の件を片づけてから、いさんで小説の方のハワーズ・エンドを語ろうとしたところ、かなり強烈な印象を受けた箇所さえ正確にはその文言が思い出せない。日本の家には古い本があるがそれを送らせることもできないし、第一確かあれはボロボロになっていた、それに字も恐ろしく小さかった、と気づいて、何だ、それならまたMさんに頼めばいいのだ、と取り寄せた次第である。
ハワーズ・エンドを開くと、その題辞は Only connect となっている。「ただ結びつくこと」「繋がりさえすれば」―まさに「人と人との結びつき」を信じたフォースターならではの作品である。
ストーリーの方はウィキの英語版を読めばよいのだが(日本語版は用をなさない)、ごく簡単に概略を述べると、主要な登場人物は英国中流上の家庭のウィルコックス夫妻と、中流で知性派のドイツ系英国人(両親は既に亡く姉妹と弟)、そして労働階級に近いレナード・バスト。ハワーズ・エンド邸の持ち主はウィルコックス夫人で、彼女の存在によってこの美しい館には生命が吹き込まれているのに、夫も子供たちもその価値に気づかぬ凡俗の輩である。
ウィルコックス夫妻とシュレーゲル姉妹が知り合ったのはドイツのハイデルベルク近辺を旅行中で、そのとき姉妹は夫人から帰国後にハワーズ・エンドに来るよう誘われる。弟の病気で二人一緒に出かけることはできなくなって妹のヘレンだけが訪問し、そこでウィルコックス家の下の息子との疑似恋愛があって姉妹の叔母までが介入する騒ぎとなり・・・
後にウィルコックス夫妻はロンドンの姉妹の家の近くにフラット(アパート)を買い、そこで姉のマーガレットに再会した夫人は心通う資質を彼女に認め、やがて重い病で余命いくばくと知った時、ハワーズ・エンドをマーガレットに与えるという遺書を書くが、仰天した家族はその遺志を無視する。
そんなこととは露知らぬマーガレットは、その後寡夫になったウィルコックス氏に望まれて彼の後添いとなるのだが、その間にヘレンはベートーベン(フォースターは絶賛)のコンサートがきっかけで知り合った貧しいレナードと恋仲になって彼の子を宿してしまう。
お腹の大きいヘレンが姉を訪ねると、俗物ウィルコックス氏は当然拒否反応を示す。しかし下層の女そのもののレナードの妻がウィルコックス氏に昔捨てられた愛人であることが分かったり、またレナードの突然の死に長男のチャールスが関与していて逮捕され刑務所行きとなるなど、一族は打ちのめされ家庭は崩壊してしまう。そんな中でマーガレットは自分の人生は終わったという夫を許して保護し、妻のもとで療養生活を送るウィルコックス氏は子供たちを呼んで、ハワーズ・エンドをマーガレットのものとすること、彼女に子がないことから妹のヘレンが産んだ息子にそれを継がせることを告げる。
こうして亡き母の意思が最終的に叶えられたことをウィルコックス夫人の娘たちが不思議がる、このシーンは映画にもあった。
私が読んで気に入った場面はまず、恋愛ごっこの混乱で庭で激しく言い争うヘレンと叔母とウィルコックス兄弟のところに、ウィルコックス夫人がそっとやってきて、その諍いをたしなめるシーンだった。手にはウサギにやる干し草をもって。
ウサギといえば、ずっと後の方で姉妹のもとに隣人の息子トムが牛乳を持って来た時、ヘレンが自分たちを紹介して「他にティビーがいるのよ」と言うと、それをウサギの名前と思った 6 歳に満たぬトムが「ぼくのは垂れ耳だよ」というシーンがたまらなく可愛かった。
もちろんそんな箇所は映画ではカットされているが、それよりも、ヘレンが最初にこの子と会って「坊や、お名前は何ていうの。私の名はヘレン」という場面は残してほしかった。このようなやりとりにこそ、フォースターの望む「結びつき」が示されているからである。ウィルコックス家の人間なら、子供に名を訊くことはあっても自らを名乗るなどあり得ない、と書かれている。そして物語の最終章で、ヘレンの赤ん坊とトムとが干し草で遊ぶ様子を見ながら、彼らは生涯の友となるだろうと姉妹が語る場面は、何かが成就したという幸福感をさそう。
しかし私がアイヴォリー氏の都合について一応は理解しながらも、どうしてこうもあっさり切り捨てたのだろう、と思うのはシュレーゲル姉妹の背景である。その名が示すように父親は英国に帰化したドイツ人で(夫の親戚にも同姓の英国人はいるから不自然ではない)、小説には「英国人がジョークの種にするような」domestic な(今風に言うと「内向きな」)典型的ドイツ人ではなかったとある。
おそらくその家系から姉妹が訪れたドイツの西部でウィルコックス夫妻と知り合うのだが、ヘレンのスキャンダルの発端となったその旅をマーガレットは叔母に語り、ライン川沿いの大司教座の都市で選帝侯の領地として知られるシュパイアー、マインツ、ケルンに言及して、シュパイアーの大聖堂が「元の構造を留めぬ修復によって完全に崩壊していた」ことを嘆く。
当初二十代の私はこれを第二次大戦による破壊からの再建だと思ったのだが、この小説は 1908 ~ 1910 に書かれているからそれはあり得ないとこのたび調べたら、ルイ 14 世時代の1689 年以降 18 世紀末までにこの教会は幾度もフランス軍によって破壊されており、本格的な再建が行われたのは 1846 ~ 1853 年とある。当時の徹底したドイツ式修復は、著しく美意識を欠いていたのだろう。

写真 2 は今日のシュパイアー大聖堂で、「 1961 年には創建当時の姿に戻す修復工事が行われた」とあるから、現在の姿を見ればシュレーゲル姉妹も満足したのではないか。あるいは彼女たちの批判のような内外の声が、本来のロマネスク建築に戻すきっかけとなったのかもしれない。(余談ながら、ここラインラント・プファルツ州出身で 2017 年に亡くなったコール元首相の遺体は自宅からライン川を船で運ばれ、この大聖堂で国葬が行われた。)
シュレーゲル姉妹に流れる血とドイツとの関係は、のっけから―後年の自身とドイツとの縁など夢想だにしなかった時から―私の好奇心を刺激したのだったが、今回読み直してみてますます複雑な気持ちになったのは、上述の「民主主義に万歳二唱」の中の第一部「第二の闇」がナチス・ドイツとドイツ人の批判に終始しているためである。
この部分は 1935 年から大戦を挟んで 1950 年までの時期に書かれており、激情を嫌うフォースターのことだから知的に譴責し上品に嘲笑しているが、それだけに当時民主主義の大敵だったドイツへの彼の怒りは隠しようがない。この本と小説ハワーズ・エンドとをどのように結び付けたらいいのか、私は今すっかり当惑している。
なお、この小説の翻訳では吉田健一のが有名なようだが、そして私は吉田健一の批評や独特な語り口のエッセイは好きなのだが、翻訳家としての彼には疑問がある。というのは、妹に読ませようとして「名訳」の噂高いこの人の翻訳版を取り寄せたものの、その彼女が変な顔をして「読みづらい」というので少し読んでみて、あ、これはちょっと、と思ったからだ。特に会話の不自然な感じは否めない。
それよりは、読んでいないけれど、先日このKBCのフォーラムで話題にした小池滋先生の訳の方がずっとこなれた仕上がりになっているものと期待する。
今回はハワ―ズ・エンドのみの紹介になったが、もう一つの名作「インドへの道」については、松岡正剛の千夜千冊でかなり詳しく述べられているので参考にして下さい。
また、主題がホモセクシュアルの恋愛であることから、当時の世相に鑑みてフォースターの死後に出版された「モーリス」についても、正剛さんは熱っぽく語っています。

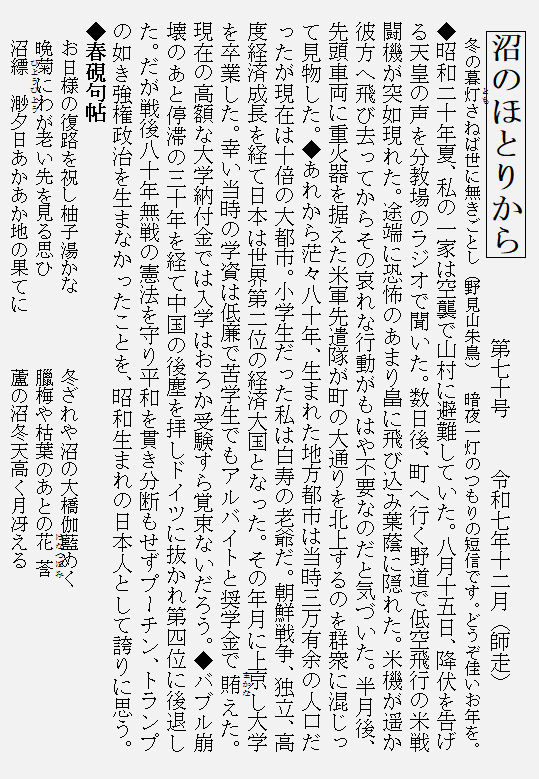


今日1月2日に頂いたメールに「コメントしました」とあったので、先ほど拝見しました。
相当長いですが、改めて確認できた箇所が多々ありました。ありがとうございます。
フォースターの趣旨の一つは異なる階級の融合(という言葉はどこにも使われていなくて、私の解釈)であることは何人かの評論家に指摘されているようですが、これはある意味、当時のインテリ特有の良心的態度で、フォースターも属していたブルームズベリー・グループの特徴とも言えるのではないでしょうか。
私の中にも反資本主義・反権威主義的要素はありますがそれは民草に過ぎない自身の体験から来た恨みであり、また私なりの正義感からでもあるのに対し、ブルームズベリーのハイ・ソサエティの人々が日常の中でそういう体験をしていたとは思えず、そのことがこのグループの文学者(ついでにケインズも)に対する私の反感になっていました。彼らの主張は、結局は豊かなインテリの机上の理論に過ぎないのではないか。(ついでにこのグループのメンバーの多くが女性も含めて同性愛者であったことも、以前には、地に足を付けずとも暮らしていける結構な身分の証しのようにも思っていました。これはLGBTへの嫌悪ではありませんが、それを表に出して弱者の身分を主張することにはやはり馴染めずにいます。というのも、日独ともに親戚に性別が難しい人・どちらともつかない人が思い浮かぶだけでも7,8人いて、それはそれで世間は責めているわけではなく本人たちもちゃんと世渡りできているのに、なぜ今騒ぐのだろう、という疑問があるのです。)
あるとき、今から7,8年前のことですが、私より少し年上の日本人のエリート男性と話していて、学生運動もやったというその彼が「下層の貧しい人たちは、教育のレベルも低くて自分が搾取されていることも知らないし、知っていてもどう表現していいか分からない。だから知識人には彼らの眼を開かせ、表現する術を教える義務があるんだ」と言ったとき、心中で「こういうタイプが私は大嫌い」とつぶやいていました。私は別にそんな指導などしてもらいたくない、あんたの義務を履行させるために貧民・弱者がいるんじゃない、という反発で、きれいごとの人生がここにもある、と感じました。
それでブログでもあえてブルームズベリー・グループには触れなかったのですが、彼らより少し前の世代のウィリアム・モリスなども社会主義に傾倒していきます。この人についても、オックスフォード大を卒業しインテリ上流層の美女を妻とし芸術活動に成功し・・・という恵まれた人生の中での社会主義運動というのに私は懐疑的でした。しかし芸術家としての活動の中で実際に見聞きした職人の苦境や当時の社会の不公平への憤りは、彼の場合は決して偽善ではなく、真摯なものだったと思います。19世紀末の英国社会は研究に値するテーマの一つですね。
ただ、こういう上流社会の知識層は左傾化するにしてもとかく一面的にしかものを見ないので(それで何の支障もないので)、極端なマルクス主義に走ったり、今の世の中だと、先進国や大企業を悪の権化として呪詛したりしますが、見たところの加害者と被害者の本当の姿、人間としてのそれぞれの深部を描くことは、才気あふれる綺羅星の如き現代の作家にとっても極めて難しいようです。
いわゆる流行作家の書くものの中に、時折真実の片鱗を見たり、普遍性とのニアミスみたいな箇所があったりしますが、この人達はもう売文で稼ぐ必要もないのだから、売れる・売れないという出版業界の思惑に左右されず、時間をかけて重いテーマと取り組むことにその才能を発揮してほしいものだとよく思います。
ついでに、わが恩師の訳本をお読み下さるそうで、不肖の元生徒として嬉しい限りです。
ロシアのウクライナ侵攻で、1 世紀歴史を巻き戻されて、このブログで取り扱われている「民主主義に万歳二唱」と「ハワーズ・エンド」のテーマは全く現在の問題としてクローズアップされてよいと思いました。びすこさんが「シュレーゲル姉妹に流れる血とドイツとの関係」に注目して「ハワーズ・エンド」をフォースターのナチス批判と読み合せてみて「すっかり当惑」してしまったこの作品を理解する助けになりそうなウェブサイトがありました。
放送大学の面接授業「映画で読むイギリス小説」の配布資料として岐阜大学の内田勝氏が作成してアップしているものです。もっぱら池澤夏樹個人編集の河出版世界文学全集の(びすこさんが?の)吉田健一訳「ハワーズ・エンド」を使った資料ですが、この入り組んだ内容豊富な作品の早わかりには役立ちそうです。
https://www1.gifu-u.ac.jp/~masaru/09/howards.html
みすず書房版「E.M.フォースター著作集 3(小池滋訳)」は図書館に予約しています。
映画はなかなか見る機会がありません。
小説だけ、あるいは映画だけを見た人は、余り迷うことはないと思いますが、両方を見ていると、やはり小説の深さには映画は適わないように感じることが多々あります。
ただ視覚的な強みというか魅力はもちろん映画の「勝ち」で、私はハワ―ズ・エンドの場合だと、レナードが早朝の森を歩く場面にシビレました。そういう反応の人は多かったようです。だけど字幕には文句を言いたい。これ、一面にBluebellが咲き乱れる森なんですが、字幕は「ホタルブクロが咲く中を」となっていて、ホタルブクロは間違いではないけれど生物の授業じゃないんだから蛍袋とするか、それでは観客に分かりにくいというなら、釣鐘草とした方がロマンチックというもの。花に興味の無い男性なら、蛍袋ってどんな袋じゃ、と思うでしょうが、釣鐘草なら察しがつくでしょう。
花の使い方はさすがアイヴィリ―で、「眺めのよい部屋」では小道具としての矢車草が活きていました。英語ではCornflower、Cornはこの場合には麦やトウモロコシなど穀類のことで、矢車草は麦畑に咲くことが多いのでこう呼ばれるようです。老女二人が「矢車草が好きだわ」というのを聞いたボーイフレンド、いやジェントルマンフレンドがその花を持って訪ねて来る。
でも残念なのは、「モーリス」の中で、私の解釈ではフォースターがシンボルとした月見草が全く登場しないこと。小説の中では何度か月見草の咲く光景が出てきて、月見草は英語でEvening primerose(夕暮れの桜草)といいますが、闇の中に咲く月見草の風情を映像で見せてほしかったのに、なぜか無視されています。ちょっと拘るのは桜草という花のイメージのせいで、これは古くはシェイクスピアのハムレットの中にprimerose path(桜草の咲く径〉という言葉があるのを思い出しました。桜草の花言葉は、昔の英国では若さ故の軽薄とか快楽という意味だったそうで、桜草の咲く径というのはa way of life devoted to irresponsible hedonism, often of a sensual natureと説明されています。「夕暮れの桜草」というと何となく禁断の花みたいなイメージで、20世紀初めのホモセクシュアルの世界を象徴しているような気がする・・・のは当方の勝手な深読みに過ぎないでしょうか。
インドへの道、図書館にリクエストしました…ご案内がなければ巡り会わなかった本ですね僕のようなものでも題名だけは聞いたと言う事はもうそれだけで読む価値があります、ありがとうございました😊