「ブッデンブローク家の人々」感想文(3)―ドイツの黒い森から 70(びすこ)
- クレマチス

- 2025年3月13日
- 読了時間: 17分
ブッデンブローク家のバリエーション:芸術と実業
別にオットー・フォン・ビスマルク伯爵の説を借りずとも日本にも「三代続く長者なし」などという格言があり、庶民はそれを岡目八目的に評したり、ときには富者の凋落に意地悪く溜飲を下げたりする。これは世界のほとんどの国に共通した現象で、これまでどれほど多くの大小のブッデンブローク家が水泡のごとく現れては消えて行ったことか。奢れる平家は久しからずというが、奢らなくても上がったものは下がり栄えた者は衰えるのが世の常である。
私の知り合いに関ケ原の戦いに関わった大名の子孫がいて、中堅企業のオーナーだったが彼の手腕のせいというより景気の循環や世界貿易の変化で傾き、その救済に乗り出した大手自動車会社の意向で退陣を余儀なくされた。その頃にあるパーティで彼に出会ったら、バンコックであつらえたというアップルグリーンのタイ・シルクのスーツを着こなしてバーボン片手に「これから滅びの美を見せてあげよう」などというので、後ろを向いてこっそり笑ってしまったことがある。
しかし実際に、滅びの「美」と言えるかどうかは別として、劇的なものを感じさせる例を私はドイツで知っていたく興味を喚起された。
このドイツのかつての名流富豪の名を知る日本人は、それに関係のある業界の人以外はごく僅かであろう。その業界というのは鉄鋼業で、ほんのこの間まで― 1980 年ごろまでは「鉄は産業の米である」などと国家規模でもてはやされていたのに、今では環境汚染に責任があるとか、これからは脱産業の時代などと言われて、いささか肩身が狭くなっている。しかしアメリカでも、19 世紀後半に未曾有の蓄財に成功したカーネギーなどは鉄鋼業への参画で名を成した。目下トランプにイチャモンをつけられて日本製鉄(Nippon Steel)が買収できずにいる US スティールの創設者が、このアンドリュー・カーネギーである。
時代によって稼げる産業分野は異なり、現代の億万長者(数十億ドル以上の規模)は多くがIT 業界の天才たちであるが、19 世紀から 20 世紀前半までの日欧米では鉄鋼業界が産業の花形であった。ドイツも例外でなく・・・どころかドイツこそはこの業界において数々の画期的な発明で特許を取得し、日本の多くの企業は戦前からその恩恵に浴してきた。
私が社会人となったのは 70 年代前半で、仕事の内容は海外からの技術研修生の世話だったため途上国からの若者たちを連れて廻った代表的な日本企業のうち、最も頻繁に訪れたのは当時繁栄の極みにあった鉄鋼会社と造船企業であった。その鉄鋼会社では、日鉄でも川崎製鉄や日本鋼管でも、テュッセンと並んでクルップという社名を耳にすることがしばしばで、会社の技術者はこれらの名を口にするときあたかも皇家を語るかのような恭しい口調になるのだった。
今世紀初頭の自分の結婚から少したって、わが亭主もその鉄鋼業界の端っこのさらに奥の方に連なることから、彼(か)のテュッセンやクルップは今どうなっているのだろうと調べると、なんと私の知らぬ間に(!)この二つの企業は合併してテュッセンクルップという会社になっているではないか(写真 1 )。合併は 1999 年のことだから古い話ではなかったものの、90 年代の私は違う分野で忙しかったので欧米産業界の変化を知らなかったのである。

そこで改めてこの両社の歴史について調べると、これが大河ドラマ顔負けの面白さで、後述のとおり実際そこからのインスピレーションで作られた映画もある。
まずテュッセンの方であるが、ドイツ西部のアーヘン近くで農器具を作っていたイザーク・ランバート・テュッセン( 1685-1773 )をその元祖とし、彼の曾孫のアウグストの時代に当時プロイセン王国領だったラインラントに鉄鋼所が設けられた。しかしすぐあと 1870 年にそれは売却され、それを資金に同じルール地方※のミュールハイムに圧延工場を建設、これが後のインダストリアル・ダイナスティ〈産業界の王朝〉の礎となる。
(※ルール地方というのは、これも高校時代の世界地理の教科書に出てきたオランダ国境に近いドイツ重工業の中心地で、ここは高炉での鉄鉱石の還元に必要な良質の石炭を産してい
たため鉄鋼業が栄えた。)
ヒットラーの台頭はアウグストの息子の時代で、最初はナチスに協力的だったフリッツも戦争の実態が明らかになるにつれて抵抗し始め、特にユダヤ人迫害に反対してスイスに亡命した後はナチ政権にドイツの資産をすべて没収されている。フランスでナチに逮捕されて妻とともにいくつかの強制収容所を転々とさせられたことは後にいわば彼の勲章となり、またその娘も戦後の復興に尽力したことから、テュッセン家は少なからぬ大企業が裁判にかけられた 1945 年以降も無傷であったが、といってそれだけで世界経済の激変を乗り切れるものではなく、1999 年にはついにライバルのクルップと手を結ぶに至る。
このように今となってはすべてが望ましい方向に作用した「良い子」のテュッセンと異なり、クルップの方は戦後さんざんな目にあって(それも自業自得ではあるが)、それだけにこの一族のドラマはスリリングですらある。
クルップ家の歴史はテュッセンよりも 100 年あまり古く、オランダから移住してきたこの一族の名がルール地方はエッセンの商業組合の文書に初めて見られるのは 1587 年のことだという。従ってこの家族は 17 世紀前半のペストの猖獗もドイツの人口の三分の二を奪った三十年戦争も生き延びてきたわけである。当初は香辛料、ワイン、食料品等を扱う商人で、それによっても財を成したが、やがて鉄鋼業に進出して会社組織とし 19 世紀のアルフレート( 1812-1887 )の時代に大きな飛躍を遂げたのは、継目無し(溶接不要)の鉄道車両用車輪など新規製品の開発力による。
アルフレートの息子フリートリッヒ・アルフレートには女の子しかなかったので娘のベルタに婿を迎えることになり、白羽の矢が立ったのはグスタフ・フォン・ボーレン&ハルバッハという貴族の外交官で、同じく外交官だった父親の勤務地オランダのデン・ハーグで誕生している。1960 年にクルップ家の一員となったグスタフが指揮をとっていた時代はドイツ産業の繁栄期と軌を一にしており、二つの世界大戦においてクルップ社が軍需産業で大儲けした背景には元外交官グスタフの政商としての暗躍があったのだろう。
もっとも第一次大戦のドイツの敗北で、ベルサイユ条約によりクルップも兵器・武器の製造をしばらく禁止された時期があった。
第二次世界大戦後にクルップがニュールンベルク裁判にかけられたのは、戦時中の軍需品の生産に強制労働を用いたためだった。そういう企業は他にも多かった中で、クルップは政府の圧力を受けて仕方なしにというのでなく、むしろ進んでそのような労働力を用いたことから、裁判で有罪判決を受けることは必至であった。大戦中の企業責任者の婿養子グスタフは、戦後には裁判に耐えられないほど衰弱していたため被告席には彼と並んで、あるいは彼の代わりに、息子のアルフリートの姿があった(写真2.手前がアルフリート・クルップ)。

このアルフリート( 1907-1967 )がまさに悲劇の人で、巨額の戦争賠償金を払い、連合軍から刑を減じられて出所した後は企業経営に戻ることができたものの、戦前に結婚した相手が離婚歴のある女性で、息子アルントはアルフリートの母親のベルタの反対で「クルップ」を名乗ることを許されなかった。結局その妻とは離婚するが、彼女が引き取った息子アルントの行状に父親は肝を冷やしたことだろう。無能とか出来が悪いなどというレベルではなく、一種の倒錯者で奇矯な振る舞いが目立ったのである。
アルフリートは再婚するが次子は生まれず再び離婚し、絶望した彼は遂にアルントを廃嫡するという遺言を書く。久離切っての勘当である。ただし息子が生涯にわたって贅沢な生活を続けられるだけの財産を手切れ金と年金という形で与えた。それ以外のクルップ家の資産は彼が設立した財団のものとなった。
(アルフレートという名とアルフリートという名とが混在していてややこしいが、ドイツ語でそれぞれ Alfred、Alfried となっていて間違いではない。)
クルップ家のこの悲劇に飛びついたのがルキノ・ヴィスコンティである。この「赤い伯爵」はアルフリート・クルップの 1967 年の死を待っていたかのように(むろん生前から企画をあたためていたはずだが)、ドイツ・プロイセンの鉄鋼王の男爵一家を巡るスキャンダルをテーマにした映画を製作した。タイトルは「地獄に堕ちた勇者ども」、ドイツ語の題の Die Verdammten は「呪われた人々」という意味である。そのモチーフは「ブッデンブローク家の人々」をベースにしたといわれ、この監督は「ベニスに死す」なども映画化しているからトーマス・マンの世界との親和度が高かったらしい。
もっとも、数百年の歴史を誇り戦前・戦後を通じて世界にその名を馳せたクルップ家と、リューベックの一商人ブッデンブローク家ではそれ自体は比較にならないが、トーマス・マンの小説の底深く流れる一種デカダンスの香りにヴィスコンティは惹かれたのだろう。実業という無味乾燥な世界をヴィスコンティはトーマス・マンとのコラボで芸術に仕立てたともいえる(その芸術性が議論を呼ぶとしても)。
ところでこの章の題に「芸術と実業」と付したのは、芸術化された実業界の例もあるが、ビスマルクのいうように事業で富を成し経済的に安定した名家に、芸術や学問や、とにかく地味な実業界とは異質の道を望む人間が生まれるのは、ある意味で当然のなりゆきだからだ。
そういう人達は必ずしも事業や商売を馬鹿にしているわけではなく、ただ余裕ある暮しの中で別の方面に関心を持ち始める。その好例がかの渋沢栄一の子と孫である。
渋沢栄一は二度の結婚で四男三女をもうけ、当然長男の篤二が後継者と目されていた。しかし妻子ある彼が芸者との醜聞を起こして離婚したとき、お家騒動を避けるため直ちに家族会議が開かれ彼の廃嫡が決まった。息子はほかにもいた中で栄一が家督相続人に指定したのは、まだ十代の若者だった篤二の長男・渋沢敬三であった。敬三はそれを拒むことはなかったものの、動物学や農学に興味があって帝大に進むことを渋るが、栄一に懇願されて大学を出たあと祖父の意に沿った道を歩むことになる。この人の凄いところは、しっかり仕事に打ち込み責任を果たしながら、若い頃の柳田国男との出会いで目覚めた民俗学への関心を終生保ち続け、また動物学・植物学などの分野で博物館を開設するなどして、数多くの研究者を養成したことである。
彼の叔父にあたる渋沢秀雄は栄一が最初の妻の死後に娶った兼子との間の子で、彼もまた多才な男であった。栄一の息子として複数企業・団体の要職にあったが戦後 GHQ による公職追放の憂き目にあうと、チャンスとばかり趣味の世界に没頭する。齢 50 代にして離婚してそれまで長年囲っていた芸者と結婚するなど女性関係が華やかだったのは、何人もの妾をもち正確にはその数が分からないほどの子供を生ませた父栄一の血というべきか。
その辺りの事情は鹿島茂の「渋沢栄一:上・算盤篇、下・論語編」に詳しい。鹿島茂は特に秀雄の文才に注目し、栄一に関する数々の伝記やメモワールの中でも秀雄の「父・渋沢栄一」から最も多くを引用している。それによると、秀雄は帝大に入るものの法学の勉強が厭になり、フランス文学に転科したいと言い出した。そのとき栄一は穏やかにしかし明確にこう諭した。
「お前は法科を卒業して、将来事業界に働くだけの能力を持っているのだから、今の科程をつづけて実業家になってくれ。どうか文学は趣味の程度に留めてくれ。ワシが頼むから、是非そうしてくれ。」
後年このやり方は、孫の敬三が旧制高校の理科を選びゆくゆくは帝大の理学部に進みたいと言ったときにも用いられて効を奏している。敬三の息子雅英が語る父の言葉によると、「命令されたり、動物学はいかんと言われたりしたら僕も反発したかもしれない。おじいさんはただ頭を下げて頼むというのだ。七十いくつの老人で、しかもあれだけの人に頼むと言われるとどうにも抵抗のしようがなかった」
上述のアンドリュー・カーネギーとは血の繋がりのないデール・カーネギーの有名な著書に「人を動かす」というベストセラーがあって、私は 60 年ほども昔に父が読んでいたのを記憶しているが、こちらで何年か前に夫の工場に研修に来た若いカナダ人が父親に勧められたと言ってそれを読んでいるのを見て驚いた。何というロングセラーであろう。
だが、さすがに渋沢栄一、そんな啓発書など読まずとも人の心を掌握する方法を十分に心得ていたわけである。またその息子も孫も立派なもので、逆らうことなくしかし自分の意志を貫徹する術を知っていた。
これはおそらく曖昧さを許容する日本文化の中でこそあり得る事態で、黒白をつけることを強いられる西洋文化においては難しいかもしれない。日本人はのらりくらりとして不気味などという批判もあるが、水が器の形に従うごとく与えられた状況に沿って生きるのも一つの力である。だからこそ、日本の往時の財閥や富豪の多くはある日突然途ぷつりと切れるのでなく、静かに姿を消していくことができるのであろう。そしてそれもまた滅びの美といえるのではないか。
愛しのトーニ
ブッデンブローク家の長い物語は、「それなあに、それなあに」というトーニことアントーニの質問で始まる。玉虫色の柔らかい絹の服を着た 8 歳のきゃしゃな金髪娘は窓辺の祖父の膝に寄りかかり、傍らの長椅子には祖母と父母が座っている。1835 年のことである。
この幸せそうな光景はトルストイの「アンナ・カレーニナ」の有名な冒頭の言葉を思わせる。「幸福な家族はみな同じように幸福だが、不幸な家族はそれぞれに不幸である。」幸福の典型のような家族の真ん中にいたトーニを待ち受けていた苛酷な運命を、この時点でだれが予想できただろう。
町の裕福な商家の娘という以外は特に取り立てて言うほどの特徴もない女の子で、長じても才能・才覚を発揮するわけではなく、育ち方も日頃の言動も全く普通の娘。けれどもその彼女が嫌悪する男との結婚を父親に強いられて半病人のようになる辺りから、私は彼女が好きになった。
それはトーニが普通のありふれた娘だからである。彼女の心の内も周囲への反応も、同性としてよ~く分かる。それは、第一に私自身が平凡な並みの女だから。そもそも小説の中でこういう女主人公は珍しいのではないか。そしてこういう登場人物が読者から好意を持たれるということも、あまりないように思われる。
求婚者を拒否し続けて、一夏を保養地で過ごせば気も変わるだろうと父親から送り出されたトラーヴェミュンデで、彼女は休暇で帰省中の民宿の息子と出会い恋に落ちる。(この二人の逢瀬が美しい。)そこで駆け落ちでもすれば情熱的なヒロインということになるのに、父や兄や気色の悪い求婚者にその初恋を阻まれて手も足も出ないという情けなさ。時代が、環境が、それを許さないということなのだが、これではどこにでもいる何の取柄もない娘ではないか。これでどうして主人公(の一人)なのだ。と思いながら、私はそれを責める気になれないのだった。
最初の夫グリュンリッヒの詐欺が露見し、責任を感じた父親に連れられてハンブルクからリューベックに戻ったトーニは、町の人々の悪意と好奇の目や幼い頃から仲の良くなかった同年配の女たちの「いい気味」と言わんばかりの態度に落ち込む。自分の母親に辛かった結婚生活を語ろうとしても「そんな話やめて」と言われるし、父や兄を相手に愚痴を言うこともできない。(この母親がこういうときフランス語を使うのも厭らしい。テレビドラマで配役が気に入らなくて嫌いになっていたこのコンズリンに、私はますます反感を持つようになった。)
しかしさんざん酷い目に遭ってからのトーニの反応がユニークである。悩んだ挙句の結論は、それならばこれからは、結婚に失敗した敗者としていっそ徹底的に哀れな薄幸の女を演じてやろう、というものだった。同時に、誰に出会っても背筋をしゃんと伸ばして威厳を失うまいと誓う。なるほど、こういう緩和策(解決策ではない)もあるのかと感心してしまった。新聞雑誌の身の上相談で同じような境遇の女性から助言を求められたら、これを答えにするのも一案である。(もっともそんな相談を持ち込むのは一世代・二世代前の女性だろうが。)
二度目の結婚の失敗もこのやり方で乗り切る。グリュンリッヒとの間に出来た娘エリカの結婚の悲惨な結末(その夫は保険詐欺で有罪となる)にはさすがに打ちのめされ、兄のトーマスの早い死や可愛がっていた甥のハンノの夭逝に、自分は神から罰せられているのかと嘆きつつ、最後まで残るブッデンブローク家の人間は彼女である。
何か厭なことがあるとすぐに意気阻喪するが、そのくせ何らかの形で自分をダマシダマシしてもとにもどるのは、今でいう「レジリエンス」というのともちょっと違う。こういうところが「いるいるそういう人(自分も含め)」という感じで共感を誘うのである。そしてトーマス・マンのように、私などとは生きる世界がまるで違って天と地ほどの隔たりがある人間が、こんなにも自分に近しい登場人物を創造したことを不思議に思う。しかもこれを書いた当時のマンはまだ 20 代前半であった。
最近は見かけないが、私の若い頃にはいろんな雑誌で著名人が「好きなヒロイン」について語る記事があった。(今もそういう特集があるかとネットを見たら、あるにはあったがほとんど全部がアニメの主人公で、腹が立つやら呆れるやら。)私が覚えているのは、「カラマーゾフの兄弟」のカチェリーナとか「戦争と平和」のナターシャとか、日本の小説では漱石の「行人」の三千代がいいという学者もいた。
そもそも世の小説家の多くは男性で、女流がこれだけ増えてもやはり少なくとも半分は男性である。昨今は文学賞にしても読者層と宣伝効果を考えて男女のバランスが重視されるという。しかし私が読むようなちょっと昔の小説などは断然男性のものが多く、明治・大正・昭和初期の小説となるとなおさらである。そのためかどうか私などが読むと、男の勝手なイメージで作られた不自然な女性が多くて閉口する。男の身で女の本性が分からないのは当然であり、女の書いた女の方がリアリティがある一方で、その場合は男の登場人物が何やらしっくりしない。
ただし女流作家による男の登場人物たちはどちらかといえば女の添え物的存在で、実態とのずれはさほど気にするほどのものでもない。それに対して男の描く女はかなり大きな役割を担っていることが多いから、「女はこんなこと考えないわよ」「こんな女が現実にいるものですか」と思わされることがしばしばである。
上記の「好きなヒロイン特集」でも、当時答えていたのはほとんどが男性だった。ごく最近の傾向はさておき、ある時期に中年男に大人気だった某作家の小説などは、男のためのお伽噺として読めば面白いのだろうが、私のような凡庸な女にはアホらしくていずれもまともに読み通したことがない。
それで私が好きな女主人公は誰かといえば(そんなことを訊いてくる人はいないだろうけれど)、少数ながら実在しそうな女性として感じるところがあったのは G. エリオットの「ミドルマーチ」のドロセーアだろうか。同じく女流作家のエミリー・ブロンテによる「ジェーン・エア」は今でも女性に結構人気があるらしく何度も映画化されているが、この一人称の作品はしがない身分の著者の「こうなれたら」という夢を語っているようで、「われ褒め」みたいなところもあり、どうも感心しない。
学生の時この作品の一部を講読する授業があって、担当した女性の教授はブロンテを好きでないらしく(まさか私と同じ理由ではなかろうが)、最初の授業でいきなり「ジェーンは器量も悪いし頭だってどうってことないのに、プライドばかり高くて、皆さんみたいね」と言い放ち生徒を唖然とさせた。今どきの授業で教授がこんなことを言ったらどうなるだろう。しかし団塊世代の私の学生時代には大学生など「なんぼでも」いて、高い授業料を払っている私立大においてすら生徒に大した値打ちはなく、学校側は生徒に言いたい放題であった。
話を戻して、私が一番好きなヒロインはジョセフ・コンラッドの「ノストローモ」のグールド夫人である。南米の銀山に取り憑かれて「物質的利益」のみを追求するようになった夫を哀しく見ている悲劇の女性。この小説は(Nostromo, 1904、『ノストローモ』 上田勤・日高八郎・鈴木建三訳、筑摩書房〈筑摩世界文学大系50〉、1975年)、かの名監督デヴィット・リーンが映画化を考えていたそうで、彼の腕をもってすれば「アラビアのロレンス」や「戦場にかける橋」を超える大作が生まれたろうに、企画中に物故してしまって残念でならない。
とまあ、話が逸れたが、要するに私が言いたかったのは、トーニのようなタイプの同性には今まで惹かれたことはなくて自分でもちょっと驚いたということ、そしてその作者がよりによってトーマス・マン―それも若き日の―であることだ。もしかしたら、こんな等身大の異性を無理なく描くことができたのは、彼の中の同性愛的嗜好によるのかもしれない。典型的な「男」ではないから、男好みの嘘っぽい女にならなかったのではないか。
ともあれ、トーニとは気安い友達になれそうな気がする。彼女と知的な会話なんかできなくても構わない、「風景の部屋」でご近所の噂話などして笑い転げたい。

(最後の写真はTVドラマ「ブッデンブローク家の人々」の登場人物。真ん中の女性がコンズリン、右側がトーニ、左側はトーマスの妻ゲルタ)

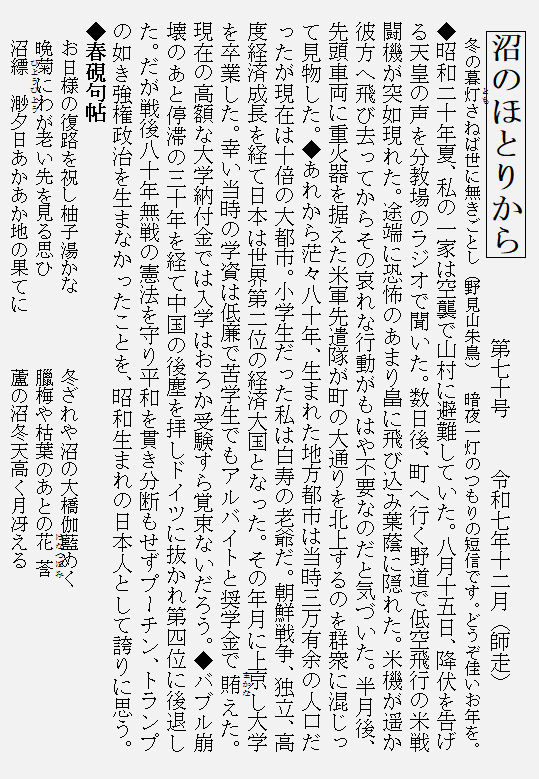


語りのリズムの小気味よさと、所々わかる。所々わかりにくいけど、ついていける。このバランスがとても良いせいか、一気に読み通せました。
もちろん、出版されれば真っ先に買います。続きを読みたくなるような組み立ては技巧の問題で問題ではないだろうなとすでに刊行が待ち遠しい位です。
今回のびすこさんのブログ送信メールはとても面白かったので、管理人の独断で一部編集して以下に転載させていただきます。なお明日から少し東京を離れますのでご了解をいただく時間がなく、本文でも一部改竄させていただいた部分があります。ご容赦ください。
Cさま
・・・
昨日は東日本大震災・津波から 14 年で、日本の新聞であまりちゃんと取り上げられていなかったのは、来年が 15 年だからその時に特集をということでしょうか。今は歳月の流れがおそろしく速くて、10 年ひと昔というより 5 年、3 年でもう昔の事になってしまうので、15 年目にはあの大災害の記憶もいささか風化しているかもしれません。
ひと昔、と言えば、このところ、既に読んだ遠藤周作のエッセイを読み直していて、改めて感じたことがありました。これは 1996 年に亡くなったこの作家が 80 年代後半から 90 年代の初めにかけて記したものですが、そこには欧米、とくにヨーロッパ、その中でも彼が留学経験のあるフランスに対する礼賛と、それと比較しての日本の公共心やモラルの欠如が強調されていますが、今のフランスを彼が見たらどういうだろうか、と考えてしまいました。
フランスのほとんどの町の汚さ、国民の倫理道徳の無さ、エリートの独断、庶民のヤケクソ…フランス人が東京に来て整然としていてゴミが落ちてないことに驚き「映画のスタジオみたい」と言ったという話が伝わっていますが、遠藤周作が亡くなって 30 年近く、ほとんど一世代分が過ぎ、欧州は昔の面影がないほど変わってしまいました。生きていれば今年 100 歳前後になる日本人世代の欧米観は、ほとんどが「無効」になっています。
私が一番戸惑うのは、秩序、清潔、法の順守などという「普遍的」と考えられていた徳目がほとんどの先進国でバカにされていることで、英国、フランスもですが、その中で保守的とされたドイツが特に今はそれらを恥じて「自由」の名の元に好き放題に走っていることです。尤も元来が真面目な人々だったはずなので、羽目の外し方が堂に入っているフランスやイタリアと異なり、何をしてもぎこちない。なぜ自国の歴史や伝統にもっと誇りを持たないのか。ナチスの蛮行を恥じることが自国の否定につながっている昨今の風潮には、痛ましさすら感じます。
現在ドイツでは CDU/CSU と SPD による組閣のための予備談義が行われていますが、数々の障害にぶつかって前途多難です。先の選挙では 3 分の一が極右・極左に投票したため、国会で 3 分の 2 を要する重要な案件が決められません。欧州全体の命運もトランプの脅しで危険に晒され、今は防衛問題が最大の課題となっている中、フランスが自国の核を欧州のための「抑止力」とすること(つまり核開発・製造の費用を EU=ドイツに支払わせること)を提案するなど、フランス・ファーストの本性がむき出しです。一方ドイツは戦車や砲弾の製造においては他の国の追随を許さないだけに、その利点を阻もうとする他国の動きもあって、欧州防衛政策も到底一枚岩とは言えません。
皮肉なことに、防衛費の増大でラインメタルなどの軍事企業や、さらに今回のブログで言及したテュッセンクルップ社などの株価が上昇、軍備品の製造となれば工作機械の需要も増大しますのでDMG森精機(DMG MORI)などのメーカーは期待に胸を膨らませている気配です。DMG森精機は夫の会社の顧客でもあって、この種のニュースには私も個人的に関心を持っています。軍備拡張での儲けなど不謹慎と言われるでしょうが、このところ自動車産業が大きく傾いてその代替産業が見当たらないドイツで、経済復興のための当面の「希望の星」が軍需というのは事実です。
・・・