幾年ふるさと――ドイツの黒い森から 30(びすこ)
- クレマチス

- 2022年1月22日
- 読了時間: 12分
昨年末にタカコさんの遺品として頂戴してきた本の中に丸谷才一の随筆集*があり、それを寝転んで読んでいたら「幾とせ古里きてみれば」と題したエッセイに出くわして、思わず起き上がってしまった。
善くも悪くもびっくりした理由は、私が子供の頃からもっとも好きな唱歌の一つが「幾年ふるさと」で始まる「故郷の廃家」で今でもよく口ずさむのだが、殊にも意外だったのは丸谷才一という作家・評論家がそれを取り上げたということだった。
丸谷才一といえば学識豊かな都会的インテリ(生まれは山形県の鶴岡市だが)の代表で洗練された洒脱なスタイルを旨とし、故郷を恋う明治・大正の感傷的な歌などとは無縁の人という気がしていた。文学にも音楽・美術にも一家言どころか三家言も四家言もあって、乳臭い小学唱歌なぞ洟も引っ掛けないというイメージがある。
*『猫だつて夢を見る』文藝春秋1989年10月25日刊、のち文春文庫。
しかし私が驚いただけあって、丸谷氏は何もこの歌への思い入れがあったわけではなく、全く別の件でその歌詞に興味を抱いたのだった。そもそもの発端は著者が中国人による日本語の悪口を何かの記事で目にしたためで、その中国人は日本人がよく使う「数日」「数人」などという場合の「数」が実に曖昧だと批判し、中国語なら「数」といえば大体 7 くらいだと述べていたという。
その意見が斬新だと思ったので、丸谷氏は何かの会合(もちろんインテリ集団)の席で参加者に「数年」や「数人」の「数」とはいくつくらいと思うかと尋ねてみた。そんなこと考えたこともない、という人が多くてまともな反応は得られない中、「いくつか」を意味するとされる単語(の一つ) several は seven に関係あるのでは、という意見に丸谷氏は感心したらしいが、これは完全に間違い。私の調べたところでは、むしろ「分ける」「隔てる」を意味する sever に由来するらしい。
ともかく実のある回答はなかったため、次に丸谷氏はさる有名女子大で英語を教えている英国人のナントカ・キーン教授(ドナルド・キーンではない)に英語で数年、数個、数枚などという場合の、あるいは日本語の「幾つか」にあたる、few, several, some にはどんな違いがあるのかと質問したそうだ。丸谷氏は東京大学文学部英文科の卒業生だしどこかの大学で英語を教えていたこともあるからそれなりの知識と確信はあって、fewなら 2, 3 、severalは 5, 6 だと信じていたらしい。
別に大学でなくても、中学校でも高校でもそう習いますよね。東大とは無縁の私だって丸谷氏と似たり寄ったりの理解だった。few はせいぜい 3, 4 個かな、とか、several は 5 から 8 くらいまでだろうとか。
ところがそのキーン先生から返ってきた答えは全く予想外で、few (a few) は 5 か 6 か 7 、several は 13 か 14 だと言ったそうな。some というのははっきりしないとき、あるいははっきり言いたくない場合に使われるのだろう。
となると丸谷先生の理解は長年間違っていたことになり、その間違いをもとに英語を教えていたわけだから、正解を聞いた同氏はいたく驚き狼狽し意気消沈した(その教えで実害を受けた学生はほとんどいないと思うが)。
茫然としている彼を慰めんとしてキーン先生は、暗示される数のほどは「時と場合による」と言い、50 歳・ 60 歳の人がセヴェラル・イヤーズ・アゴウと言ったら 13 年前か 14 年前だが、6 歳か 7 歳の子がそう言うなら「それは 2 年か 3 年前のことでせう」と宣まった由。
子供の記憶でセヴェラルが 2, 3 というのはジョークだろうが、しかし私はこのキーン先生の説には頷けない。英国人の英語の先生に異議を唱えるなんて不遜の極みと言われても、これまで読んだり聞いたりした例から(70 代も半ば近いと例は無数にある)、違うだろ、それは、と言いたくなる。
例えば英語で the fortunate fewという表現があって、これはもちろん「幸運な少数の人々」という意味であるが、まさか 2, 3 人とか 5, 6 人ということはない。人口が一億数千万人にのぼる現代日本で幸運な少数の人々、というなら、少なくとも数万人はいるだろうよ。また 50 歳・ 60 歳はともかく、20 代の人がセヴェラル・イヤーズ・アゴウと言えばそれは多分 7, 8 年前、少なくとも 10 年以内のことだと思う。これが 70 ~ 80 歳だと、さらに朧な記憶でも「まあ、いいか」となる。
序が長くなったが(ごめんなさい、ここまではメイン・テーマじゃないんです)、丸谷氏はその後もしつこく「数」「幾」に拘っているうちに、「幾とせ古里きてみれば」という唱歌の一句を思い出し、その歌がヘイスというアメリカ人の原曲を日本の犬童球渓が訳したものであることから、英語ではこの「幾とせ」を何と言っているのだろうと知りたくなった。
ところが原曲 My Dear Old Sunny Home のもとの歌詞がどこにも見つからない。それで今「探索中」だからしばらく待って下さい、と結んでおいて、その後記として「やっぱり見つからなかった」とある。
丸谷氏のこの随筆集の初刊は 1988 年頃なので、今のようにインターネットの力を借りることもできず、当時の唱歌の専門家たちに訊いても分からず、結局「研究と言うのはどうも大変なものです」とギブアップするしかなかったのだろう。
しかし今は違います。私はわりとカンタンに見つけた。普通はヘイスという名前を入力して探すのだろうが、まずヘイスの綴りとフルネームが分からない。それで YouTube でこの歌の英語版を聞こうとしたけれどどこにもない。
ところが韓国語版の画面に英語の歌詞が出て、初めの部分だから「幾とせ」が Many years ago であることがすぐ分かった。なーんだという感じ。そうだなあ、それなら 14, 5 年昔の記憶か。丸谷さんは 6, 7 年でこんなに(歌詞にあるように)荒れるはずはない、と言い、 10 年以上は経っているだろうと推測しているが、いや、日本語の歌詞は必ずしも原文に忠実とは限らず、第一英語の題名も「わが懐かしき陽の当たる家」で、「廃れた」とか「荒れた」という形容はない。
ただし、日本語版は犬童球渓による意訳とばかりもいえず、「昔を知る人もいず、鳥も歌わなくなった故郷を寂しくさまよう」などと雰囲気としては似通っている。やっぱりこれなら 10 年以上昔に故郷を出たのであろう。ちょっとその出だしの節をご紹介。
Where the mocking bird sang sweetly / Many years ago / Where the sweet magnolia blossoms / Grew as white as snow----.(その昔モッキングバードが優しく歌い、麗しきマグノリアの花が白い雪のように輝いていたところ・・・)
モッキングバード、日本語でマネシツグミについては、60 年頃に日本でも流行った「モッキンバード・ヒル」、それもパティ・ペイジのカバーが私は好きだったので耳に馴染んでいた。全米各地にいる鳥だそうで、アメリカ人の郷愁を誘うらしい。
そのあとの「雪のように白いマグノリア」であるが、これは米国なら泰山木のことではないかと私は思い、作詞者はもしかしてバージニアかその南の人ではないかと想像した。この州で泰山木の並木道を見たことがあるからだ。泰山木は一般に暖かい気候を好む。しかし調べてモクレン、コブシなども米国ではマグノリアというと分かり、コブシなら「北国の春」にも咲くから、はてこの歌の舞台はどこだろうと考えているうち、ヘイスはケンタッキー州の出身と判明した。この辺は古き良き時代の長閑な田舎というイメージで、確かに懐かしい故郷としての諸条件を満たしてもいる。
さて、韓国版「故郷の廃家」でヘイスのフルネームがウィリアム・シェイクスピア・ヘイスであることも分かったが、シェイクスピアというのはどうやらあだ名、または通称らしい。若いときから文才を発揮していたから、こう呼ばれるようになったのだろう。
ここで問題。さっきから原詩を知るのにヘイス、ヘイスと繰り返しているが、ヘイスって作曲家じゃないの。岩波文庫の「日本唱歌集」にも「原曲はヘイス作曲の・・・」とある。となると、さっきのマネシツグミだのマグノリアだのという歌詞は誰が作ったのか。
フルネームが分かったので英語のウィキを見てみると、このヘイスの肩書は今日でいう作曲家(composer)ではなく、ソングライターとある。当時から一人で作詞も作曲もやってのける人間をこう呼んでいたようだが、ソングライターというと何となく芸能人的なニュアンスがあるらしい。いわゆる作曲家という職業が確立されていなかったという説明もあるが、このヘイスの「故郷の廃家」と並んで日本人に愛されてきた「旅愁」の作詞・作曲家であるオードウェイの場合は poet/composer とされており、彼は医師であり政治家でもあって社会的地位が高かったので、軽い響きの「ソングライター」では失礼とアメリカ人は考えたのだろうか。
ついでにアメリカ人の唱歌作曲家として日本で知名度の高いスティーブン・フォースターもソングライターという肩書になっていて、かの「夢見る人」や「おおスザンナ」、「オールド・ブラック・ジョー」など全部自分で作詞・作曲したらしい。肩書はどうあれ、アメリカでは 19 世紀から 20 世紀初めまでは作詞と作曲の分業はなかった、というより、ハイネの詩にメンデルスゾーンが作曲、なんていうドイツの場合とは違って人口に膾炙した名詩はなく、また「こんな詩を作ったので曲を付けてくれないか」などと誰かに依頼する仕組みにはなっていなかったようだ。
それにしてもヘイス(「冬の星座」も作詞・作曲している)といいフォースターといい、その才能には感嘆させられる。いや、こういう人は実は現代日本にもいて、ちょっと昔の人だが米山正夫がその好例。彼は私の好きな「山小屋の灯火」や「津軽のふるさと」を作詞・作曲している。美空ひばりの歌にはとんと関心がない私も、「りんごのふるさとは~」の歌だけはよく聴く。
とまあ、19 世紀のアメリカで音楽家が置かれていた状況を垣間見ることになったのだが、その情報源となったのが韓国版さらには中国版の唱歌を聞かせるYouTubeで、私にとってそれには別の感慨があった。
結論からいうと、日本の雅楽とかヨーロッパの宗教音楽等は別として、大衆が歌う唱歌・演歌の分野に関しては「東アジアは一つ」と認識させられたのだった。歌詞は当然違うけれど、題名に見る限りそれらのアメリカの歌を聞いた韓国人や中国人が抱いたイメージはいずれも、日本人のそれとよく似ている。
明治時代に独・英・米の歌をいち早く輸入したのは日本だったから、隣のアジア国には日本を経て伝わったのではないか。日本ではほとんど歌われなくなった「仰げば尊し」(作曲は外国人らしい)が台湾で好まれているのも、その一例であろう。
ろくに調べもせずに日本経由と考える根拠は、小学生の頃に私が聞いた朝鮮語の「うさぎとかめ」の歌である。級友の一人のお父さんが戦前・戦中に朝鮮総督府(無論当時は「朝鮮にあった日本のお役所」程度の認識)で用務員のような仕事をしていたそうで、「うちのお父さん、もしもし亀よの歌を朝鮮語で歌えるんよ」と彼女が自慢そうにいうので、遊びに行ったときねだって歌ってもらった。(すみません、その頃は韓国という国名はあまり聞かれず、朝鮮語とか朝鮮半島という言葉は「事実」として使われていたので、差別という意識はなかったのです。まして子供には。)
そのお父さんが言うには、当時は日本の歌を朝鮮人と一緒によく歌ったそうで、またそれらを朝鮮語に訳して日本人がその歌詞を覚えることもあったという。今回韓国語の「故郷の廃家」を聞いて、この歌もそれらの中の一つだったのかもしれないと思い当った。
それとの関連で私がやっぱりと感じたのは、「旅愁」(原題は Dreaming of Home and Mother:故郷と母を夢見て)の作詞・作曲者オードウェイの英語版ウィキを見た時で(日本語版はない)、そこには次のように記されている。
<Dreaming of Home and Mother (1868) was a very popular sentimental song of the Civil War era, and continues to be played; it is popular in China, Japan, Korea, and Taiwan in translated versions.
「故郷と母を夢見て」は南北戦争時代に大きな人気を博したセンチメンタルな歌で今も演奏され、中国、日本、韓国、台湾ではその翻訳版が愛唱されている。>
誰が書いたのか知らんが、センチメンタルとは妙に見下した表現だ。丸谷氏タイプの知識人か。しかしオードウェイがウィキに登場するのはまさに東アジアでの人気のゆえで、我々に愛されていなければこの音楽家は自国でとうに忘れられていたはず。
そしてさらに面白いのは、このウィキの中国語版があることで、そこには次のように記されている。
佢喺中國嘅版本《送別》同日本嘅版本《旅愁》嘅翻譯版本都好受歡迎
中国語は理解できなくても、おおよその意味は分かりますよね。中国語では「送別」と題したこの歌の日本語版が「旅愁」であることを記して、「都(いずれも)好受歓迎」とある。
こんな良い歌がわが国で広く知られるようになったのは日本のおかげです、なんて声は中国でも韓国でもまず聞かれないという事実は別として、東アジアの人々の情感がかくも似通っていることは喜ばしい。何だかほっとする。
だいぶ前にサミュエル・ハンティントンという人が「文明の衝突」という本を出して大きな話題になった。私は少し読んだだけで全く気に入らずすぐ投げだしてしまったが、その理由の一つは、この学者が文明と文化を正しく定義づけていないという点にあった。そして「日本文明」を独特のものとして中国ともインドとも異なり当然西洋のそれとも別物という扱いをし、そのことを満更でもないと感じた日本人もいるようだが、この種の著書を読んで苛立つのは、その国の一般民衆・庶民(こういう言葉もあまり好きじゃないけど)に関心を向けることなくインテリの皮相な論理で偉そうに御託を並べている点である。
ところで今回のふるさとに関連した写真だが、一つは日本の我が家から見た風景で 2020 年、2 年近く前の春に撮ったもの。この年の 2 月にコロナが日本にも欧州大陸にも上陸して私は日本から離れられなくなった。冬の間シューベルトの「春の夢」を聴きながら、手術後の治療もすっかり終わる 3 月にはドイツに帰るんだ、と思っていたのに、それが叶わなくなったときの失望といったら。
古い日本建築の我が家は暖房が効きにくいため冬の間は寝室と居間の間を行き来するだけで、閉めきってあった北の部屋の窓を開け放ったときは桜も終わり新緑の候になっていた。塀のむこうに田んぼと畑が、そしてそのさらにむこうに緑の山並みがあって、私はフランクフルト到着後に空港から南に向かう途上で目にする景色を思った。

アウトバーンを降りてシュヴァルツヴァルト地域に入ると道の両側にはリンゴとサクランボの果樹園や麦畑が広がり、遠くに黒い森の連山が見えてくる。
日本の家は北緯 33 度にありドイツの住居は北緯 48 度の地にあるから、気候も風景も大きく異なるが、山々の遠景はよく似ていると最初に言ったのは夫であった。二つのふるさとに再会する嬉しさの裏には、それらと別れるときの寂しさがある。日本にいればドイツが、ドイツにいれば日本が、恋しくなる。常にない物ねだりをしているワガママ婆だ。
二つ目の写真は夫の母が最晩年を過ごした家で、姉と兄には祖父が大きな家を残した一方でいわば「出来損ない」として無視された夫は、この亡母の家が欲しくて姉・兄の計三分の二の権利を買い取った。小さな小屋だからさほどの費用もかけず改築し、休暇には私たちがのんびり過ごす家となっている。
ヘイスの歌の原詩風にいえば、<春の朝キツツキが忙しく森の樹を叩き、木々の下で野生のアネモネが花開くところ>ということになる。このアネモネは夕べには花びらを閉じる。
どちらの家も、自分たちの目の黒いうちは(夫のそれは灰緑色だが)「廃家」にはならないであろう。多分。


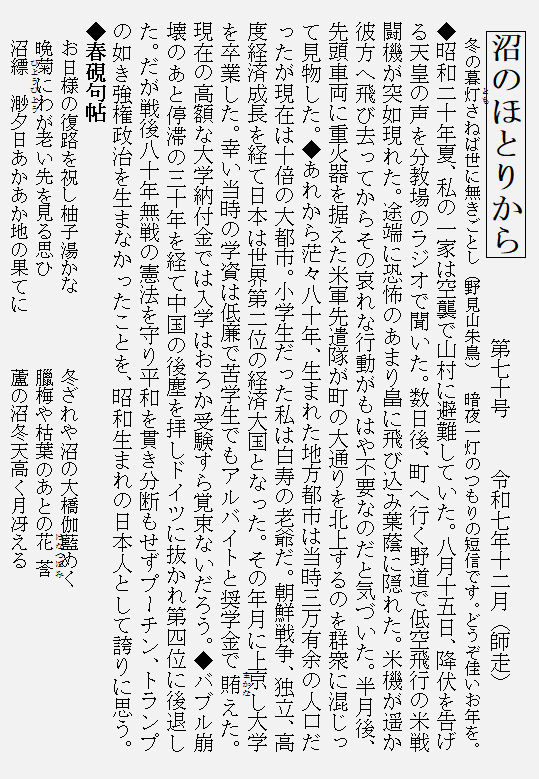


補助金とか助成金の話は田舎でもよく出ます。そのことで「もらえるもんは全部もろたらええねん」という愚弟と大喧嘩になったこともあります。そういう根性が気に食わんのだ。助成金たって、もとは市民の税金じゃないか。
そもそも我が家の改築・補強はいずれ必要と覚悟していましたが、東日本大震災の2年ほど前に市が「耐震診断を受けませんか、市から助成金が出て診断費はほぼただです」と言って来たのです。私は「ははあん」と無視していたのですが、愚弟が「ただならやってもらおう」と勝手に申し込んだ。市内の建築事務所が私の留守にやって来て調べて「地震で倒壊する可能性は80%、大々的な工事が必要」という結果を愚弟に渡し、この阿呆は慌て腐っている(私が死んだらこの家は自分のものになると勝手に信じているから)。
それを聞いた、わが家に出入りしている工務店が、さあ、怒った怒った。母屋の屋根も軽くし梁も補強して、ちょっとやそっとの地震では倒れないようにしてある、80%なんてありえない!
調べて分かったのは、市が建築事務所と結託して古い家を診断させ、倒壊の危険を強調して耐震工事をさせる。建築事務所はそれで仕事を手に入れ、市に入る税金も増える。
私はこのやり方が全く気に入らないので診断書を建築家である元同僚のご主人(神奈川県在住)に見せたところ、これは安物のソフトウエアで通り一遍の診断をするだけなので、9割以上の家が「耐震工事が必要」という結果になる、そうなるように造ったソフトともいえる、とのこと。
しかし一部耐震補強が必要なことは私にも工務店にも分かっていたので、この際キチンと、と思って、そのご主人を通じ木造建築専門家を関東から呼んで診断してもらいました。もちろん工務店立ち合いのもとで、紹介してくれた建築家までが同行してくれました。
床下から天井裏まで徹底的に調べ、数か所の補強を指示されましたが、蔵の方にはそれまで手を付けてなかったので、大々的に修理することを勧められ、工務店は喜んで引き受けてくれました。因みにこの工務店は私が見つけた高知市の企業で、私の郷里の市とは関係ありません。そのことも市当局は気に入らなかったようで、ぶっちゃけ、脅して市内の建築事務所を使わせようとしていたわけです。
そんなわけで助成金はもらいません。市の世話にはなりません。タダほど怖い物はないから。
追記:
いちまるさんは建築にもお詳しいようですので、ちょっと耐震工事の一部をお見せしています。日本の家は、そこで婚礼も葬式もできるように、襖を取っ払えば広間として使える構造になっています。そのため真ん中に柱があるだけで、壁がないので、地震の大揺れに耐えられないことが多い。建築家と工務店さんが頭を寄せ合って強度計算をして、その真ん中の部分に幅半間ほどのしっかりした壁を設ければほぼ大丈夫ということで(うちは平屋だし)、この写真のように目立たない壁を設けてくれました。箪笥の後ろの左半分です。広間にならなくても、昨今は婚礼も葬式も自宅ではやりませんものね。
我が家は築100年を越えていますので、10年ほど前にかなり手を入れました。そのために関東在住の木造建築専門家に来てもらって、アドバイスをもらいました。一番高くついたのは、古い蔵の梁を新しくし、瓦を全部変えて地震で潰れないように屋根を軽くするとともに、漆喰も塗り直すという作業でした。「もう、すごく費用がかかって、こっちが潰れそう」と専門家の人にこぼすと、東京や大阪などではその3倍はかかる、第一請け負ってくれる人がいない、お宅は幸運ですよ、と言われました。田舎の不便さに文句ばかり言っている私ですが、そういう昔ながらの仕事をしてくれる人がまだまだいることは有り難いと思っています。
家の中の塀には瓦を使っていますが、これも壊れたら大変。
いいですね、こういう石塀。びすこさんのご実家の家の全景を見てみたいです。
故郷を思うというのはこういうお家であることがその思いを強いというか、蘇るのでは?と言う気がします。
いまのように、実家もマンションではなかなか得られないの故郷なんでしょうか。
日本の風景の前景が石っぽいのに比べもう一方は木っぽい、これがどちらもなんともそぐわしい。どちらも気持ちの良い空気まで伝わって参ります。
幾年…から話が縦横無尽に広がりまして細かいことがよくわからない私でもついつい楽しさに釣られ読み進めてしまいました、勉強にになりました
幾らか、数年、〇〇余年、適当にいいように使っている僕としては少しは気をつけようかと思いました、最近では周りに合わせるということが仕事を離れてしまったせいか合わせる意欲がわきません、そのかわり気配りとごまかしで乗り切ることにしています、あ、それでも少しは気を使ってるんだと気がついてもらえば目的達成です。あはは