君よ知るやウクライナ――ドイツの黒い森から 34(びすこ)
- クレマチス

- 2022年3月26日
- 読了時間: 13分
ロシアの侵攻開始以来日本でも頻繁に聞かれるようになった(らしい)ウクライナという国名だが、これまであまり馴染みがなかったとはいえ、多くの日本人がそれで連想したのは映画「ひまわり」ではないだろうか。
ひまわりは別にウクライナでなくても欧州各地で栽培されており、優しい黄色の菜の花が終わって少しすると、ドイツでも隣のフランスでも広い畑に一斉に大輪の花が開く。欧州ではこれは食用油になるし、その種をふんだんに乗っけたプチパンも多くて実際的な用途の農産品である。ここで早くも脱線するが、こういうパンをドイツ語でゾンネンブルーメンケルンブロートヒェンという。これで一語です。え? 長すぎる? ゾンネンブルーメンはひまわり、ケルンは種、ブロートヒェンは小さなパンという意味で、ドイツ語では組み合わせた語にスペース(ハイフン)を設けないので、単語の意味を知っていないと分節が分からない。

それはともかく。私もこの映画は好きだし、ヘンリー・マンシーニのテーマ曲を聴くとドクトル・ジバゴの「ララのテーマ」と同じくらいウルウルして来るのだが、ひまわりの話は今回これだけにして、それとの関連で今言及したばかりのドクトル・ジバゴについて少し。
私の頭の中では「ドクトル・ジバゴ」もまた何となくウクライナを思わせるのであった。それでいろいろ調べてみたが、映画の舞台はロシアでモスクワのほかエライど田舎、さらに撮影場所もウクライナではなく北スペインである(ソ連時代のロシアでは撮影できなかったので)。その場所を私はちょうど 10 年前にスペイン北部を旅したときにバスで通って、ガイドさんが誇らし気に「ここで映画撮影が行われました」と説明してくれた。
しかしなぜか私にはこの作品がウクライナと無縁とは思われなかった。暇にあかせてあれこれ調べているうちに、ユーレカ(分かったぞ)!! 作者のボリス・パステルナークがウクライナ人と判明したのである。正確にいうと、両親がウクライナの黒海沿岸の港町オデッサ出身だそうで、画家の父親はモスクワ芸術大学で教え母親も名の知れたピアニストとしてロシアで活動したので、ボリスはモスクワ生まれだが、オデッサを故郷のように感じており、そして一家はかつてウクライナに多かったユダヤ系であった。
どうも私の思い込みはボリス・パステルナークの風貌から来ていたらしい。いわゆる白人の顔とちがって多分に異国風なのである。そしてドイツから東欧、ロシアにかけて多いアシュケナジムではなく、イベリア半島を起点とするセファルディムのユダヤ人だという。何となく肌の色が濃いように思われたのも、父祖の地がスペイン・ポルトガルだったせいか。
ウクライナ人の血を引く有名人は他にも結構いて、日本人の間でもよく知られている一人は作家のソルジェニーツィンである。この人は母親がウクライナ人、ただしユダヤ系ではないが、その代わり(?)父親はコサックの子孫だそうでこれまたユニークな血筋だ。
コサックというのは、今回私も初めて知ったのだが、西方から流れてきた没落貴族と遊牧民系の盗賊から構成されていた集団で、ロシアではその腕力・膂力を買われて軍団として雇われ、のちに正規軍にまでなったという。この話を聞いて、満州の騎馬武装集団、俗にいう「馬賊」が頭に浮かんだ。ソルジェニーツィンの容貌からコサック盗賊団は想像し難いが、中央アジアの遊牧民の末裔というならなるほどテュルク系アジア人の面影がある。
ウクライナの地にはこのコサックの伝統が今も残っているそうだ。ドン川だかボルガだかの辺りにステンカ・ラージンとかいう首領がいて、ペルシアの美姫を拉致してきたんじゃなかったっけ。やはり大陸人はスケールが違う。(このコサック人のことはその昔ダークダックスの歌で知った。)
さて、ウクライナとの繋がりは「ひまわり」ほどには知られてないかもしれないが、ウクライナを舞台にした有名な物語として「屋根の上のヴァイオリン弾き」がある。このミュージカル、私は見たことがないのだけれど、その中で歌われているいくつかのナンバー、特にサンライズ・サンセットなどは好き。ユダヤ人の家族愛をテーマにしただけあって、哀愁のあるオリエンタルなメロデイーは日本人の心の琴線に触れるものがある。オリエンタルという点ではハンガリー人やジプシーの民謡との類似も感じるが、それも道理、どちらもアジアを故郷とする音楽の才能豊かな人々で、奏でる旋律には「東」の香が漂う。
周知の通りユダヤ人は天性の音楽家で、著名な作曲家・指揮者・演奏家はその人口に比して全く不釣り合いなほどに多く、カラヤンのライバルとされたレナード・バーンスタインはユダヤ系ウクライナ人移民の二世である。(バーンスタインはドイツ語でバーンシュタイン、「琥珀」という意味。名前からアシュケナジムのユダヤ人と分かる。)
音楽家ではないが「屋根の上のヴァイオリン弾き」で脚本を担当したジョセフ・スタインもウクライナからのユダヤ系移民で、アメリカの映画界・演劇界で活躍しているユダヤ人は枚挙にいとまがない。(これはユダヤ人の名誉にはならないが、先回のブログで世紀のセクハラ男として顔を出したハーヴェイ・ワインスタインも東欧からのユダヤ人移民の子で、プロデュ―サーとしては大きな成功を納めた。)
「屋根の上の・・・」の原作は「牛乳屋のテヴィエ」といい、それを書いたショレム・アレイヘムはウクライナの現在の首都キエフ郊外の出身で、そこからウクライナを舞台とする物語が誕生した。ユダヤ人庶民の悲喜こもごもの日常が繰り広げられる場所は、シュテットルと呼ばれる、ユダヤ教徒の多い小さな町。このシュテットルという言葉もドイツ語との因縁が深い。
ドイツ語で町のことをシュタットといい、小さな町にはそれにヒェンをつけてシュテットヒェンとする。ひまわり種パンのような小さなブロート(パン)をブロートヒェンというのと同じ。しかし「小さな」という意味の接尾語にはもう一つレ(le)があって、方言っぽいが「シュテットレ」ということもあるので、ユダヤ人の住む小さな町シュテットルはこちらの方から来たのだろう。
ユダヤ人迫害は古代より旧世界のほとんどの地域(ユーラシア大陸に加えて北アフリカも)で見られ、彼らはジプシー以上に流浪の民で一か所に数代にわたり定住することは稀だったが、それでも比較的安定した穏やかな時期というのもあり、シュテットルではイディッシュの大衆文化の慎ましい開花が見られた。イディッシュとはドイツからロシアにかけての広い地域でユダヤ人が用いた古いドイツ語からの派生言語とされ、書くにはヘブライ文字を用いる。「牛乳屋のテヴィエ」もそうしたイディッシュ大衆文化に属する。
上記の通りユダヤ人は音楽の天分豊かな人々で、歌も歌うしピアノも巧みに弾くのだが、追い立てられて逃れる時に携帯できる楽器となればやはりヴァイオリンである。そのためかほとんどの男性の場合ヴァイオリンはお手のものだった。

写真はクレズマーと呼ばれるドイツ・東欧起原のジャンルの音楽を演奏する人々で、「屋根の上の・・・」で使われている音楽もこのクレズマーだそうだ。ユダヤ人の結婚式や祝い事で招待客が賑やかな音楽に合わせて踊っているシーンを映画などに見ることがあるが、それもクレズマーだという。
ユダヤ人のヴァイオリン弾きといえば、数少ないユダヤ人画家の一人シャガールの絵がある。アレイヘムの「牛乳屋のテヴィエ」がミュージカル化に際して「屋根の上のヴィオリン弾き」となったのは、この絵からのインスピレーションか。シャガールはウクライナではなくベラルーシのシュテットルの生まれで、自らの宗教には拘らず、独・仏のキリスト教の教会・聖堂でもステンドグラスの絵を描いたりしている。

こんな風にウクライナの歴史や慣習をちょこまか調べているうち、私はどこかでウクライナに住むユダヤ人の話を読んだことがあると思い出し、記憶をたよりに 11 年前に読んだ「ヴェイユ家の人々・シモーヌとアンドレ」にたどり着いた。
ヴェイユ家について知る日本人はかなり少ないかもしれない。しかし私の年代の特に女性であれば、シモーヌ・ヴェイユという名に思い当る人はいるだろう。この哲学者・神秘主義者は私の学生の頃には高級アイドルのようなところがあって、彼女の著書「神を待ち望む」はインテリ女性の間でちょっとしたブームになった。非インテリの私は読んでないが、多分おそろしく分かりづらいだろうと推察する。というのも、彼女は世界的な数学者の兄アンドレ同様に天才だったからだ。数学の才能もあり、その苦行者・殉教者のような生き方と相まってかのパスカルを想起させる。(ただ、パスカルはさほど難しくないが。)
ブームから 40 年余り後、60 歳代で彼女のことを思い出したきっかけは、こちらの新聞に掲載されていた新本「ヴェイユ家の人々」の批評にたまたま目が留まったためだ。批評というより最初に見たのは著者紹介の写真で、それはド・ゴール大統領がソルボンヌ大で若い女性に賞を渡している場面であった。女性の名はシルヴィー・ヴェイユ、数学者アンドレ・ヴェイユの娘でシモーヌの姪にあたる。

最初にあれっと思ったのは Weil という姓で、ヴェイユというからフランス人の名前だとずっと思っていたのに、Weil となるとこれはドイツ語読みでヴァイル。英語の while に近い言葉で、Weiler というのは小村を指し、ヴァイラーと付く町村はドイツ南西部からフランスのアルザスにかけてあちこちに点在するし、人名にもよくある。またもやトリヴィアになるが、「ローマの休日」や「ベンハー」の監督で知られるウィリアム・ワイラー(英語読み)もアルザス生まれのユダヤ人です。
そうか、アルザスのドイツ・ユダヤ系家族だったのかと知って俄然興味が湧き、フランス語は(非常に)しんどいのでドイツ語訳を取り寄せた。ヴェイユ家は何しろ天才の集まりだから甚だクレイジーな一族で、その奇矯さの源泉を数代前の先祖に遡って叙しているのが興味深い。また、著者のシルヴィーの容姿が叔母に酷似しているため、ひょっとして 34 歳で逝ったシモーヌの隠し子ではないかと噂されたという話なども面白く読める。
が、それを綴るシルヴィーの方は優れた知性を有するにしても天下の異才というタイプではなく、長くアメリカに住み今は児童文学作家として穏やかな人生を歩んでいるらしい。
さてこの本に関して私が最初に興味を持ったのは一族がパリに移る前のアルザス時代のことだったが、もちろんそれについても「素晴らしき先祖―アルザスの側」という章で語られているのだが、その前の章「素晴らしき先祖―ガリツィアの側」の方が私には印象深かった。何しろ私のウクライナの知識は微々たるものだったし、そこのガリツィア地方となると聞いたことすらなかったからだ。
ここでガリツィア地方について説明する必要があるので、簡単な地図をお見せする。紫がポーランド側にある西ガリツィア、オレンジの部分がウクライナの東ガリツィアである。

ガリツィアは国名ではなく古くからの地方の名称で、今の国境が一応画定されたのは 20 世紀初めというから、そのずっと前からあったガリツィアが現在二か国に跨っているのは不思議ではない。どちらの側にもユダヤ人住民は多かった。
因みに、今回ガリツィアという名前に「おや」と反応したのは、先述の北スペイン旅行での目的地がスペインのガリシアだったからだ。正確に言うと、ガリシア州にあるサンチアゴ・デ・コンポステラという、カトリック教徒にとっての聖地への旅で、私はカトリックじゃないしコンポステラにも格別の関心はなかったのだが、近所の人達 15 人ほどがフランス経由でピレネーを越えて行くというのでそのバスに便乗させてもらった。
同じ地名が離れたところにあるのは別に珍しいことではないけれど、これもウクライナのことを調べているうちに、どちらの名称も、もともとそれらの地域がケルト人の定住地だったことに由来すると分かった。ガリア人(またはゴール人)とも呼ばれたケルト人は、ユーラシア大陸の欧州側で最古参の民族とされる。ギリシア・ローマ人なんかよりも、もちろんゲルマン人よりもずっと古い。シーザーの「ガリア戦記」はケルト人追討の記録である。北スペインの目的地の手前で休憩したとき、そこで古いケルト人集落を見て私は興奮した。荘厳で華麗な大聖堂なんかよりよっぽど見る価値があった。
さて、ヴェイユ家の父方はアルザスの人だが、シモーヌたちの母親の方はそのガリツィアの、それも東側にいたユダヤ人であった。シルヴィーは著書の核を成す部分でそのファミリーヒストリーを丹念に辿り、サーガ風に仕立てている。(サーガというのは中世の叙事小説みたいなものだが、一家の歴史を系図風に描いた小説を指すこともある。「楡家の人々」なんかもサーガですね。)
シモーヌから数えて 6 代前のユダヤ人家族は、世帯主がラビ(ユダヤ教の学者・指導者)で、その妻は雑貨店を営んで一家を支えた。一般にユダヤ人は学者と商人に二分されるというが、民族の存続と繁栄のため、知能の優れたラビの家系の子と、商売に長けて生き残り能力のある家系の子とを結婚させることが多い。
シルヴィーはその遠い祖先のことをユーモラスに語り、うつむいて真っ白い髭をユダヤ経典の上にたらした老人は、案外、当時ウクライナ版デュマと称された大衆作家の本などを読んでいたのかもしれないと言っている。その箇所をちょっと抜粋する。
「私にそんな(大作家になろうという)野心はないけれど、当然ながら、自分もシモーヌの母方一族の物語を書いてみたいものだと幾度か考えた。何しろ、田舎で人が冬の夜に好んで読む素敵な娯楽本の要素は、全部揃っているのだ。広大な平原と森、ほぼ年中雪に覆われた果てしないステップ、泥棒、追剥ぎ、狼、コサック、そしてポグロム。」
ここでさらっと記されているが、このポグロムこそは大陸のユダヤ人にとって天刑のごとき惨禍であった。ロシア語で集団的迫害を意味するポグロムは、20 世紀まで間歇的に欧州各地、特に東部において頻発し、嵐のようにユダヤ人を襲った。(欧州人、就中スラブ系の人々のこの根強いユダヤ人憎悪を後日徹底的に利用したのがヒトラーである。ナチスだけで600 万人のユダヤ人は殺せなかった。)
ユダヤ人はその都度、着のみ着のままで、いや、おそらくはヘブライ語のユダヤ経典と現金・金製品だけをもって、可能ならヴァイオリンも携え、別の地へと逃れた。迫害と流離とつかの間の平和。それがユダヤ人の宿命だったのだ。
わけあって私は以前からユダヤ人に興味を持っていたので、その歴史について多少調べるとともに、特に米国で目覚ましい業績をあげている学者や著名な文化人の家系を探ったこともあった。そのとき、ふむ、彼はハンガリーからの移民か、彼女の祖先はポーランドからか、などと知ってなるほどと思っていたのだが、これは全くお門違いの納得であった。
ハンガリーから来たとすれば、それは彼・彼女らの父祖が最後にいた場所が現在のハンガリーだったということにすぎず、おそらくその前には、かつてのオーストリア=ハンガリー帝国や現在の東欧諸国の町や村を転々とさまよい続けたはずである。ロシアやリトアニア、チェコで暮らした時期もあったろう。彼らには国籍など与えられず、そのアイデンティティは常に「ユダヤ人」でしかなかった。
このユダヤ人・ヘブライ人の流浪については、先々回のブログで引用した山崎正和の「世界文明史の試み」に記されているところによると、「ヘブライ人はもとバビロン語で『放浪者』を意味する『ハビル』を語源とし、中東を広くさまよう難民の総称であった」そうだ。
1948 年のイスラエル建国まで数千年の永きにわたり、世界をさすらい続けた民族なのである。シルヴィー・ヴェイユの祖先も例外ではなかった。当初一家が住んでいたのはブロディという小さな町で、リヴィウを中心とするガリツィアには他にも数多くのユダヤ人集落があった。(時代が飛ぶが、現ウクライナ首相はリヴィウ出身。)
シルヴィーは「素晴らしき先祖―ガリツィアの側」の章の終わりで、これらの地で殺されたユダヤ人の数を挙げている。
「 1939 年には 15 万人だったリヴィウのユダヤ人は強制収容所に送られ、数百人だけが生き残った。ブロディの 1 万人のユダヤ人のうち、生き残りは数十人だった・・・イデムの 1 万 2 千人は全滅であった。そして恐ろしい事実を私は語らずにおくことはできない。これらの地は現在すべてウクライナの町なのである。」
そのウクライナは 3 年前に一人のユダヤ人を国の首長とした。選ばれた大統領ゼレンスキーが今ウクライナを守るために生命を賭して闘っていることは、ウクライナ人とユダヤ人の和解を示すものとは言えないだろうか。だが戦禍の中での和解とは。

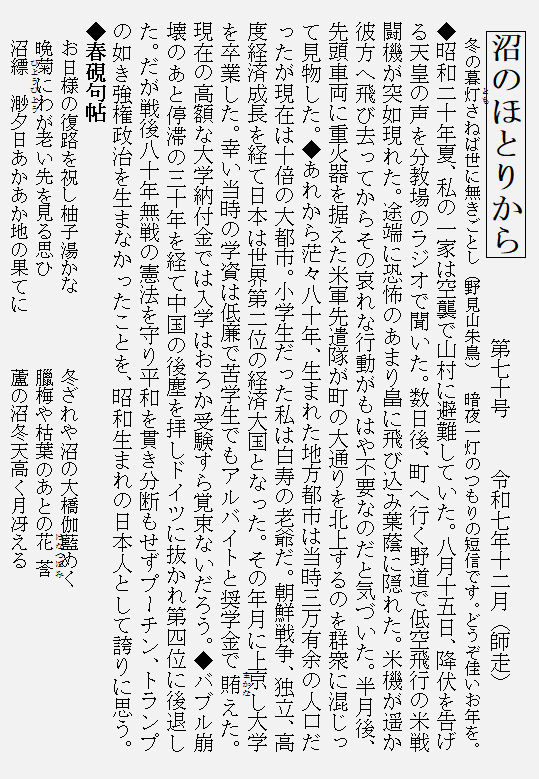


今回のロシアによるウクライナ侵攻でも私のひねくれ者気質が顔を出し、本当にプーチンが100%悪いのだろうか、本当にセレンスキーは英雄なのだろうか、という疑問が消えません。
それでふと思い出して、Foreign Affairs(アメリカの外交問題評議会(CFR)が発行する外交・国際政治専門の隔月発行政治雑誌)の、これまで捨てずにいた何冊かをめくっていると、ありがたや、2014年のロシアによるクリミア併合直後の記事、2017年にトランプが就任してからのNATO加盟国への彼の批判と要求に関する記事等が見つかって、今読んでいるところです。
Foreign Affairsはいわゆるジャーナリズムの範疇ではないので、ロシア人によるロシア(文化)擁護、中央アジアのトルコ系文化とロシアの繋がり等に関する小論文も掲載しており、こういう見解に発表の場を与えるアメリカはさすがだと改めて思いました。ユーラシア大陸へのアメリカの強い関心も、そう言われれば新大陸としてやはりコンプレックスがあるのかと思っていましたが、それよりも、別のところで読んだ「ユーラシア大陸と切り離されれば、米国は大西洋沖の島国でしかなくなる」という説や、そのユーラシアでドイツとロシアが結び付けば世界帝国になるので、これを何とか阻止することが欧州の他の国と米国の共通の目標だった、という地政学的な話にも頷くところがありました。ロシアとドイツはそれらの国々の巧妙な政策に乗って反目しあっているのかもしれない、それを体で感じている一部のドイツ人政治家が半ば意地でロシア寄りになっているのかもしれない・・・などと考えました。
セレンスキーを英国のチャーチルに譬える人達(主としてメディア)がいますが、ドイツを世界地図から消すことを切願し、ドイツ内のナチ抵抗グループからのたびたびの支援要請を無視してドイツ崩壊に手を貸したこの英国政治屋に、私は一片の尊敬の念もありません。
だからセレンスキーが本当に英雄であれば、チャーチルになぞらえられることは不名誉だと思うし、セレンスキーもありきたりの政治家に過ぎないのであれば、それはそれで問題を指摘する人がいるべきだと思う。
彼が3年前に大統領に選ばれたとき、彼が元喜劇役者と知って私は実は横山ノックを思い出し、おやまあ、役者風情(ひどい侮辱語ですが)にいったい何ができる、と思いました。実際、今回のロシアによる侵攻騒動が起きるまで、彼の人気は20%台に落ちていたといいます。それを挽回するために、ロシアを意図的に刺激したのではないか、という見方もあります。プーチンが国内での不人気に対処するためにウクライナを国家の敵にした、という主張に耳を貸すなら、セレンスキーが同じ目的で同じことをしているという意見も、全面的に無視はできません。
そのあたりは私にもよく分かりませんが、ただ、今回の事件で、政治家には「有事型」と「平時型」がいるという説が実感されました。セレンスキーは有事型で、有事に際してその手腕を発揮できるタイプなのでしょう。その点は確かにチャーチルと似ているかもしれません。セレンスキーは元俳優で演劇の素養があるから、こういうドラマチックな状況の中での民衆とのコミュニケーション術に長けているのでしょう。この紛争がどんな形で決着するかはまるで見通せませんが、その暁には、今ほとんど注目を浴びていない首相のシュミハリ氏の行政手腕が求められるかもしれませんね。
知らないことばかり…ウクライナに寄せてお話を伺っていれば…ウクライナの人の顔も気持ちも少しは想像するようになりますね シモーヌ・ヴェイユ、、の系譜の物語、、広大な平原と森、ほぼ年中雪に覆われた果てしないステップ、泥棒、追剥ぎ、狼、コサック、そしてポグロム、、静寂の広い背景に浮かび上がってくる、あるいは潜む、人のつながりと家族と民族の歴史、、大きくも小さくも思惑と怨恨、軋轢、愛憎を長い時の流れに乗せて…少しずつ書き溜めていく…ま、それはそれとして、、 このシリーズを続けていく中でおのずとその形が見えてくるものもある、、話をはぐらかすのが得意な僕と違って興味そのものに一貫性がおありになるびすこさんのこのシリーズどのように流れていくのだろう?振り返ってみたらそこにたくまざるストリームが見えてくる、そんな成り立ちも素敵ですね、楽しみにしています♪