終戦記念日を前に―ドイツの黒い森から 73(びすこ)
- クレマチス

- 2025年8月14日
- 読了時間: 15分
今年初夏にドイツで世間の耳目を集めた話題の一つに、学校教育の一環として生徒たちに強制収容所の見学を義務付けるべき、という教育界の一部の人たちの主張があった。強制収容所とは無論、第二次世界大戦中にヒトラーの第三帝国政権がドイツおよびその周辺の占領地に設けたユダヤ人、反ナチ分子、敵国の捕虜、スパイ容疑者その他を収容するための施設である。(ドイツ語で Konzentrationslager と言い、長いので省略して KZ と呼ばれることが多い。私も今回はこの KZ という略語を使う。因みにこれはドイツ語ではカーツェットと発音する。)
戦後 80 年の今になって少年少女の KZ 見学を必須とすべきとする議論の裏には、2 年近く前のハマスのイスラエル人質事件に端を発して、イスラエルがガザなど貧しいパレスチナ人の地域を攻撃して一定の成果を上げていることに対する欧州左派の反発が激化し、特にドイツの大学町や大都市で暴力的な反ユダヤ運動が蔓延ってユダヤ人憎悪を煽っていることへの懸念がある(そうである)。
そうである、と書いたのは、実のところはそんな簡単な理由づけでは済まない事情がドイツにあるからで、KZ 見学を主張する教育者がみな親ユダヤということはなく、また本気でパレスチナ人たちの反ユダヤ運動を鎮めたいと考えているわけでもなく、むしろ教師たちの間にひそかなユダヤ人嫌いが多いことは明らかだからだ。
戦後ドイツがどれほどナチス時代の罪を反省し贖罪に取り組んでいるか、そのことはいろんな政策・手段で示されている(ようだ)が、私のような、いわば外側の人間が見ても、ドイツ全体に根強いユダヤ人への侮蔑や嫌悪が残っていることは、周囲の人たちとのちょっとした会話からも明らかである。私がある女性の人柄を褒めたとき、元教師の義兄が「でも彼女はユダヤ人だよ」と言ったことを私は聞き捨てにできず、それがどうだというのですか、と言い返して彼を慌てさせたことがあった。この種の経験は直接のものだけでも半ダースを超える。
だから教師連の KZ 見学必須提案は、少し意地悪な見方をすると、ドイツに加え欧米各国でかなりの力を持っているユダヤ人グループや諸団体に対するアリバイ作りのような側面があることは否めない。口ではかつてのような反ユダヤ運動を蘇らせてはならない、と言いながら、実のところ昨今の動きにほくそえんでいる連中も少なくないのである。それも目下ドイツ政府が躍起になって進出を阻んでいる「極右」政党の人々のみならず、親イスラムの欧州左翼の間にその悪意が見え見えなのだ。
この KZ 見学必修科目案は今のところペンディング状態であるが、実は既にいくつかの州では義務付けられている(ドイツでは教育政策は原則として州政府に委ねられる)。その一つが私の住む州の東隣りのバイエルン州で、ナチといえば当然その拠点としてベルリンを連想するが、実際はナチ称揚・ヒトラー崇拝の運動が最も激烈だったのはミュンヘンを州都とするバイエルン州であった。ここはすぐ東にオーストリアが控えていて、ヒトラーがドイツとの国境に近いオーストリアの町の出身であることも関与しているだろうが、ミュンヘンという大都市の、他に類を見ない華やかさがヒトラーを魅了したのかもしれない。彼が本格的な政治活動を開始したのもミュンヘンにおいてであった。第三帝国の様々の大会・集会がここで開かれ、また同州内のニュールンベルクなどもナチにとって行政・立法や業務管理の上で重要な町だった。戦後の連合側による戦争犯罪裁判がニュールンベルクで実施されたのには、そのような事情がある。
したがってこのバイエルン州にも KZ はあり、それもアウシュヴィッツに次いで最も悪名高い収容所の一つであるダッハウ KZ が残っている。そしてここは、私がこれまでに訪れた唯一の KZ でもある。
あれは四半世紀近く前、ドイツで結婚して間もない頃、ある日夫に「ドイツに住むからには一度強制収容所を見ておく必要があるだろう。喜んで行きたい場所ではないが、いわば一つの義務だ」と言われた。その時はそんなものかと思い別に反対も同意もしなかったが、あるときアルザスへの小旅行でその地方の知識がほとんどない私を車で連れて回っていた夫が、広い敷地に古い建物がまばらに立っている所で車を停めて、ここもナチの KZ だよ、入ってみるか、と訊く。何の心の準備もしていなかった私は驚いて咄嗟には答えられず、少し考えてから「またにするわ」と言った。そうか、とそれだけで済んで別に強制はされなかったが、このことで、本当に一度は見ておかなくちゃいけないんだな、と少し本気になった。
それからだいぶ経って、夫がミュンヘン郊外の顧客を訪ねるのに同行した際、彼が商談している間に、いつものように町で買い物をしたりカフェに入ったりする代わりにダッハウのKZ を見学しようと思い立った。調べるとバス・電車・バスと乗り継いで小一時間の距離である。
ダッハウ駅からは収容所直行のバスがあり、それも比較的頻繁なので待つこともなく乗ることができた。不運なことに、乗り合わせたのはアメリカ人のグループで中高年者もいたが大半は若者層であった。彼らの傍若無人ぶりにはもう言葉もないほどで、そもそもかつて何十万人もの無辜の人々が犠牲になった場所へその恐ろしい歴史を記憶するために行こうとしているのに、彼らはまるでピクニック気分で歌い騒ぎ、いい年をした男性たちも彼らに注意することは一切なかった。この人たちはなぜ KZ を訪ねるのだろう、戦争について何を知っているのだろう、そもそもアメリカでどんな教育を受けてきたのだろう。あれこれ考えると吐き気がして、バスが到着するやいなや一番に飛び降りて入り口に向かった。
見学者はアメリカ人を除けばさほど多くはなくて、その彼らもまず門を入ったところで到着早々コーラをラッパ飲みしながら休憩しているので、私は邪魔されずに広い敷地と建物を見て回ることができた。
入って右側には昔の建物が保存されている。そこは独房が多く、取り調べや拷問の行われた部屋もあった。ここに収容されたのは比較的高いステータスの人々、というのも妙な表現だが、要するにドイツ人から見て劣等とは分類されない囚人で、スパイ行為の罪や騒乱の企てを疑われたドイツ人、あるいは英仏など西欧人の捕虜が厳しい尋問を受けた施設であった。
それらを見たときの第一印象は、その少し前に夫の大学同窓会のイベントで訪れたザクセン州はバウツェンという町に残る旧東独の政治犯の刑務所に酷似している、というものだった。建物の外壁が淡い黄色なので一般には「黄色い悲惨」という呼び名で知られるその施設は、東西ドイツ統一までソ連の傀儡として「われわれはナチとは全く無縁である」と主張してきた東独政府によって運営されてきたわけだが、それがよりによってナチの KZ をモデルにしたかのような獄舎とは。

ダッハウ収容所は相当広く、大きな空き地の反対側には、俗にいうバラックのような建屋がポプラ並木を挟んで左右に建っている(写真 1)。一般の囚人はここに収容され、狭い空間に二段ベッドがぎっしりと並ぶ。建物といえばこの左右の二つだけなので不思議に思ったが、入り口の受付で借りてきたガイドフォンの説明によれば、戦後西ドイツ政府はこれら二つを見本として残し、その後ろにずらりと並んでいた同じサイズ・同じ形状の囚人棟は全部取り壊されてそれらのフットプリント、つまり嘗て建物があったと分かる跡だけが残されているのだった。
そしてそれらの建屋には手前から人種国籍によって順位がつけられ、それぞれ西欧人、東欧人、ロシア人、バルカン人等を収容し、最下等のレベルがユダヤ人で一部同性愛者やロマ(ジプシー)も彼らの中にいた。
真ん中の径を歩いて行くと突き当りには記念碑としてチャペルが立っている(写真 2 )。石の礼拝堂のデザインは美術的観点からは興味深い建築物であるが、これがカトリック教のチャペルというのに私は些か抵抗があった。建設は 1960 年で私が KZ を訪れた時期から数えて 50 年ほど昔のことであり、保守的なバイエルン州は新・旧教徒が半ばするドイツで最もカトリック教信者の割合が多い地域だから、それは当然と受け止められたのかもしれない。また、その記念碑の建立を企画したのはミュンヘンのカトリック教会の神父で、彼自身ナチに抵抗して 1941 年から終戦の 1945 年までダッハウに収容されていた。一体に聖職者はナチから危険分子とみなされ、各地の収容所で命を落とした教会の指導者も少なくない。

従ってキリスト教の、それもカトリックの要素をこのモニュメントに付与したかったという意図は分かるが、捕われの聖職者の中にはプロテスタントの牧師もいたし、正教徒の囚人もいたはずで、何より最も残虐な扱いを受けたのはユダヤ教徒である。その施設に特定の宗教の色が濃い慰霊碑というのはいかがなものであろうか。(十字架はユダヤ教では禁忌とされる。)私は日本での靖国神社をめぐる論争を思わずにはいられなかった。
ダッハウを私が訪れたのは 7 月だったので、径の両側に立つ見事なポプラの列が濃い緑色に輝き、風にそよぐ葉末の美しさと、どこまでも澄んだ真っ青な空と、暗黒の過去との対比に胸を打たれた。
・訪ねきて収容所跡にたたずめば鼓動に重なるポプラのさやぎ
そのときの衝撃を託した後日の拙歌である。
見るべき場所は見終えてホテルに戻ろうと門に向かっていたら、13, 4 歳の男の子二人が駆け寄ってきて「一緒に写真を撮りたいのですが、よろしいでしょうか」と英語で訊く。とても感じのいい少年たちでアメリカ人のチンピラボーイとは大違いだったので「もちろんいいですよ」と答えると、後ろの方にいた 3, 4 人の男女がそれを聞いて「私たちも一緒に」と寄ってきて、さらに少し離れたところにいた数人も仲間に加わり、私は 10 人ほどの中学生と一緒にカメラに収まることになった。
お礼を言う彼・彼女らに「あなたたちはどこから来たの」と尋ねると「ここバイエルン州の生徒なんです、見学は授業の一部で」とのことで、学校のプログラムに従っていることが分かったのだった。聞くも恐ろしい KZ で遠くから見学に来た日本人に出遭ったと、先生や両親に写真を見せて報告したかったのかもしれない。そのときの彼らの礼儀正しい振る舞いにドイツの若者を見直し、少々辛すぎた一日の最後が少しだけ明るくなった。
ところで上に述べたアルザスの KZ であるが、結局そこには今日にいたるまで足を踏み入れていないものの、思いがけない所でこの KZ への言及に遭遇することになった。
これも 17,8 年ほど昔の話になるが、「愛を読む人」という映画がアカデミー賞を得て評判になり、日本でもずいぶん話題になったらしい。私はこの種のハリウッド映画にはあまり興味がなかったのだが、あるとき、この KBC でもラインでときどき顔(声?)を出す高校時代の同級生からメールをもらって、「私の娘がこの映画を見て『ハンナ・シュミッツさんがどうして英語で話すのよ』と言っている」とあったので、初めてその原作がドイツ語であることを知り、急いで「朗読者」を取り寄せた。
ここでその原作のあらすじ(映画はいくつか異なる箇所があるらしい)を簡単に紹介すると、主人公で語り手でもあるミヒャエル・ベルクの少年の頃の恋人ハンナ( 1943 年生まれの主人公より 21 歳年長)にはポーランドの KZ の看守として働いた過去があり、さらにその経歴を探ると、戦前はドイツ帝国の領土だったルーマニアのジーベンビュルゲンの生まれ育ちであった。彼女の家庭の背景には触れられていないものの、後に判明したように彼女が「文盲」であったことは、ドイツ人が優遇されていたルーマニアで相当貧しい暮らしぶりだったろうと察せられる。
大学生になったミヒャエルは専門の勉強のためにフランクフルトの戦争犯罪裁判を傍聴に行き、そこで裁かれているハンナの姿を見て驚く。裁判は終始彼女に不利に展開し、当時の看守仲間から身に覚えのない罪まで転嫁されるのだが、彼女らの主張に対する反証には、自分が文字を読めずもちろん書くこともできないことを告白する必要がある。これはハンナには耐えられない屈辱で、それよりは無実の罪を被る方を彼女は選び刑務所に入る。
この裁判から戦争犯罪の重さを知り、ミヒャエルは KZ なるものを見学しようと考えるが、あいにくハンナに関係のあるアウシュヴィッツやその近くの KZ へは当時 1960 年代前半の政情からみて足を運ぶことができない。それでヒッチハイクをしながら彼が訪れたのがアルザスのナッツヴァイラー KZ であった。
原作者のベルンハルト・シュリンクが小説の舞台として選んだのは今私の住むバーデン・ヴュルテンベルク州の北部で、明示はされていないが父親はハイデルベルク大学の教授らしい。一つ明確に地名が出てくるアモールバッハにはオルガンで有名な教会があって、ここには私も 30 年近く前に行ったことがあるが、ちょうどバイエルン州とヘッセン州とバーデン・ヴュルテンベルク州の 3 州が接する地点に位置する。
つまり、その地理的条件を見ると、裁判の行われたフランクフルト(ニュールンベルクの裁判が連合軍占領下であったのに対し、フランクフルトのそれはドイツの司法に基づいて実施された)はミヒャエルの住まいの北方の「近所」であり、また現在はフランスの東北地方であるアルザスも国境のすぐ西側で、ヒッチハイクで行けるほどの距離なのである。
その舞台設定も、私が「朗読者」の原作を(当時のドイツ語読解力で)読み進む上で大いに助けになったのだが、後にこの小説との縁のようなものを感じたのは、ロマの救済プロジェクトに夫が関与していたため、ハンナの生まれ故郷であるルーマニアのジーベンビュルゲンに旅する機会が得られたことだった。
ジーベンビュルゲンはドイツ語名称で一般にはドラキュラで有名なトランシルバニアという名で知られており、そのトランシルバニア地方最大の都市はシビウである。そこもやはりドイツ語ではヘルマンシュタットと呼ばれていた。その歴史的経緯からシビウには今日でもドイツ人旅行者がかなり多く、町には「シラー」という名の書店があって、そこがドイツ人の集合場所になっているのがおかしかった。
日本なら、「朗読者」(というより映画「愛を読む人」)の人気に便乗して、どこかの村に「ハンナの生家」なんてものがでっち上げられ兼ねないが、実を言うとこの旅で私が認識を新たにしたのは、地政学というものの重要性であった。東と南に伸びるカルパチア山脈はさほど高くはなく急峻でもないので、ハンガリー人が先祖と仰ぐアッチラも、ジンギスカンもチムールも、馬を駆って難なくこの山を越えたであろうと思うと、元寇などで大騒ぎした日本の長閑さがありがたいような、滑稽なような。
それにしても、ドイツはどうしてこんなところにまで版図を広げたのだろう。私はこの国に住むまでは、海岸線の長さが限られるドイツはフランスや英国と異なり海外植民地をほとんど持たなかったので、戦後その負の遺産を清算する必要がないのはせめてもの幸運だと思っていたが、それは無知・無見識の為せる勘違いであった。ドイツ人は早い時期から大陸の東方に領土を拡大していたのである。
敗戦でこれら旧ドイツ帝国の住民は戦勝国に激しく追い立てられ、少なからぬドイツ人が虐殺され、危険を承知でかつての領地に残らざるを得なかったドイツ人はロシアやルーマニアなどの政府から人質として利用されて、ドイツ政府は彼らを帰国させるのに莫大な身代金を払った。
しかも、ナチの犠牲者として堂々とドイツという国を弾劾できる他の欧州人と異なり、ドイツ人は戦後 80 年経っても「加害者」のままで、この国の再生のために捨て石となった同胞の悲劇を語ることは許されないのである。それゆえの自虐的な思考様式も捨て鉢な憤怒も、現在の極右の台頭に繋がっているのかもしれない。何かといえばホロコーストを持ち出されてうなだれるしかない口惜しさ。経済・財政的には欧州の繁栄に最も貢献してきたのに、主役を演じるフランスや英国のための縁の下の力持ちに甘んじるほかないという理不尽。
今の欧州を見ていると、結局人々はその歴史から大して学んではいないという思いを深くする。過去の戦争が、今までとは違う形で、つまりもっと洗練された巧妙なやり方で繰り返されるだけではないか。それに対しどんな悪い平和でも戦争よりはいい、という「平和主義者」の声を聞くにつけ、では、日本が海の外への扉を固く閉ざし、身分は固定され移動も言論も厳しく制限され、その代わり戦争も内紛もなかった徳川 250 年の「平和」はどうなんだ、と問いたくなる。
今日本では団塊の世代の「老害」を罵る声が聞かれるが、そもそも私たちの青春時代に「戦争を知らない子供たち」などと誇らかに歌った気楽さをどう評すべきか。先人に対する敬意を欠いていた点では今の若者と変わらない。そして、現在の「生きづらい」世の中に団塊の世代が責任あるとする人々も、40 年、50 年後にはその次の世代に責められる定めにあるのだろう。所詮世の中はその繰り返しなのだ。
私自身は、1940 年代生まれは戦争の後遺症に苦しめられた世代だと思っている。戦争そのものは知らないかもしれないが、戦争の残骸・残滓の中で育った。少なくとも私自身はそう言い切れる。

今から 17 年前の初秋に母が逝った後、その遺品を整理していると刺し子のような布が出てきて、妹が「こんなぼろ布、捨ててもいいわよね」というので見ると、何と千人針ではないか(写真 3 )。父が戦地に赴くとき、祖母と母とがその武勇と無事の帰還を祈念して近所の女性たちに頼んで縫ってもらったもので、千人の縫い手を見つけられたかどうかは知らないが、父はそれを携えて中国の東北地方に発った。そして九死に一生を得て帰還したときには、千人針を持ち帰ることも忘れなかった。
・北支より千人針も帰る秋
この話を私の弟妹は知らない。彼らの育った時代には、戦争の残骸は日本社会からほとんど掻き消されていて、一つには私が長女で祖父母・父母から昔話を聞かされながら育ったこともあって戦争は常に頭のどこかにあるのに対し、三歳下の弟や六歳下の妹の場合には、どんな形であれ、戦争に思いを致しそれについて語るということはなかった。まして千人針など。
万に一つの偶然で命拾いをした父は、同郷の出身者で構成される部隊が朝鮮から出港して大宮島(グアム)で玉砕したことを受け、息子を失った母親や未亡人のための「恩給」受給の手続きに奔走していた時期があった。この手続きは簡単ではなく、殊に田舎の農家の婦人たちにとっては厄介極まりなかったようで、私が 4 歳ぐらいのときにも父がしょっちゅう遺族を訪ねて回っていたのを覚えている。
その記憶があるので、私は今でも帰国中には村の目立たぬ場所にある慰霊碑を訪ねる。
・父母の知る人の名尋(と)め来(く)慰霊塔

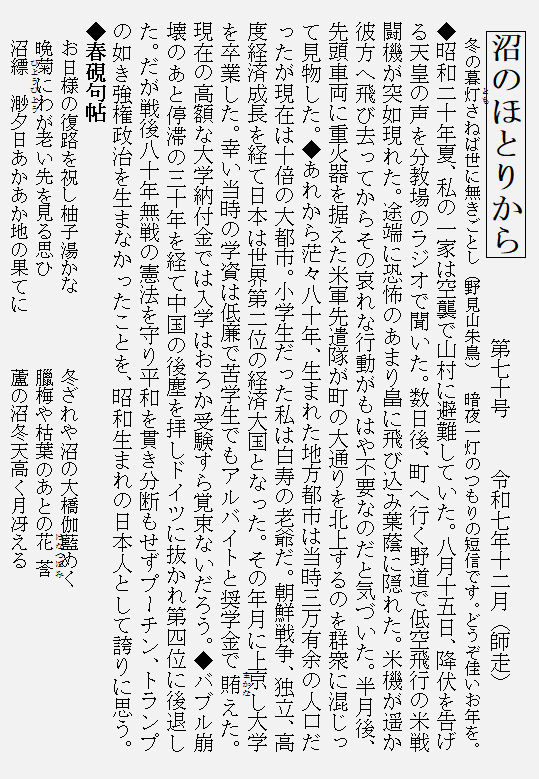


Such a thrilling experience! Sikkim Game keeps me entertained for hours.
Sikkim Game
The customer support team of Big Mumbai is very responsive. They helped me resolve my issue within minutes!
Big Mumbai
Can someone explain how to withdraw winnings from TC Lottery? I just got a small win and want to make sure I do it right.
tc Lottery
The interface of Lottery 7 is smooth and user-friendly, makes the experience enjoyable.
Lottery 7 Game
Okwin App Download was super easy, and it runs perfectly on my phone. OKWin , OKWin Login , OKWin Game , OK Win